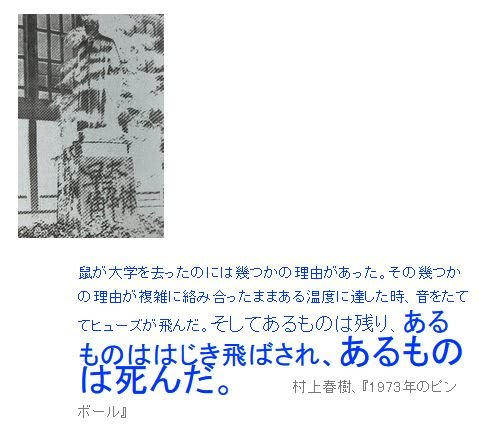
全共闘を体験した人は、積極的かつ過激だった人だけに少なめに限定しても、十万人はいる。これらの人は、苦悩の中で沈黙したり、新たな道を模索したり、あの全共闘時代と、続く鉛色の十年の意味をとらえ返しつつ生きている。
呉智英、『インテリ大戦争』、1982年
1980年代前半、おいらが十代の頃に読んだ呉智英さんは"全共闘「崩れ」"だった。呉智英さんが本を出し始めたこの頃(1980年代初頭)、村上春樹もデビューしていたのだ。おいらが村上春樹の『風の歌を聴け』、『1973年のピンボール』、『羊をめぐる冒険』を読んだのははたち位の頃で、この3部作が出た時期からやや時間が経っていた。中曽根内閣300議席の頃だ。そして、『風の歌を聴け』は"全共闘「崩れ」"の話らしいと推定できた。(関連愚記事: 「傷痕文学」なのだ)
その村上春樹の『職業としての小説家』に書いてある;
僕が早稲田大学に入学し、東京に出てきたのは一九六〇年代の末期、ちょうど学園紛争の嵐が吹きまくっていた頃で、大学は長期にわたって封鎖されていました。最初は学生ストライキのせいで、あとの方は大学側によるロックアウトのせいで。そのあいだ授業はほとんどおこなわれず、おかげで(というか)僕はかなり出鱈目な学生生活を送ることになりました。
僕はもともとグループに入って、みんなと一緒に何かをするのが不得意で、そのせいでセクトには加わりませんでしたが、基本的には学生運動を支持していたし、個人的な範囲でできる限りの行動はとりました。でも反体制セクト間の対立が深まり、いわゆる「内ゲバ」で人の命があっさりと奪われるようになってからは(僕らがいつも使っていた文学部の教室でも、ノンポリの学生が一人殺害されました)、多くの学生と同じように、その運動のあり方の幻滅を感じるようになりました。そこには何か間違ったもの、正しくないものが含まれている。健全な想像力が失われてしまっている。そういう気がしました。そして結局のところ、その激しい嵐が吹き去ったあと、僕らの心に残されたものは、後味の悪い失望感だけでした。どれだけそこに正しいスローガンがあり、美しいメッセージがあっても、その正しさを支えきるだけの魂の力が、モラルの力がなければ、すべては空虚な言葉の羅列に過ぎない。僕がそのとき身をもって学んだのは、そして今でも確信し続けているのは、そういうことです。言葉には確かな力がある。しかしその力がある。しかしその力は正しいものではなくてはならない。少なくとも公正なものでなくてはならない。言葉が一人歩きをしてしまってはならない。
(村上春樹、『職業としての小説家』、第二回 小説家になった頃)
一方;
最初に小説を書こうとしたとき、いったいどんなことを書けばいいのか、まったく考えが浮かびませんでした。僕は親の世代のように戦争を体験していないし、ひとつ上の世代の人たちのように戦後の混乱や飢えも経験していないし、とくに革命も体験していないし(革命もどきの体験ならありますが、それはとくに語りたいようなしろものではありませんでした)、熾烈な虐待や差別にあった覚えもありません。
(村上春樹、『職業としての小説家』、第五回 さて、何を書けばいいのか?)
つまり、あの「大学紛争」は革命もどきであったと村上春樹は認識している。これは、"革命的な、あまりに、革命的な"という絓秀実さんの認識とは違うことを示している。
なお、冒頭の呉智英さんの文章は一部抜き書きであり、省略がある。省略部分も示す。そもそも、この文章は津村喬の本に対する書評の冒頭である;
全共闘の恥部 -津村喬 「全共闘―持続と転形-」 五月社
津村喬は、全共闘の恥部である。全共闘を体験した人は、積極的かつ過激だった人だけに少なめに限定しても、十万人はいる。これらの人は、苦悩の中で沈黙したり、新たな道を模索したり、あの全共闘時代と、続く鉛色の十年の意味をとらえ返しつつ生きている。その中で、津村喬だけが、何の臆面も内省もなく、全共闘を口にしている。
津村喬は1948年生まれ。村上春樹は1949年(早)生まれ。ともに、早大文学部。同時期に同じ場所にいたのだろう。村上春樹は津村喬のアジビラを読んでいたのかもしれない。
■ まとめ
呉智英、津村喬、絓秀実、そして、村上春樹。 みんな「サラリーマン」[1]にならずに済んでるらしい。
[1]
こういうことを言うと、あるいは腹を立てる人もいるかもしれませんが、出版社の編集者は日本の場合、専門職といっても、結局のところサラリーマンですから、(以下略)[強調 いか@] (村上春樹、『職業としての小説家』、第六回 時間を味方につける―長編小説を書くこと)









