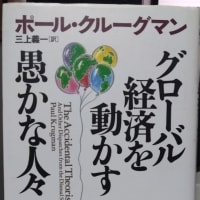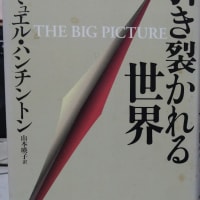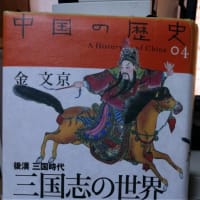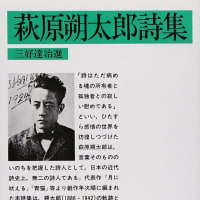LGBT法の成立を急ぐ人たちは、日本と欧米との違いに目を向けたくないようだ。フーコーがロサンゼルスのゲイ新聞「唱道者」(1984年8月7月号)のインタビューに応じ、ホモセクシュアルについて語っている。
フーコーは「古代以来、何世紀ものあいだ、友情は社会関係のきわめて重要な様式なのであって、その様式につつまれながら男性はある種の自由を、ある種の選択の可能性をもっていたし、その様式はしかも同時に強烈な情愛の関係でもありました。この種の友情が、少なくとも男性社会で消滅するのが見られるのは16世紀と17世紀のことだと、ぼくは思う」との見方を示した。
つまり、それまでは男同士の性などは問題にならず、警察は司法制度と衝突するようになったのは、18世紀からだというのだ。フーコーは「友情」の消滅とからめて論じたのである。「友情」が認められている社会では、男同士が愛し合っていようがいまいが重要なことではなかったからである。
しかし、文化的に容認された関係としての「友情」が認められなければ、「男同士がいっしょにいて何をやっているのか」という問いが出され、同性愛が社会的で政治的で医学的な問題となったというのだ。
それはあくまでも欧米でのことではないだろうか。日本においては男同士の付き合いが変な目でみられることはほとんどない。「男の友情」が歌謡曲の有力なテーマになり、外部から見れば同性愛と誤解されるほどに、親密な男の「友情」が未だに維持されているのではないか。
また、フーコーは、アブノーマルな性的な行為というのを、肉体的を源泉とした創造過程とみていえるが、日本文化における性愛の技術は、欧米よりも格段に進んでいるのではないだろうか。多神教の日本人と、一神教の欧米とでは、性に対する考え方が異なるのである。
エマニュエル米国大使のように、あたかも日本人が野蛮であるかのように蔑み、一方的に自分たちの価値観を押し付けるのは、内政干渉以外の何物でもない。そんな人間が押し付けるような法律を拙速に通せば、ありもしない差別とかいうことを我が国に持ち込み、事を荒立てるだけなのである。