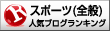天租神社(大塚)
大塚の天祖神社は、鎌倉時代末の元亨年間(1321~4)に、巣鴨村(巣鴨村は現在の巣鴨・西巣鴨・北大塚・南大塚・東池袋・上池袋一丁目の広大な範囲でした)の鎮守として、領主の豊島氏が創建しました。
ご祭神は、天照大神です。
古くは神明社・神明宮と呼ばれていて、江戸時代には十羅刹女堂も祀られていましたが、明治6年(1873年)に天祖神社と改称した際に分離、今に至ります。
そびえ立つ大きなイチョウの木。右が雌、左が雄です。
天祖神社は何と言ってもご神木である「夫婦公孫樹(めおといちょう)」が見応えあります。
推定樹齢は約600年、昭和20年(1945年)4月13日の城北大空襲により被災し、一時期は枯れることも懸念されたようですが、今では見事に復活して大きな枝葉を広げています。
さざれ石
もう一つ、イチョウの木の左側に密かに置いてある天然記念物があります。
国家「君が代」で歌われる「さざれ石」です。
産地は岐阜県揖斐郡春日村で、昭和55年(1980年)にサンシャインシティから分割奉納されたものとのこと。
(7月13日記)
大塚の天祖神社は、鎌倉時代末の元亨年間(1321~4)に、巣鴨村(巣鴨村は現在の巣鴨・西巣鴨・北大塚・南大塚・東池袋・上池袋一丁目の広大な範囲でした)の鎮守として、領主の豊島氏が創建しました。
ご祭神は、天照大神です。
古くは神明社・神明宮と呼ばれていて、江戸時代には十羅刹女堂も祀られていましたが、明治6年(1873年)に天祖神社と改称した際に分離、今に至ります。
そびえ立つ大きなイチョウの木。右が雌、左が雄です。
天祖神社は何と言ってもご神木である「夫婦公孫樹(めおといちょう)」が見応えあります。
推定樹齢は約600年、昭和20年(1945年)4月13日の城北大空襲により被災し、一時期は枯れることも懸念されたようですが、今では見事に復活して大きな枝葉を広げています。
さざれ石
もう一つ、イチョウの木の左側に密かに置いてある天然記念物があります。
国家「君が代」で歌われる「さざれ石」です。
産地は岐阜県揖斐郡春日村で、昭和55年(1980年)にサンシャインシティから分割奉納されたものとのこと。
(7月13日記)