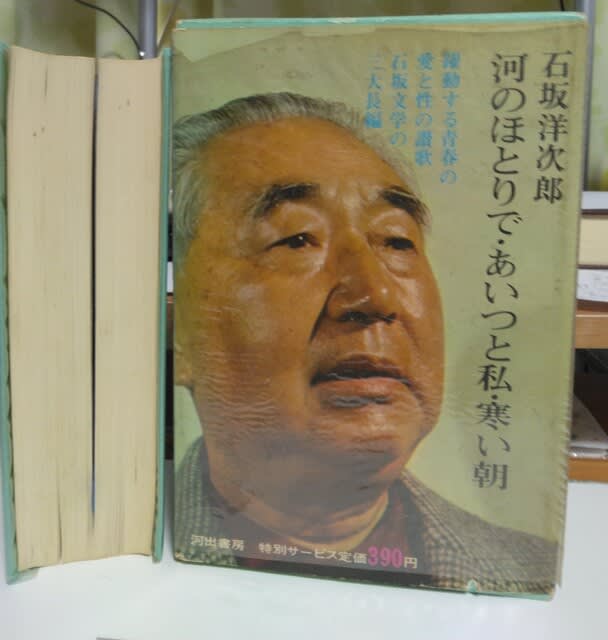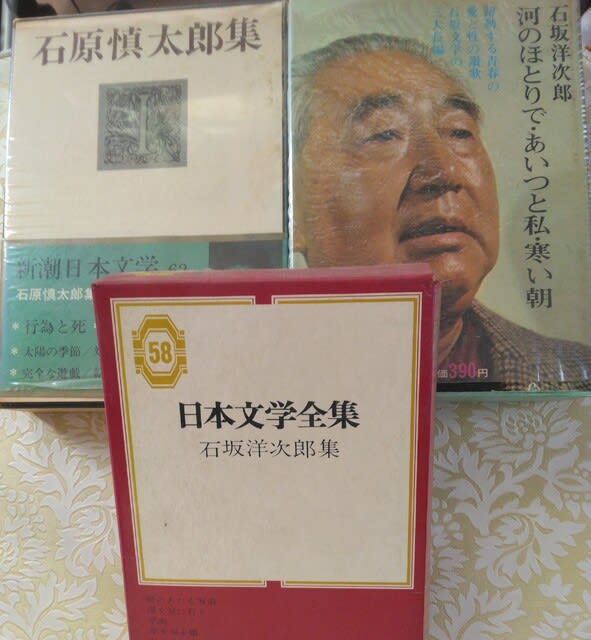同級生友達のチコちゃんの旦那様が亡くなって、つーくんと通夜に言って来た。
旦那さまは病気がちで、彼女は20年以上もずっと面倒見やら看病やらを献身的に続けて来たのだった。
彼女も我々も昭和25年生まれの「五黄の寅」、36年に一度訪れる星だ。
五黄の寅と丙午(ひのえうま)の女は亭主を食い殺すと言われてきたが、周囲を見るに、たしかに気が強く前向きで活きが良く、辛抱強い女性が多いが、昔の女ながら、亭主の後ろで静かにしているようなタイプは少ない、バリバリと家庭の切り盛りをやっていく
けれども亭主を食い殺すどころか、とても大事にしている。
沢村貞子さんの「私の浅草」を読んでいる、沢村さんは五黄の寅ではない
私の父よりも16歳も年上の明治41年生まれだから、このブログをご覧の皆さんの半分は知らないかもしれない。
私が子供の頃には、よくテレビに出ていた女優さんで、浅草生まれだから生きのいい江戸弁で話す人だった。
ネットによれば、父親の竹芝傳蔵(本名 加藤伝太郎)は歌舞伎作者、母は一般女性で、兄、國太郎は歌舞伎役者、弟は名俳優の加藤大介
俳優の長門裕之(妻は南田洋子)、津川雅彦(妻は朝丘雪路)は國太郎の息子で、貞子の甥になる。
父の伝太郎、兄の國太郎、甥の津川雅彦はいずれも花筋が通った美男子で女性にもてまくったそうだ。
そんな家系にあって、加藤大介さんは俗にいう小太りの「ずんぐりむっくり」で顔立ちはふっくらで目がパチリ、きれいな顔立ちだ
戦争中は南洋の島にいて部隊ごと孤立、日本軍は撤退、アメリカ軍は素通りしたから平和ではあったが、食糧不足、マラリアで命を落とす兵隊も少なくなかったと言う。
そんなみんなを元気づけるために、内地で役者だった加藤さんは軍隊劇団を作って毎日部隊内で公演したと言う
それが「南の島に雪が降る」という小説や映画になった
そういえば聞いたことがある、これを思い出したので、今度小説と映画を見てみたいと思うようになった。
沢村貞子さんは1996年に88歳で永眠されたが、俳優の他、随筆家でもあり、「私の浅草」はその中の一冊、少女時代の浅草生活の思い出が詰まっている。
私の父の叔母も明治生まれで、浅草に住んでいたので同年代かと思い興味を持った次第である。
そして知るにつれ、親しみを感じて来た、父の叔母さんは明治40年生まれ、沢村さんは41年生まれと1歳違い。
住まいは、叔母さんは浅草象潟町、沢村さんは浅草猿若町で距離にして400mあるかないかの近く、道すがら、あるいは浅草寺境内や仲見世で何度もすれちがったことくらいあるかもしれない。
叔母さんは浅草で昭和20年の大空襲で亡くなったが、沢村さん一家は京都に疎開していて助かった。
だが大正12年の関東大震災では、お互い酷い災難を被った。
沢村さんの姉は、幼いうちに伯母さん宅へ養女に出されたそうだが、名前はせい子さん、父の叔母もセイという名なので、ここにも意味のない共通を見つけて嬉しがっている。
本の中で「五黄の寅」という記事を見つけた、「父はそれは女性にモテモテで、そこらの役者より、よっぽど人気があった、浮気のお相手も粋筋の女性ばかりで競って父に熱を上げていた」と言う。
しかし齢を取って仕事が干上がってからは、金の切れ目が縁の切れ目で全くもてなくなった。
関東大震災では焼け出されて、すっかりしょげかえっていて気丈な母の世話になりっぱなしだったそうだ
「かあちゃんにゃあ敵わねぇよ、なにしろあいつは、五黄の寅だからな・・
俺は七赤の兎と来てやがる」
五黄の寅は相手を食い殺してしまうほどに強いのに、七赤の兎は、気が弱く優しい星だそうだ。(色男 金と力はなかりけり)を地で行っている。
なるほど、ここでも五黄の寅の女性の逞しさが描かれている
同じ五黄の寅でも、男どもは空威張りでからっきし意気地がない、七赤の兎とあまりかわらない、五黄の寅の特性は女性だけに当てはまるようだ。