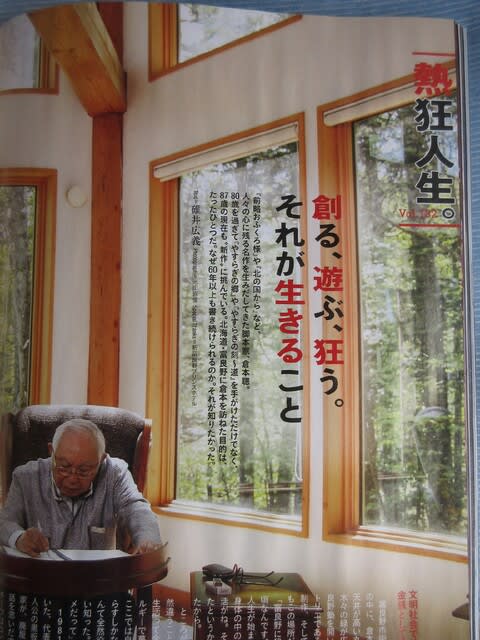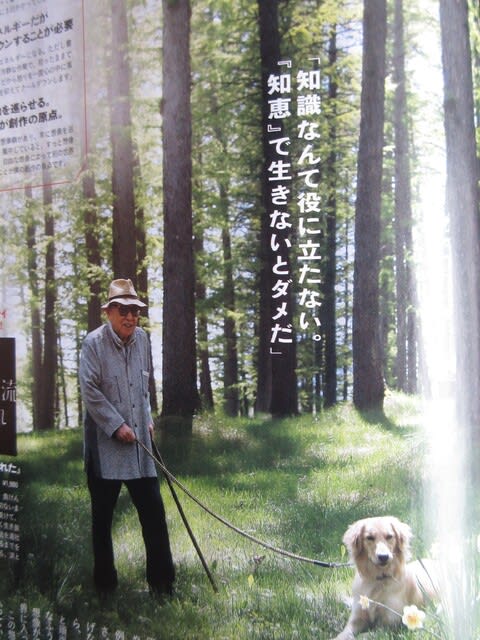<週刊テレビ評>
再出発描く2本の夏ドラマ
気になる若くない「新人」たち
各局で「夏ドラマ」が始まった。その中で気になる「新人」が2人いる。新人俳優ではない。それまでのキャリアを捨て、新天地で初めての仕事に就いた登場人物のことだ。2人とも既に若者ではないという点で共通している。
1人目は日曜劇場「オールドルーキー」(TBS系)の主人公、新町亮太郎(綾野剛)だ。37歳の元サッカー日本代表選手。J3のチームに所属し代表への復帰を目指していたが、突然チームが解散となり、引退を余儀なくされる。ハローワークで紹介された仕事にトライするが、うまくいかない。
そんな新町を拾ってくれたのが「スポーツマネジメント」の専門会社だ。有望なアスリートのために練習環境を整え、宣伝活動やCM契約などをフォローする。慣れない仕事に戸惑う新町だが、マネジメントという仕事の面白さを少しずつ理解していく。何より、スポーツ選手の気持ちを理解できる点が強みだ。
新町にとって最大の課題は、忘れられない過去の栄光と、捨てきれないサッカーへの未練だろう。それは一般社会とも重なる。かつての肩書や実績にこだわる人間ほど、転職先で浮いてしまうことが多い。倒産やリストラなどで、余儀なく転職した「新人」のケーススタディーとして、彼の今後を注視していきたい。
そしてもう1人の新人が、「ユニコーンに乗って」(同)の小鳥智志(西島秀俊)だ。48歳の元銀行マン。ヒロインの成川佐奈(永野芽郁)がCEOを務める教育系IT企業に転職してきた。誰もが平等に学べる場を作りたいという佐奈の理念に共感したからだ。
新町とは違い、小鳥は自らの意思で銀行を辞め、未知の世界に飛び込んできた。しかし若者ばかりの会社では、即戦力とは言えないおじさんはお荷物扱いとなる。また仕事以前のコミュニケーションも容易ではない。今後、世代間ギャップや異なる価値観が物語に起伏を生んでいくはずだ。
若き女性経営者と、転職してきて彼女の部下となる中年男の物語は、米映画「マイ・インターン」(2015年)を想起させる。アン・ハサウェイが社長を務める通販会社で採用されたのが、ロバート・デニーロだ。当初は異質だったおじさんが徐々に存在感を増し、女性社長との信頼関係が生まれる。小鳥もまた、いい意味で周囲を変えていくのではないだろうか。
元スター選手のプライドと情けなさをバランスよく演じる綾野。常識とユーモアを併せ持つ中年男をひょうひょうと演じる西島。やはり2人の新人から目が離せない。
(毎日新聞「週刊テレビ評」2022.07.09 夕刊)