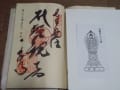中央公園から歩いて瓦町駅に到着する。駅は「瓦町FLAG」という駅ビルと一体化している。

このビルは1990年代に、瓦町駅の駅舎建て替えも含めた再開発のために建てられたもので、当初はことでんとそごうが共同出資した「コトデンそごう」としてオープンした。しかしそごう自体の低迷や店舗としての売り上げも伸びず、ことでんの本体の経営にも影響した。2000年代に入って天満屋に経営を引き継ぎ、一時は業績も回復したがやはり低迷、2014年に閉店した。現在はことでんが双日グループと提携し、2015年からは百貨店方式ではなく複合ビルという形で「瓦町FLAG」という名前になった。高松の中心にある瓦町において、街の「フラッグシップ」として未来に向けた旗を掲げるという意図がある。現在も店舗のリニューアルが進められており、近日オープンのフロアもある。


バッグをコインロッカーに収めて、10時26分発のことでん志度線の志度行きに乗る。駅ビルの建設にともない、志度線は琴平線、長尾線と線路が分断され、改札口の中だがホームも完全に独立している。ことでんはこの3線で成り立っていて、瓦町にはその3線が集まる。ただそれぞれがバラバラのダイヤを組んでいて独立運転しているのは、大阪でいうなれば阪急の梅田か十三かを連想させる。

行き止まり式のホームから出発。土曜日の午前中、乗客もまばらである。また駅ごとに下車する客のほうが多いので数も少しずつ減っていく。そのうち私の乗った車両には他の乗客がいなくなった。


前回の四国めぐりでは車窓に広がる屋島、そして五剣山にある札所を回った。いずれも香川独特の地形に歴史を持つところだった。今回は前回下車した琴電屋島、その先の八栗(前回の帰りは八栗から乗らず、少し南にあるJRの古高松南から乗ったのだが)から次へのつなぎということにする。



国道11号線、その先にJR高徳線の線路を見ながら東に進む。塩屋を過ぎて急なカーブに差し掛かるところで、車窓左手に海が姿を現す。志度にかけてちょうど入り組んでいるところで波もほとんどない。こうした地形を利用してか、この一帯では牡蠣の養殖も盛んで、牡蠣を殻つきのまま豪快に鉄板で焼く牡蠣焼きが名物だという。

房前では線路横に愛染寺という寺がある。どこかアピールしてくる感じだったのでスマホで検索すると、江戸時代に現在の四国八十八所のルートを定めてPRし、いわば「四国遍路の父」とも言える真念法師の終焉の地だという。八栗寺から志度寺までガチで歩く遍路ならその途中で立ち寄るであろうスポットだ。



11時ちょうどに終点の志度に到着する。ここまでで乗客も減っていて、下車したのは私ともう一人だけ。折り返しの列車にはそれより多い数の客が乗り込んだのが救いといえる。


さてこれから志度寺を目指すが、少し早く昼食とする。ことでんの志度駅のすぐ南には国道11号線を挟んでJR高徳線の志度駅があり、その西隣にうどん店がある。さぬきうどんについていわゆる通ではないのだが、「牟礼製麺」というこの店に入ってみる。

中は昔ながらの雰囲気で地元の人向けのうどん店という感じである。標準的なセルフ方式ということで、かけうどん(大)を注文し、天ぷら、おにぎりも取る。だしもいりこと昆布という讃岐のスタンダードな味だ。
ただ牟礼製麺で扱うのはうどんだけではないようだ。先客が食べていたのは日本そばだったし、後から入った客は中華そば、次の客は中華そば(大)を注文する。後で知ったことだが、この牟礼製麺は製麺所としてうどんだけではなく日本そば、中華そばも扱うそうで、グルメサイトの口コミを見るとうどん以上に中華そばが評判のようだ。他の客が注文した中華そばをちらりと見ると、純和風のスープに入った昔ながらの中華そばで、1杯300円というこちらも昔ながらの価格である。現在ラーメンの専門店に行けば1杯800円、1000円も当たり前というご時世だが、その中にあって300円とは、その辺の社員食堂かそれ以下の値段である。そうしたことは知らなかったのでこの日はそのままうどんをいただいたが、もし次に志度駅前に来ることがあれば中華そばに挑戦しようと思う。
志度寺へは駅から徒歩でも数分で、現在の国道11号線の前身の一部である旧志度街道を歩く。現在は「源内通り」と呼ばれている。
「源内」とは江戸中期の科学者・平賀源内である。この志度の出身ということで地元の人は「源内先生」「源内さん」として親しんでいる。この平賀源内という人物、先に「科学者」と書いたが、その肩書はもっと他にあり、ウィキペディアの記載では「本草学者、地質学者、蘭学者、医者、殖産事業家、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、蘭画家、発明家として知られる」とある。

街道沿いには駅の東西に分かれて旧宅と記念館があるが、人物紹介や資料展示は志度寺寄りの記念館のほうということでそちらに向かう。中の撮影は禁止なので建物の外観のみの写真だが・・・。
中は源内の志度、高松藩での生い立ちに始まり、諸国行脚や数々の業績について触れられている。奥のシアター室では源内の生涯を10分ほどのアニメで紹介しているので、まずそちらを見たほうがわかりやすい。子どもの頃に読んだ歴史漫画のシリーズの中に平賀源内があり、さまざまなことを手掛けながらなかなか世に認められないもどかしさが描かれていたのを思い出す。。
源内は12歳の時に、掛軸に細工をした「お神酒天神」というのを作った。掛軸の天神様の顔のところをくり抜き、その後ろに白色と赤色に塗った紙を垂らしておく。普段は白色の顔だが、特利を置いて糸を引っ張るようにすると、紙がずり上がって顔が赤くなったように見える仕掛けである(記念館の売店ではそのペーパークラフトも売られている)。源内はこれで大人たちを驚かせ、「天狗小僧」と呼ばれた。その評判で藩医のもとで本草学を学ぶようになり、長崎にも留学してオランダ語や医学、絵画を学んだ。
その後も江戸や長崎で学び、それを活かした源内の業績を並べてみると、
・江戸で薬草の物産会を開催した。
・伊豆や秩父で鉱山開発を行った。
・さまざまなペンネームで『根南志具佐』や『風流志道軒伝』などの戯作、『神霊矢口渡』などの浄瑠璃脚本(今でも演じられる)を書いた。
・今でも香川で「源内焼」と呼ばれる陶芸の技法を開拓した。
・火浣布(かかんぷ)という、耐火性のある布を開発した。他にも発明、開発品は数々。
・西洋画の技法を伝え、司馬江漢や『解体新書』の挿絵を担当した秋田藩の小田野直武らに影響を与えた。
などなどあるが、中でも有名なのは、
・オランダで発明されたエレキテルを修理して復元し、医療器具として用いた(実際は見世物だったようだが)。
・土用の丑の日にうなぎの蒲焼を食べることをPRした。
の2つだろう。
記念館にはエレキテルの模型が置かれて、その原理を体験することができる。エレキテルはハンドルを回して摩擦により発生する静電気をエネルギーとして箱の中の蓄電池のようなものに集めておき、銅線どうしを近づけることで放電する仕組みである。ハンドルを回してピカッと光るのも見ることができ、大型のものだと蛍光灯も一瞬点くほどのものだ。修理と言っても図面やマニュアルがあるわけではなく、自分の力だけで復元させたというのが源内の優れた所以である。
こうして見ると源内の業績は数々あるのだが、歴史的に誰もが知っている有名人というほどでもないだろう。当時の人から見れば奇才すぎてついて行けなかったとか、現代につながる実用的な発明ではなかったとか、最期は人を殺めた疑いで牢に入れられ獄中死したとかで、評価がいろいろ分かれているのだろう。あまりにもマルチすぎていわゆる「器用貧乏」だった側面も否定できない。
讃岐の天才、偉人ということでまず挙げられるのは四国八十八所の巡拝の対象である弘法大師空海だろう。弘法大師に関する伝説の数々はこれまでの巡拝の中、あるいは歴史の時間で登場する業績にも現れている。空海が讃岐の西・善通寺ゆかりなのに対抗するわけではないが、讃岐の東・志度にはもう一人の天才、平賀源内がいる。もう少し後の時代に生まれていたら、果たしてどのようなことを成しただろうか。




記念館の近くにさぬき市役所があり、建物のすぐ裏は海岸である。また市役所にはコミュニティバスが待機していて、車体には「上がり三ヵ寺まいり」のラッピングが施されている。コミュニティバスには結願の帰りに乗る予定だ。改めて上がりに挑むべく、志度寺に向かう・・・。


 源内通りを歩く。沿道には平賀源内が残した言葉を紹介するパネルも飾られている。ちょうど通りの突き当たりが志度寺の山門である。五重塔も見える。山門と五重塔の組み合わせはなかなか様になる。
源内通りを歩く。沿道には平賀源内が残した言葉を紹介するパネルも飾られている。ちょうど通りの突き当たりが志度寺の山門である。五重塔も見える。山門と五重塔の組み合わせはなかなか様になる。
 山門の手前に塔頭寺院の自性院があり、「源内さんのお墓」の立て札がある。源内は江戸で獄中死して、親友の杉田玄白らの手で浅草に葬られたが、自性院が平賀家の菩提寺のため、参り墓を建てたとも実際に分骨されたとも言われている。いずれにしても志度の人たちにとって今に至るまでの偉人であることがうかがえる。
山門の手前に塔頭寺院の自性院があり、「源内さんのお墓」の立て札がある。源内は江戸で獄中死して、親友の杉田玄白らの手で浅草に葬られたが、自性院が平賀家の菩提寺のため、参り墓を建てたとも実際に分骨されたとも言われている。いずれにしても志度の人たちにとって今に至るまでの偉人であることがうかがえる。


 さて志度寺、山門をくぐるとやたらと緑が多く感じる。ただ何だか雑然と並んでいるような・・・。境内というよりどこかの屋敷の手入れされていない庭に入ったかのようである。木の間を縫うように標識に従って本堂に出る。まずはここでお勤めである。
さて志度寺、山門をくぐるとやたらと緑が多く感じる。ただ何だか雑然と並んでいるような・・・。境内というよりどこかの屋敷の手入れされていない庭に入ったかのようである。木の間を縫うように標識に従って本堂に出る。まずはここでお勤めである。 志度寺の歴史は古いようで、7世紀の前半、推古天皇の時代に、志度の海岸に流れ着いた檜の霊木を尼が持ち帰り、十一面観音像を彫って祀ったのが始めとされている。奈良時代に藤原不比等やその子房前らの手で伽藍が建てられ(だから先ほどその駅名があったのかな)、その後も栄えたが、戦国時代には土佐の長宗我部元親にも攻められ(阿波や讃岐の札所はほとんど彼の戦火に何らかの形で巻き込まれたように思う)、江戸時代に高松松平家の手で復興した歴史を持つ。
志度寺の歴史は古いようで、7世紀の前半、推古天皇の時代に、志度の海岸に流れ着いた檜の霊木を尼が持ち帰り、十一面観音像を彫って祀ったのが始めとされている。奈良時代に藤原不比等やその子房前らの手で伽藍が建てられ(だから先ほどその駅名があったのかな)、その後も栄えたが、戦国時代には土佐の長宗我部元親にも攻められ(阿波や讃岐の札所はほとんど彼の戦火に何らかの形で巻き込まれたように思う)、江戸時代に高松松平家の手で復興した歴史を持つ。
 本堂と並ぶ大師堂にも手を合わせる。
本堂と並ぶ大師堂にも手を合わせる。


 この後で三尊像や閻魔堂、薬師堂などを回るが、どこか違和感を覚える。先に「どこかの屋敷の手入れされていない庭」と書いたが、よく見れば手入れはされているものの、植木鉢なども並んでいてどこかの植木市の屋外売り場に見えなくもない。どういう経緯でそうなったのかはわからないが、山門前から見た姿が由緒ある大寺の風情だったのに対して、境内が無駄に草木の生える状態だったのは意外である。
この後で三尊像や閻魔堂、薬師堂などを回るが、どこか違和感を覚える。先に「どこかの屋敷の手入れされていない庭」と書いたが、よく見れば手入れはされているものの、植木鉢なども並んでいてどこかの植木市の屋外売り場に見えなくもない。どういう経緯でそうなったのかはわからないが、山門前から見た姿が由緒ある大寺の風情だったのに対して、境内が無駄に草木の生える状態だったのは意外である。 あくまで訪ねた時の印象なので、時季を変えれば違った景色が見られることだろう。
あくまで訪ねた時の印象なので、時季を変えれば違った景色が見られることだろう。 さて時刻は12時半前、志度寺から次の長尾寺までは約7キロ。この時間なので歩きへのプレッシャーはない。ともかく南に向けて歩き始める・・・。
さて時刻は12時半前、志度寺から次の長尾寺までは約7キロ。この時間なので歩きへのプレッシャーはない。ともかく南に向けて歩き始める・・・。