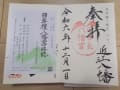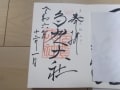11月30日~12月1日の神仏霊場巡拝の道めぐりは4ヶ所を回り、その前に西国三十三所の谷汲山華厳寺にも参詣した。そして近江八幡の日牟禮八幡宮で終了。まだレンタカーの返却まで時間があるので、八幡宮のすぐ横から出る八幡山ロープウェーで山上にある八幡山城跡に向かうことにする。
11月30日~12月1日の神仏霊場巡拝の道めぐりは4ヶ所を回り、その前に西国三十三所の谷汲山華厳寺にも参詣した。そして近江八幡の日牟禮八幡宮で終了。まだレンタカーの返却まで時間があるので、八幡宮のすぐ横から出る八幡山ロープウェーで山上にある八幡山城跡に向かうことにする。




 通常ダイヤだと15分おきだが、ちょうど山上の紅葉が見頃ということで実質ピストン輸送している。早速乗り込む。所要時間は4分だが、その間に近江八幡の城下町の景色、琵琶湖につながる水郷の一帯の景色が広がる。
通常ダイヤだと15分おきだが、ちょうど山上の紅葉が見頃ということで実質ピストン輸送している。早速乗り込む。所要時間は4分だが、その間に近江八幡の城下町の景色、琵琶湖につながる水郷の一帯の景色が広がる。
 八幡山城が築かれたのは豊臣秀吉の天下取りの中である。本能寺の変の後に焼失した安土城に替わり、秀吉の甥の秀次への恩賞として与えた近江の新たな拠点として城を築き、安土から遷した城下町を開いた。ただこの秀次は悲劇の人で、当初は子のない秀吉の後継者と目されていたが、秀頼が産まれたことで次第に疎まれるようになった。最後は謀反の疑いをかけられて高野山に追放され、切腹させられた。
八幡山城が築かれたのは豊臣秀吉の天下取りの中である。本能寺の変の後に焼失した安土城に替わり、秀吉の甥の秀次への恩賞として与えた近江の新たな拠点として城を築き、安土から遷した城下町を開いた。ただこの秀次は悲劇の人で、当初は子のない秀吉の後継者と目されていたが、秀頼が産まれたことで次第に疎まれるようになった。最後は謀反の疑いをかけられて高野山に追放され、切腹させられた。
その後の八幡山城は京極高次が城主となったが没後に廃城となり、江戸時代には天領として近江商人の町として栄えるようになった。



 さてロープウェーを降りると、山上一帯が紅葉の見頃である。ちょうどこの日(12月1日)まで「竹灯りの紅葉路」というイベントが行われており、竹を切って作った灯籠が並ぶ。そうし中、かつての城郭跡をめぐる。
さてロープウェーを降りると、山上一帯が紅葉の見頃である。ちょうどこの日(12月1日)まで「竹灯りの紅葉路」というイベントが行われており、竹を切って作った灯籠が並ぶ。そうし中、かつての城郭跡をめぐる。




 かつての本丸跡には、日蓮宗の門跡寺院「村雲御所 瑞龍寺門跡」が建つ。豊臣秀次の菩提を弔うために京都に開かれた寺院だが、1961年にここに移築されたとある。切腹から400年以上の時を経て名誉が回復されたということかな。この境内からの眺めもなかなかよい。
かつての本丸跡には、日蓮宗の門跡寺院「村雲御所 瑞龍寺門跡」が建つ。豊臣秀次の菩提を弔うために京都に開かれた寺院だが、1961年にここに移築されたとある。切腹から400年以上の時を経て名誉が回復されたということかな。この境内からの眺めもなかなかよい。



 反対側の西の丸跡に向かう。ちょうどこちらは琵琶湖に面した側である。近くは長命寺山、そしてはるか遠くには比叡山の方向も見ることができる。1日の札所めぐりの最後にふさわしい景色である。
反対側の西の丸跡に向かう。ちょうどこちらは琵琶湖に面した側である。近くは長命寺山、そしてはるか遠くには比叡山の方向も見ることができる。1日の札所めぐりの最後にふさわしい景色である。




 ロープウェーで下山し、駐車場までぶらぶら歩く。そして近江八幡駅前のトヨタレンタカーに到着し、レンタカーを返却する。
ロープウェーで下山し、駐車場までぶらぶら歩く。そして近江八幡駅前のトヨタレンタカーに到着し、レンタカーを返却する。
さてこの後だが、近江八幡からJRで京都まで出て新幹線に乗る予定である。それまで時間があり、近江八幡で一献としてから移動しても十分間に合うくらいである。しばらく、駅前のイオンにて時間をつぶす。

 そして開店を待って入ったのが駅前の「らいおん丸」。2023年の大晦日、神仏霊場めぐりで近江八幡に泊まったのだが、その時の一献の店として入ったところである。さまざまな料理あり、雰囲気もよかったのを思い出し、列車までの時間を過ごすことにした。
そして開店を待って入ったのが駅前の「らいおん丸」。2023年の大晦日、神仏霊場めぐりで近江八幡に泊まったのだが、その時の一献の店として入ったところである。さまざまな料理あり、雰囲気もよかったのを思い出し、列車までの時間を過ごすことにした。

 まずはサッポロの赤星で乾杯。「白子祭」ということで白子ポン酢と合わせる。
まずはサッポロの赤星で乾杯。「白子祭」ということで白子ポン酢と合わせる。

 その後は近江鶏のとり皮ポン酢、寒ブリの塩たたきなどいただく。白子もそうだがいずれも濃厚な味わいである。
その後は近江鶏のとり皮ポン酢、寒ブリの塩たたきなどいただく。白子もそうだがいずれも濃厚な味わいである。


 滋賀の地酒も充実しており、松の司、七本槍、喜楽長といった銘柄が並ぶ。またメニューにあったので鮒ずしも注文。
滋賀の地酒も充実しており、松の司、七本槍、喜楽長といった銘柄が並ぶ。またメニューにあったので鮒ずしも注文。

 最後は、その七本槍を使った「サムライハイボール」。滋賀の夜はよいものになった・・。
最後は、その七本槍を使った「サムライハイボール」。滋賀の夜はよいものになった・・。


 近江八幡から新快速で京都に移動し、20時02分発「のぞみ79号」広島行きに乗る。帰りの列車を選ぶうえで、終点広島というのは安心である。
近江八幡から新快速で京都に移動し、20時02分発「のぞみ79号」広島行きに乗る。帰りの列車を選ぶうえで、終点広島というのは安心である。
 そして今回は7号車「Sシート」を選択。料金は上乗せになるが、隣を気にせずゆったりと・・(パソコンは使わないが)。
そして今回は7号車「Sシート」を選択。料金は上乗せになるが、隣を気にせずゆったりと・・(パソコンは使わないが)。
さて今回の札所めぐりで、神仏霊場巡拝の道も残り30ヶ所あまりになった。依然として京都近辺に札所が固まっているが他地区にも点在しており、2025年はどのような形で回ることになるかな・・・。