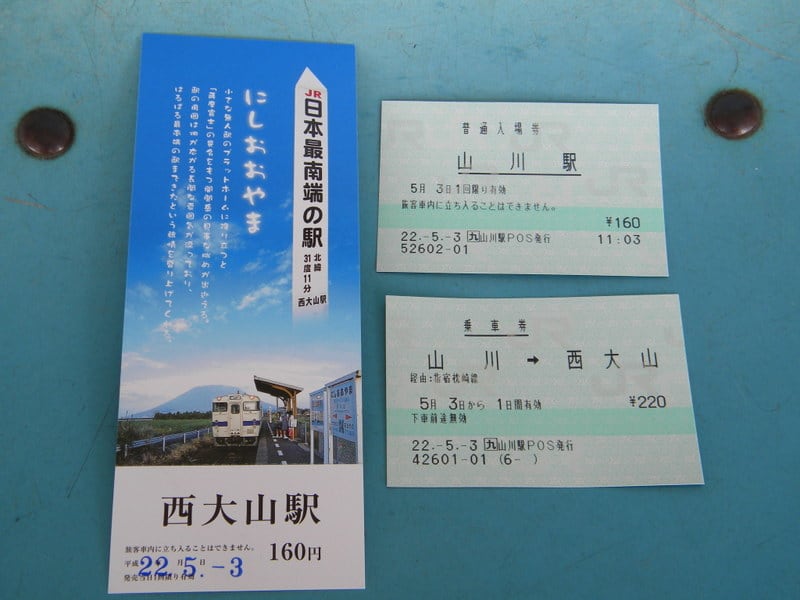小田原散歩の続き。
「小田原おでん」で昼食とした後、これからどのように回るかを検討。小田原文学館は必須としてコースに入っているようだが、後は成り行きである。会主の旅の侍さんいわく、普段の人数の散歩ではコースもきちんと決めた上で回ることになるのだが、今回4人という人数のためコースどりの自由度は高い。
 小田原には「街かど博物館」というスポットが結構ある。小田原の産業や歴史文化をPRするために、街かどの店舗や工場を博物館として公開しているという。文学館までの間にもいくつか点在しているようで、それらを見学しつつ行こうかと思う。まずは「小田原おでん本店」の斜め向かいにある「かまぼこ伝承館」、その次は通りを一つ入った「ひもの工房」に行こうということになる。何かかまぼこをこしらえたり、干物を干したりという体験メニューがあるかもしれない。
小田原には「街かど博物館」というスポットが結構ある。小田原の産業や歴史文化をPRするために、街かどの店舗や工場を博物館として公開しているという。文学館までの間にもいくつか点在しているようで、それらを見学しつつ行こうかと思う。まずは「小田原おでん本店」の斜め向かいにある「かまぼこ伝承館」、その次は通りを一つ入った「ひもの工房」に行こうということになる。何かかまぼこをこしらえたり、干物を干したりという体験メニューがあるかもしれない。
・・・ということで向かったのだが、パッと見たところ普通のかまぼこ屋であり、干物屋でありという感じ。「これで博物館?」「ちょっと、無理があるんじゃないの?」という声が出る。やはりこじつけの面があるのかな。それとも、かまぼことなると商売敵が多いからここだけ「伝承館」を名乗るのに差支えがあるとか。「本家」と「元祖」争いみたいなものか。
 そんな話をする中でやってきたのが「かつおぶし博物館」の「籠常」。先の二つがあったので「ただのかつおぶし屋だろう」というイメージがあったのだが、まず建物がえらい時代がかっている。そして、開け放たれた扉から中をのぞくと、かつおぶしづくりの工程を解説したパネルなどもあり、一応「商店の中で博物館的に何か学べる」ような風情だったので、ちょいとのぞいてみる。
そんな話をする中でやってきたのが「かつおぶし博物館」の「籠常」。先の二つがあったので「ただのかつおぶし屋だろう」というイメージがあったのだが、まず建物がえらい時代がかっている。そして、開け放たれた扉から中をのぞくと、かつおぶしづくりの工程を解説したパネルなどもあり、一応「商店の中で博物館的に何か学べる」ような風情だったので、ちょいとのぞいてみる。
 そこで、店のおばあさんの熱烈な?歓迎を受ける。この建物、小田原でも大きな被害を出した関東大震災の翌年に建てられたものとかで、現在も店の裏がかつおぶしづくりの工場となっている。かつおぶしはうまい具合にかつおの切り身にカビをつけて風味を出すのだが、「このカビをつけていい味になるのには半年はかかるんですよ。半年ですよ。」「かつおぶしの切り身は必ず2つが一体でして、これは夫婦がぴたりと寄り添うところから、今でもかつおぶしが結婚式の引き出物として喜ばれるんですよ・・・今ではそんな人も少なくなりましたが」「かつおぶしというのは栄養価満点で健康食なんですよ。今日はこれをご自分の口で、学んで帰ってください」など、私たちを日本の伝統文化に興味ある集団と見てか、あるいはここをのぞく客が珍しいのか、あれやこれやと話しかけてくれる。
そこで、店のおばあさんの熱烈な?歓迎を受ける。この建物、小田原でも大きな被害を出した関東大震災の翌年に建てられたものとかで、現在も店の裏がかつおぶしづくりの工場となっている。かつおぶしはうまい具合にかつおの切り身にカビをつけて風味を出すのだが、「このカビをつけていい味になるのには半年はかかるんですよ。半年ですよ。」「かつおぶしの切り身は必ず2つが一体でして、これは夫婦がぴたりと寄り添うところから、今でもかつおぶしが結婚式の引き出物として喜ばれるんですよ・・・今ではそんな人も少なくなりましたが」「かつおぶしというのは栄養価満点で健康食なんですよ。今日はこれをご自分の口で、学んで帰ってください」など、私たちを日本の伝統文化に興味ある集団と見てか、あるいはここをのぞく客が珍しいのか、あれやこれやと話しかけてくれる。
せっかくなのでということで、かつおぶしの味見をさせてくれる。かつおぶしと言って思いつくのはパックに入った削り節であるが、かつおの他にそうだがつお、鯖などもそれぞれの魚の風味を出す感じで燻製をつくり、削ったものを出している。それぞれに違った風味を感じる。まさか、小田原でかつおに出会うとは思わなかった。
「小田原の人は口下手で商売が苦手でねえ・・・」というおばあさんの言葉。いや、十分商売してまんがな。結局パックの削り節と、出汁用にカットされたかつおを買い求め、なかなか充実の「博物館」を後にする。帰宅後にこれで出汁をとってみたが、いやこれ、なかなかいけましたぞ。先に食べたおでん屋も、もっとこれくらいかつお風味の味を出してくれてもいいと思うのだが・・・。
この通りは海産物を扱う昔ながらの店も多い。その中で「小田原名物さつま揚げ」という看板も見る。さつま揚げ・・・って。小田原で薩摩を名物にすることもないでしょうに。
また、小田原というところは歴史的な側面と現在の生活が実に密接につながっていると感じさせられるスポット。それが「川崎長太郎の石碑」である。川崎長太郎という人、小田原出身の小説家で、芸術選奨にも選ばれたというくらいの人らしいのだが、その生家か何かの跡地に石碑が建っている。・・・のはいいのだが、その石碑のすぐ横に「ゴミ回収 一般ゴミ毎週○曜日」という看板があり、市が定めるところのゴミ収集場になっている。これには散歩の参加者、特に俳句のサークルも主宰している文学好きのセージさんに至っては「こんな扱いねえよ!可愛そうだよありえねーよ!」とあきれかえるやら半ば憤るやら。これまでの「博物館」のあれこれといい、何とまあ大らかな、細かいことを気にしない街というか・・・。
 さて気を取り直しつつやってきたいのは西海子小路。これまで見てきた古い建物やごちゃごちゃした商店街と比べ、道幅も広くなり、両側の邸宅もゆったりした造りになる。その一角にあるのが小田原文学館。
さて気を取り直しつつやってきたいのは西海子小路。これまで見てきた古い建物やごちゃごちゃした商店街と比べ、道幅も広くなり、両側の邸宅もゆったりした造りになる。その一角にあるのが小田原文学館。
 この文学館、明治時代に警視総監や宮内大臣などを歴任した田中光顕伯爵の別邸として建てられた洋館である。建物自体、大正ロマンを感じさせるものである。この中では小田原出身の文学者(先ほどゴミ置き場に石碑があった川崎長太郎もその一人)のほか、小田原ゆかりの文学者の解説もされている。この小田原、美しい山と海とに囲まれ、天候も温暖ということで文学者の別荘地として賑わったところ。谷崎潤一郎の妻をめぐり、谷崎と佐藤春夫が争った文学者の別荘地サロンでの出来事として現在なら連日ワイドショーのネタになったような「小田原事件」というのもあるとか。
この文学館、明治時代に警視総監や宮内大臣などを歴任した田中光顕伯爵の別邸として建てられた洋館である。建物自体、大正ロマンを感じさせるものである。この中では小田原出身の文学者(先ほどゴミ置き場に石碑があった川崎長太郎もその一人)のほか、小田原ゆかりの文学者の解説もされている。この小田原、美しい山と海とに囲まれ、天候も温暖ということで文学者の別荘地として賑わったところ。谷崎潤一郎の妻をめぐり、谷崎と佐藤春夫が争った文学者の別荘地サロンでの出来事として現在なら連日ワイドショーのネタになったような「小田原事件」というのもあるとか。
 敷地内には尾崎一雄の書斎を移築していたり、8年を小田原で過ごし、現在に伝わる童謡作品の多くをここで手がけた北原白秋の館も持ってきている。セージさんに至っては、「これだけの文学者にゆかりがあるなんて、小田原はすごいですよ」と感心しきり。それだけに、「ゴミ置き場の川崎碑」には別の意味でよけいに「小田原はすごい」と思ったことだろう。
敷地内には尾崎一雄の書斎を移築していたり、8年を小田原で過ごし、現在に伝わる童謡作品の多くをここで手がけた北原白秋の館も持ってきている。セージさんに至っては、「これだけの文学者にゆかりがあるなんて、小田原はすごいですよ」と感心しきり。それだけに、「ゴミ置き場の川崎碑」には別の意味でよけいに「小田原はすごい」と思ったことだろう。
この文学エリアは予想外の発見。そこを後にして、少しずつ中心部に戻る。途中、これは「街かど博物館」ではないのだが、旅の侍さんが興味を示してのぞいてみた洋風雑貨店に立ち寄る。雑貨の数々にも驚くのだが、それらを収めたクローゼットに年季が入っていていい艶を出している。東南アジアでの特別製作というが、長持ちするものであり、今度も女性主人のあれこれ話を聞く。ここでも「小田原の人ってなかなか商売が下手で・・・」ということを聞く。これは本当にそうなのか、あるいは強い謙遜なのか・・・。
小田原というところ、やはり武家の町であり、宿場町なのだろう。そしてその宿場町といっても、昔の東海道ならいざ知らず、現在なら箱根やら湯河原、熱海など近くに温泉街も多くあり、ホテルそのものが数えるしかない(新幹線の停まる駅なのに、大手チェーンのホテルが1軒もないのは意外)。一方で商売のほうはどうだろうか。
 そんなことを思いつつやってきたのは「ういろう博物館」。こちらは小田原城を模した建物で出迎えてくれる。ういろうと言えば名古屋名物というイメージが強いが、実はここ小田原が発祥の地。「外郎」というのも名字である。またういろう博物館の向かいは「メガネスーパー」の本店。こういうのもあるんですな。
そんなことを思いつつやってきたのは「ういろう博物館」。こちらは小田原城を模した建物で出迎えてくれる。ういろうと言えば名古屋名物というイメージが強いが、実はここ小田原が発祥の地。「外郎」というのも名字である。またういろう博物館の向かいは「メガネスーパー」の本店。こういうのもあるんですな。
 そろそろ散歩も終盤ということで、小田原城のお堀端を通り、小田原駅方面に向かう。ここで、その名前が気になる「塩から伝統館」へ。駅前のこととてさまざまな飲食店や魚屋などで賑わう一角。この「街かど博物館」も要は塩辛とかまぼこの店。ここで試食をさせていただき、土産物用として塩辛などを買い求める。
そろそろ散歩も終盤ということで、小田原城のお堀端を通り、小田原駅方面に向かう。ここで、その名前が気になる「塩から伝統館」へ。駅前のこととてさまざまな飲食店や魚屋などで賑わう一角。この「街かど博物館」も要は塩辛とかまぼこの店。ここで試食をさせていただき、土産物用として塩辛などを買い求める。
そして散歩の最後は、北条氏政・氏照兄弟の墓所。小田原攻めで敗れ、結局北条氏を滅ぼすことになったのだが、その墓が駅のほど近くにあるという。ただ、先ほどの「ゴミ置き場の文学碑」もあることだから、ここは何か驚くオチがあるに違いない・・・。
 路地の飲食店に囲まれ、お二人様専用ホテルも見える一角。果たして、その一角に石で仕切られたスペースがある。ここが氏政の墓である。それにしても何とまあ落ち着かないところか。そして敷地の前はここもゴミ置き場・・・。やはり、「敗軍の将」というのは後世における扱いはこうなのだろうか。それとも、これも小田原という街のなせることなのか、そんなことには頓着しないのか・・・??
路地の飲食店に囲まれ、お二人様専用ホテルも見える一角。果たして、その一角に石で仕切られたスペースがある。ここが氏政の墓である。それにしても何とまあ落ち着かないところか。そして敷地の前はここもゴミ置き場・・・。やはり、「敗軍の将」というのは後世における扱いはこうなのだろうか。それとも、これも小田原という街のなせることなのか、そんなことには頓着しないのか・・・??
何ともまあ、ツッコミどころ満載の街の散歩を終え、ここで中締め、お開きとする。ここで小田原を後にするさるのこさんを駅までお見送り。入口には二宮金次郎の銅像・・・の先に「小便小僧」の像。二宮金次郎が一生懸命薪を背負って本を読んでいる横で小便を垂らすのって、これも見ていておちょくられた気分。やはり小田原はすごいや。
 さてこれからがこの会恒例?の二次会。店についてはセージさんがいろいろ調べてくれていたが、結局、店の看板を実際に見て、駅すぐの地下にある「清盛」に陣取る。北条氏ゆかりの城下町で平清盛(でしょうね、店名の由来は)に出会うとは。たいらのきよもり、tiredきよもり、疲れた清盛・・・(byラーメンズ)。
さてこれからがこの会恒例?の二次会。店についてはセージさんがいろいろ調べてくれていたが、結局、店の看板を実際に見て、駅すぐの地下にある「清盛」に陣取る。北条氏ゆかりの城下町で平清盛(でしょうね、店名の由来は)に出会うとは。たいらのきよもり、tiredきよもり、疲れた清盛・・・(byラーメンズ)。
セージさんとは初めて一席お相手つかまつることになったが、いやお酒のほうもいける口で、話も熱く大いに盛り上がる。実に楽しい時間を過ごすことができた。4時間近くいましたかね・・・。店のほうも「昔ながらの、サラリーマンが集う居酒屋」といった風情で、料理もリーズナブル。ここはまた来てもいい店である。
 半日を過ごした小田原。歩いてみて実に奥の深い、いろんな表情を持った街であることを感じられた。中でも庶民の現実味たっぷりのエリアと、文学者がかつて集った閑静なエリア、それらがすぐ隣り合って同居しているのも意外な発見である。関西から神奈川というとどうしても横浜を目指してしまうが、横浜とも違う、鎌倉とも違う、「相模の国」を感じられるスポットとして、通過ばかりではなく立ち寄って時間を過ごすことをオススメしたい。
半日を過ごした小田原。歩いてみて実に奥の深い、いろんな表情を持った街であることを感じられた。中でも庶民の現実味たっぷりのエリアと、文学者がかつて集った閑静なエリア、それらがすぐ隣り合って同居しているのも意外な発見である。関西から神奈川というとどうしても横浜を目指してしまうが、横浜とも違う、鎌倉とも違う、「相模の国」を感じられるスポットとして、通過ばかりではなく立ち寄って時間を過ごすことをオススメしたい。
さて散歩はこれでおしまい。翌日23日は1日かけて関西に戻る。天気予報は鉄板で雨・・・・。(続く)