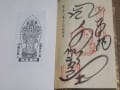円満院門跡に向かう。寺の門はよく見られるような仁王門ではなく屋敷の門である。ここは勅使門と呼ばれている。今は開けっぴろげだが、その昔は勅使が来た時しか開けなかったのだという。門跡寺院というのは僧侶がいて修行の場であるというよりは、皇族や摂関家の言わば口減らしというか、天下りのような形で皇子たちが住職を務めたところであるから、そういう造りになったのかなと思う。


ただ現在は駐車場の入口がメインになっているようで、勅使門をくぐった後に駐車場の敷地に出る。右手にコンクリート造りの建物があり、階段を上がるようになっている。この上が不動堂で、近畿三十六不動としてはここにお参りすることになる。階段下に洗心不動明王像があり、まず口と手を清めた後、不動明王にも水をかける。


階段を上がったところに賽銭箱や燭台など一通りのものがそろっている、その先に畳敷きの外陣があり、座布団がずらりと敷かれている。その先の内陣では係の人が掃除機をかけているところ。何だか行事が行われる前の掃除の時間に割り込んだような気がして、お参りするのに気が引ける感じだが、「騒がせてすんませんねえ。どうぞお参りください」と声をかけてくれる。賽銭箱の前に立ってお勤めとする。ここには箱の中に不動明王の勤行次第と般若心経を印刷した紙が置かれていて、手元に経本がなくてもそれを見て一通りできるようになっている。せっかくなので一枚いただく。
円満院は平安中期、村上天皇の皇子である悟円法親王により創建され、長く三井寺の塔頭寺院としての歴史を持つ。元々は平等院という名前だったが、藤原道長・頼通の時代、宇治に別荘が建てられた時にその名前を譲ったとある。その後、明尊大僧正によって円満院という名前がつけられた。現在は独立して単体の寺院として活動している。




朱印は総合受付でとある。それは奥のほうの建物で、そちらに向かう間に屋敷の正面玄関に出る。この建物は宸殿で、江戸時代に禁裏から移されてきたとされ、現在は国の重要文化財である。こちらは有料で見学ができる。

総合受付があるコンクリートの建物の前には「三井の名水」がある。三井寺の名前の由来ともなった湧水がこちらに流れているそうだ。三井寺では水を汲むことはできないが、円満院で無料でいただくことができる。ご自由にとのことで、ペットボトルの飲みかけの水を空けて、その後で名水をいただく。
施設の受付のようなところで納経帳のバインダーを呈示して朱印の旨を告げる。せっかくなので宸殿などの見学も申し出ると「無料です」と言われる。案内には500円とあったがと確認すると、「朱印の方は無料とさせていただいています」とのこと。実質300円で朱印をいただき見学もできるという意外な展開となった。普通なら、拝観料は拝観料、朱印は朱印とはっきり分かれるところだが。ここで番号札を渡され、朱印の紙は帰りにいただく仕組みである。





宸殿に入る。部屋の一つには赤い毛氈が敷かれ、投扇興ができるようになっている。これは扇子を的に投げて、扇子と的の落ち方によって点数を競うお座敷遊びである。これは参詣者が体験することができる。円満院では日本文化の体験プランとして、この投扇興の他に座禅、茶道といったところを予約制で受け付けている。重要文化財で日本文化に触れるというのは外国人にも好評とのことである。




その円満院は玉座があり、ふすまの障壁画も狩野派によるものを復元している。そして庭園はそれよりも古く、室町時代の相阿弥の作によるとされている。まだ冬のことで花が咲いているわけではないが、季節がよければこの庭園も京都の有名どころに負けず劣らずの景色になるのではないかと想像する。

宸殿と庭園の奥に本堂があり、こちらにも戒壇が設けられ、脇には三井寺を創建した智証大師円珍の像もあるが、ここは窓から覗き込むだけである。実質的な本堂は先ほどの不動堂(三心殿)ということなのだろうか。



順路に従って行くと宝物殿があり、その2階が大津絵美術館となっている。先ほど、大津市役所の前で歩道に設けられた大津絵のレリーフを見たが、ここでは作品がいろいろと並べられている。大津絵という言葉を知ったのもつい最近のことで、その歴史や絵に込められたメッセージについては『大津絵 民衆的諷刺の世界』(クリストフ・マルケ著 角川ソフィア文庫)という一冊を帰りに買い求めたのでこれから読むところ。最近改めて見直されている大津の民衆文化なのかなという程度の理解である。


そのさまざまな作品が展示されている。大津絵は描くテーマがある程度決まっているそうだが、その中で多く描かれているのが「鬼の念仏」である。僧衣を着た赤鬼が念仏を唱えながらお布施を乞うて歩く図柄。これは、「僧侶の姿をしていてもその内面は鬼である(要は偽善者)」という諷刺の意味と、「鬼と言えども念仏を唱えれば極楽往生ができる。だから心をこめて念仏を唱えることが大事である」という念仏のご利益の意味という二つがあるそうだ。外見よりも内面、というところか。


宝物殿の1階には円満院に伝わる絵画や彫刻が展示されている。その中で目を引くのは円山応挙の作品。当時の円満院の祐常門主(住職)が応挙を支援したそうで、写実の画風をこの地で確立したとある。応挙といえば幽霊の絵などで知られるが、そこに円満院が関係しているとは知らなかった。


ここまで一通り見た後で、受付に戻り朱印を受け取る。三井寺の陰に隠れた存在のように見えるが、中身はなかなか濃いものだった。
・・・と書く中で、円満院は順風満帆の歴史スポットである印象を受けていたのだが、実は裏の面もいろいろあるようだ。元が門跡寺院であまり財政のやり繰りを考えることがなかったのかもしれないが。別に円満院に悪意があるわけではないので、ネット記事を参考に、事実とされていることに一応触れておく。
戦後、円満院が所有していた文化財をいろいろ手放すことになった。重要文化財クラスのものもあったが、京都国立博物館などに引き取られた。戦後ともなると皇室との関係は完全に切り離され、寺の経営のためには身の周りの物を売らなければならなかったのだろう。その後、水子供養など経営の手を広げる中で多額の債務を抱え、僧侶への賃金未払いとか、元住職が出家詐欺に加担したとかの金銭トラブルも起こったという。あげくの果てには2009年には重要文化財の宸殿と庭が競売にかけられ、甲賀市の宗教法人が落札した。絵画や彫刻ならまだしも、動かせない重要文化財の建物まで手放したとは。ただ、今でもこうしてお参りができるし、不動明王の護摩供えや年中行事は滞りなく行われている。投扇興などの日本文化体験も、今の経営だからできるのかもしれない。先日、四国八十八所めぐりで札所間のトラブルについて触れたのだが、裏の話が表に出るのではなく、お参りする人がとりあえずその場は安心して手を合わせることができるようにしてくれればよいと思う。
・・・と言いつつも気になるのは、中国の記事で「60億円で日本の古刹が手に入るかも?」などということ。中国マネーが日本の土地をいろいろ買っているという話題は耳にしているが、寺に対してそれはあかんやろう。彼らは不動明王などはどうでもよくて、宸殿と庭園を手に入れればそれでいいのだろうが、ならばなおのことよろしくない。噂が本当ならそこは断固阻止しなければ。



さて、一通り回ったところで昼食とする。訪ねたのは「開運そば」。先ほどの勅使門の脇にあり、元々は門番の小屋だったそうだ。円満院といえば寺と言うより開運そばがあるところとして知られているともされているようで、私が行った時も待ち状態で、しばらく外の床几に腰かける。待つうちにも次々に客がやって来る。

順番になって中に入る。店内には全国各地の寺社の絵馬が飾られている。「開運」の名前によく合っている。

注文したのは店の名前である「開運そば」の定食。出汁は三井の名水を使っており、そばの上には湯葉、青唐、しいたけ、さつまいも、海苔が乗る。これにかやくごはんと、野菜の小鉢がついてくる。よく見れば肉や魚を使っていない(そばの出汁には鰹もあるそうだが)精進料理風である。この辺りのそばと言えば比叡山坂本駅近くの鶴喜そばが有名だが、こちらの開運そばもなかなかのものである。ここでも天台宗の山門派・寺門派のライバル関係がある・・・と言えば言い過ぎだが。
これで昼食としたところで、忘れては行けないのが次の札所へのくじ引きとサイコロ。出たのは・・
1.山科(岩屋寺)
2.嵯峨(大覚寺、仁和寺、蓮華寺)
3.生駒(宝山寺)
4.醍醐(醍醐寺)
5.湖西(葛川明王院)
6.泉佐野(七宝瀧寺)
先ほど触れた門跡寺院もある中で、サイコロが出したのは「6」。これはまたハードなところ・・・「七宝瀧寺」と言われてピンと来ない方もいらっしゃるだろうが、一般的な呼び方で言えば大阪の方なら多くの方が「あそこか」と合点されるスポットである。
この後、隣の三井寺に向かう。こちらは西国1巡目でも来ているので、気楽な感じで回ることに・・・。
 近畿三十六不動めぐりの円満院を後にして、隣にある三井寺の仁王門の前に立つ。ここからは西国三十三所の札所めぐりに切り替わる。三井寺にはこれまで京阪三井寺駅から琵琶湖疎水沿いに歩いて長等神社から西国札所の観音堂に出たが、北側の仁王門から入るのは初めてである。こちらのほうが正門のように見える。
近畿三十六不動めぐりの円満院を後にして、隣にある三井寺の仁王門の前に立つ。ここからは西国三十三所の札所めぐりに切り替わる。三井寺にはこれまで京阪三井寺駅から琵琶湖疎水沿いに歩いて長等神社から西国札所の観音堂に出たが、北側の仁王門から入るのは初めてである。こちらのほうが正門のように見える。 2巡目ということもあり、気楽な感じで境内を回ることにする。まずは仁王門すぐの釈迦堂に向かう。釈迦如来に手を合わせる。前は気づかなかったが、本尊の右手には歴代天皇の位牌が祀られている。その中に昭和天皇のものもあるのは意外だった。こういうことはもちろん今なら宮内庁の許可がなければできないことだろう。歴史ある三井寺だからできたことだろうか。
2巡目ということもあり、気楽な感じで境内を回ることにする。まずは仁王門すぐの釈迦堂に向かう。釈迦如来に手を合わせる。前は気づかなかったが、本尊の右手には歴代天皇の位牌が祀られている。その中に昭和天皇のものもあるのは意外だった。こういうことはもちろん今なら宮内庁の許可がなければできないことだろう。歴史ある三井寺だからできたことだろうか。

 本堂に当たる金堂に着く。方丈の造りは堂々としたもので存在感がある。外陣を一回りする中で、正面におわす本尊の弥勒菩薩は秘仏で手を合わせるだけだが、不動明王や阿弥陀如来、毘沙門天など各時代の仏像が金堂の三辺を護るように飾られている。これらをガラス越しではなく間近に見られるとは、特に仏像好きの方には興味深いものだと思う。
本堂に当たる金堂に着く。方丈の造りは堂々としたもので存在感がある。外陣を一回りする中で、正面におわす本尊の弥勒菩薩は秘仏で手を合わせるだけだが、不動明王や阿弥陀如来、毘沙門天など各時代の仏像が金堂の三辺を護るように飾られている。これらをガラス越しではなく間近に見られるとは、特に仏像好きの方には興味深いものだと思う。

 続いて、近江八景にも歌われた三井の晩鐘や、阿迦井の井戸、さらには同じ鐘でも弁慶が引き摺ったとされる釣り鐘を見る。この辺りは三井寺の中の観光スポットと言ってもいいだろう。
続いて、近江八景にも歌われた三井の晩鐘や、阿迦井の井戸、さらには同じ鐘でも弁慶が引き摺ったとされる釣り鐘を見る。この辺りは三井寺の中の観光スポットと言ってもいいだろう。

 何だか淡々と歩くような感じで昔ながらのたたずまいや(最近の時代物の映画のロケ地に三井寺のこの場所が選ばれたという看板も見るが、それだけのものが残っている証)、緩やかな坂道をたどる。
何だか淡々と歩くような感じで昔ながらのたたずまいや(最近の時代物の映画のロケ地に三井寺のこの場所が選ばれたという看板も見るが、それだけのものが残っている証)、緩やかな坂道をたどる。
 そして最後に観音堂に出る。西国三十三所1300年の幟があちこちではためく。仁王門から一通り歩いてようやく着いた感じはあるが、これが本来なのだろう。西国札所「だけ」を目指していれば、長等神社の石段を上り、観音堂にお参りして、朱印をいただいてそれで終わりである。まあ、そういうお参りをする人も結構いると思うが。
そして最後に観音堂に出る。西国三十三所1300年の幟があちこちではためく。仁王門から一通り歩いてようやく着いた感じはあるが、これが本来なのだろう。西国札所「だけ」を目指していれば、長等神社の石段を上り、観音堂にお参りして、朱印をいただいてそれで終わりである。まあ、そういうお参りをする人も結構いると思うが。
 観音堂に入る。西国の白衣を着た人もいる。私もここで西国先達の輪袈裟を引っ張り出して首にかけ、お勤めの準備をする。ふと目をやると、そこには大津絵の鬼の念仏の額が掲げられていた。昨日今日掲げたものではなく、私がこれまで意識しなかっただけのことだが、寺のお堂にこの図柄を掲げるのはお参りする人たちへの問いかけなのかなと思われた。鬼が僧侶のふりをして回っているだけなのか、鬼だけど信仰によって喜びや幸せを得られるものか。
観音堂に入る。西国の白衣を着た人もいる。私もここで西国先達の輪袈裟を引っ張り出して首にかけ、お勤めの準備をする。ふと目をやると、そこには大津絵の鬼の念仏の額が掲げられていた。昨日今日掲げたものではなく、私がこれまで意識しなかっただけのことだが、寺のお堂にこの図柄を掲げるのはお参りする人たちへの問いかけなのかなと思われた。鬼が僧侶のふりをして回っているだけなのか、鬼だけど信仰によって喜びや幸せを得られるものか。 その答えがいずれともわからないまま、一通りのお勤めを行い、お堂の中の納経所に向かう。例のごとく巻物の先達納経帳を出して朱印をいただいていると、横の列に並んでいた人は「西国のご詠歌の紙と、びわ湖百八観音のバインダーのやつを・・・」と依頼している。びわ湖百八霊場。琵琶湖を囲むように百八の観音霊場があるそうで、エリアが滋賀県限定とはいえ全部回るのは大変そうだ。百八の中には住職や係の人が常駐していないところも多いため、朱印はあらかじめ書き置きを用意しておき、それをバインダーに綴じるのだそうだ。
その答えがいずれともわからないまま、一通りのお勤めを行い、お堂の中の納経所に向かう。例のごとく巻物の先達納経帳を出して朱印をいただいていると、横の列に並んでいた人は「西国のご詠歌の紙と、びわ湖百八観音のバインダーのやつを・・・」と依頼している。びわ湖百八霊場。琵琶湖を囲むように百八の観音霊場があるそうで、エリアが滋賀県限定とはいえ全部回るのは大変そうだ。百八の中には住職や係の人が常駐していないところも多いため、朱印はあらかじめ書き置きを用意しておき、それをバインダーに綴じるのだそうだ。
 観音堂の上の展望台に上がる。少し雲がかかっているが琵琶湖の眺めはよい。滋賀県にもこれからまたいろいろ訪ねることがあるだろう。
観音堂の上の展望台に上がる。少し雲がかかっているが琵琶湖の眺めはよい。滋賀県にもこれからまたいろいろ訪ねることがあるだろう。

 このまま石段を下り、長等神社からアーケードの商店街や旧東海道を歩く。大津の宿場町の風情も所々に残っている。
このまま石段を下り、長等神社からアーケードの商店街や旧東海道を歩く。大津の宿場町の風情も所々に残っている。

 JRの大津駅に到着する。駅のすぐ横にあった平和堂は完全に取り壊されて、高層マンションが建つようだ。また駅も一昨年10月にビエラ大津という商業施設ができている。線路と同じ高さにある簡易宿泊施設や、飲食店も並ぶ。先ほど円満院の開運そばを食べたばかりということもあって食事はしなかったが、新たにできた観光案内所の売店で琵琶湖の幸を土産に買い求める。また時間を合わせて訪ねてみたいものだ。
JRの大津駅に到着する。駅のすぐ横にあった平和堂は完全に取り壊されて、高層マンションが建つようだ。また駅も一昨年10月にビエラ大津という商業施設ができている。線路と同じ高さにある簡易宿泊施設や、飲食店も並ぶ。先ほど円満院の開運そばを食べたばかりということもあって食事はしなかったが、新たにできた観光案内所の売店で琵琶湖の幸を土産に買い求める。また時間を合わせて訪ねてみたいものだ。