奈良県は五條に行ってみようと思う。
・・・この五條、「五条」ではなく「五條」なんですな。昔の都のような一条、二条・・・の五条ではなく、別なところから来ているということで、あくまで「五條」と書かなければならない。奈良県にはあるが、私の住む藤井寺から列車で行こうと思えば、河内長野~橋本と来て和歌山線に乗り継ぐか、あるいは御所、はたまた吉野口から和歌山線に乗ることになる。どのルートを通っても金剛・葛城の山々を避けるコースで、それなりに時間がかかる。鉄道が和歌山線のみということで、かなり長い間、「和歌山県五條市」と勘違いしていたものである。
 五條といえばその南の十津川村とか、もっと先に抜けて熊野本宮、果ては新宮という紀伊半島の真ん中から南に抜けるコースの玄関口として何度か通ったことはあるが、五條そのものを目的としたことはない。そんな中、ふとしたことで「五條に行ってみようか」と思い立って自宅を出発し、気づけば五條のバスセンターも兼ねているイオンの前で傘を差して立っていた。
五條といえばその南の十津川村とか、もっと先に抜けて熊野本宮、果ては新宮という紀伊半島の真ん中から南に抜けるコースの玄関口として何度か通ったことはあるが、五條そのものを目的としたことはない。そんな中、ふとしたことで「五條に行ってみようか」と思い立って自宅を出発し、気づけば五條のバスセンターも兼ねているイオンの前で傘を差して立っていた。
 しばらく歩くと交差点に出る。直進すれば橋本から和歌山へ、左に曲がれば吉野川を渡り、十津川から新宮へ抜ける延々としたルート、右に曲がれば隘路を抜けて千早赤阪村や河内長野に出る要衝。ここから少し入ったところに「五條新町」という、江戸時代から続く街並みが広がる。
しばらく歩くと交差点に出る。直進すれば橋本から和歌山へ、左に曲がれば吉野川を渡り、十津川から新宮へ抜ける延々としたルート、右に曲がれば隘路を抜けて千早赤阪村や河内長野に出る要衝。ここから少し入ったところに「五條新町」という、江戸時代から続く街並みが広がる。

 特に前々からこの日を狙っていたわけではない。どこかに出かけようとしてたまたま思いついたところである。結構降りしきる雨の中、十津川に続く国道から一本路地に入ると、そこはタイムスリップしたかのような落ち着いた街並みである。
特に前々からこの日を狙っていたわけではない。どこかに出かけようとしてたまたま思いついたところである。結構降りしきる雨の中、十津川に続く国道から一本路地に入ると、そこはタイムスリップしたかのような落ち着いた街並みである。
 紀州街道に沿って400年の歴史を持つ五條新町。今でも生活の匂いを漂わせる町家が続く。ふとそこで目にするのは「HANARART2012」という垂れ幕。「ハナラート」というこのイベント、奈良県内の各地の町家を舞台にして現代アートを披露しようというものである。安藤忠雄デザインだか何だか知らないが、ああいうハコモノでやるのではなく、昔ながらの町家を舞台にするというのが面白い。ちょうど先日に六甲の山々を巻き込んだアート展を見たが、それとはまた対照的なところであろう。
紀州街道に沿って400年の歴史を持つ五條新町。今でも生活の匂いを漂わせる町家が続く。ふとそこで目にするのは「HANARART2012」という垂れ幕。「ハナラート」というこのイベント、奈良県内の各地の町家を舞台にして現代アートを披露しようというものである。安藤忠雄デザインだか何だか知らないが、ああいうハコモノでやるのではなく、昔ながらの町家を舞台にするというのが面白い。ちょうど先日に六甲の山々を巻き込んだアート展を見たが、それとはまた対照的なところであろう。
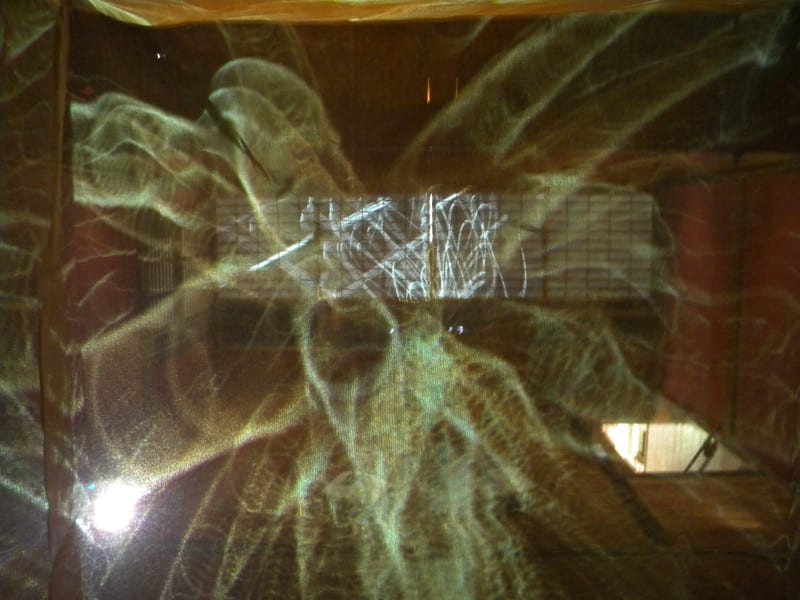 「まちや館」で展示されていたのが光の仕掛けを駆使したアート。畳の部屋にタブレット端末を敷き並べて映像を映し出したり、障子を壁代わりに光のグラフィックを上演したりしている。中には、手を叩いたり、声を出したりというのに反応してグラフィックが動き回るという仕掛けもあったりする。
「まちや館」で展示されていたのが光の仕掛けを駆使したアート。畳の部屋にタブレット端末を敷き並べて映像を映し出したり、障子を壁代わりに光のグラフィックを上演したりしている。中には、手を叩いたり、声を出したりというのに反応してグラフィックが動き回るという仕掛けもあったりする。
 スクリーンが町家の障子だったりするのが面白い。古いものと新しいものが見事に混ざり合っている。
スクリーンが町家の障子だったりするのが面白い。古いものと新しいものが見事に混ざり合っている。
 もう少し歩いたところが「まちなみ伝承館」。ここは普段は公開していないそうだが、この芸術祭に合わせて、屋敷全体を舞台として公開している。数々の木彫りの作品やら、あるいは奥に行けば本格的な油絵もあったりと、なかなか見ごたえがある。こういう構成、安藤忠雄デザインのコンクリートづくめの美術館では決して観られるものではない。町家アート、ええやないですか・・・。
もう少し歩いたところが「まちなみ伝承館」。ここは普段は公開していないそうだが、この芸術祭に合わせて、屋敷全体を舞台として公開している。数々の木彫りの作品やら、あるいは奥に行けば本格的な油絵もあったりと、なかなか見ごたえがある。こういう構成、安藤忠雄デザインのコンクリートづくめの美術館では決して観られるものではない。町家アート、ええやないですか・・・。
 この町家イベントは前半後半分かれて御所、八木、田原本、郡山などで開催されているという。これらを気軽に観て回るのも面白いかと・・・。
この町家イベントは前半後半分かれて御所、八木、田原本、郡山などで開催されているという。これらを気軽に観て回るのも面白いかと・・・。
 番外編として、「まちや館」の向かいではひっそりと、「鉄道ジオラマ」の館があった。この芸術祭の期間に合わせてとのことであるが、かつての建物を利用してのジオラマ展示、ちょうど入ったのが私だけということもあり、小ぶりながら精緻に作られたジオラマのスイッチを入れて電車を走らせてくれる。これらのジオラマ、10万単位を払えばそっくり持ち帰ることができる。たださすがにそうは行かず、それこそ童心に帰ってそのレイアウトを楽しむ。私の部屋にも100円ショップで購入したケースに何両か模型が陳列されているが、やはりこうした「景色と一体となった」演出をしてやりたいなと思う。
番外編として、「まちや館」の向かいではひっそりと、「鉄道ジオラマ」の館があった。この芸術祭の期間に合わせてとのことであるが、かつての建物を利用してのジオラマ展示、ちょうど入ったのが私だけということもあり、小ぶりながら精緻に作られたジオラマのスイッチを入れて電車を走らせてくれる。これらのジオラマ、10万単位を払えばそっくり持ち帰ることができる。たださすがにそうは行かず、それこそ童心に帰ってそのレイアウトを楽しむ。私の部屋にも100円ショップで購入したケースに何両か模型が陳列されているが、やはりこうした「景色と一体となった」演出をしてやりたいなと思う。
そんな模型の世界はさておくとして、実際の鉄道が走る予定として建設されたはいいが、結局何も通らなかったというのがこちら「五新線」の高架橋の跡。
五は五條、新は新宮ということで、紀伊半島を縦断してというのが当初の目的であった。ただそれが財政難やモータリゼーションもあり建設の見通しが立たなくなり、結局は一部区間を路線バスで走らせるのみ、ということになった。まあ、頻繁に来る台風による土砂災害などの影響を考えれば、無理矢理に鉄道を伸ばしたところでしょっちゅう運休し、そのうち廃止になるだろうという意見はごもっともである。
 その五新線が走るはずだった高架橋跡であるが、傍で生活する人にとっては何の役にも立たないものである。高架を利用して洗濯物を干したりというのはあるが、結局どのように役立てようとしているのか、不安である。ただ現在では観光地図に載っていたり、昨年とかはこの高架橋を通るというウォークイベントも行われたという。
その五新線が走るはずだった高架橋跡であるが、傍で生活する人にとっては何の役にも立たないものである。高架を利用して洗濯物を干したりというのはあるが、結局どのように役立てようとしているのか、不安である。ただ現在では観光地図に載っていたり、昨年とかはこの高架橋を通るというウォークイベントも行われたという。
 こういうイベントがあれば地域活性化の面でもプラスになるだろう。奈良にこういう一面があるということで・・・・。
こういうイベントがあれば地域活性化の面でもプラスになるだろう。奈良にこういう一面があるということで・・・・。
 橋下・大阪市長率いる「日本維新の会」がどうなるかという中で、新たに名乗りを挙げたのが石原・東京都知事。石原知事が辞職することで、「たちあがれ日本」に合流し、新党を名乗ることで「第三極」の主導権を握ろうというものである。まあ、「たちあがれ日本」の主義主張は石原知事とマッチするから、この流れ自体は不思議に思うものではなく、「待ち焦がれた人がとうとう来てくれたのね」という感じである。
橋下・大阪市長率いる「日本維新の会」がどうなるかという中で、新たに名乗りを挙げたのが石原・東京都知事。石原知事が辞職することで、「たちあがれ日本」に合流し、新党を名乗ることで「第三極」の主導権を握ろうというものである。まあ、「たちあがれ日本」の主義主張は石原知事とマッチするから、この流れ自体は不思議に思うものではなく、「待ち焦がれた人がとうとう来てくれたのね」という感じである。














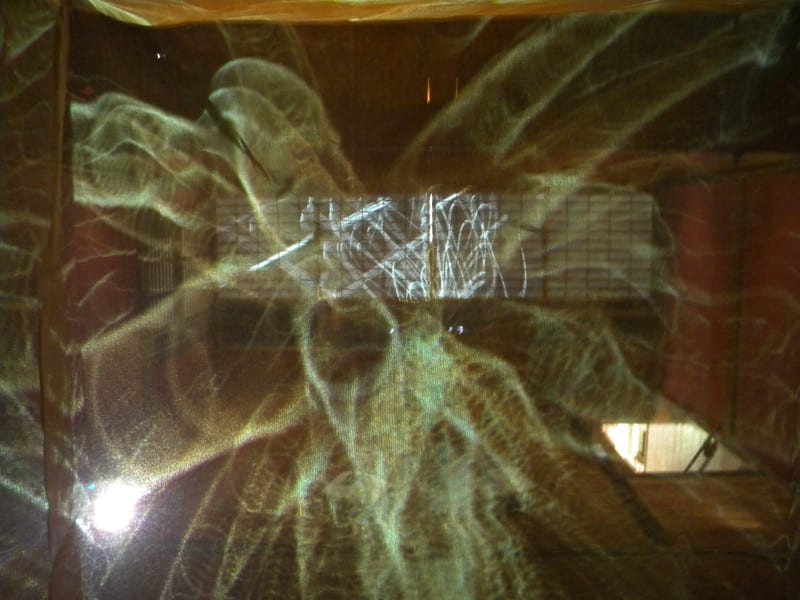




 その五新線が走るはずだった高架橋跡であるが、傍で生活する人にとっては何の役にも立たないものである。高架を利用して洗濯物を干したりというのはあるが、結局どのように役立てようとしているのか、不安である。ただ現在では観光地図に載っていたり、昨年とかはこの高架橋を通るというウォークイベントも行われたという。
その五新線が走るはずだった高架橋跡であるが、傍で生活する人にとっては何の役にも立たないものである。高架を利用して洗濯物を干したりというのはあるが、結局どのように役立てようとしているのか、不安である。ただ現在では観光地図に載っていたり、昨年とかはこの高架橋を通るというウォークイベントも行われたという。















































