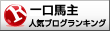早いもので、ついこの前に金杯があったと思ったら、あっという間に1月が終わってしまいましたね。
別に感慨深くなっているわけではないのですが、ふと思い立ったので今月の出資馬成績をまとめてみました。
【日付 レース 出走馬 着順】
1/10 3歳以上500万下(ダ1200m) スプラッシュエンド 11着
1/16 岩清水ステークス(1600万下・芝1600m) ブリッツェン 2着
1/17 紅梅ステークス(3歳オープン・芝1400m) ステラリード 8着
1/24 若竹賞(3歳500万下・芝1800m) バシレウス 2着
1/31 大津特別(1000万下・ダ1800m) プラチナメーン 6着
1月は、北海道でお休み中のアルシラートを除く稼動馬5頭が、それぞれ一度ずつ走ってくれました。
残念ながら勝ち星はありませんでしたが、ブリッツェンとバシレウスの2着もありましたし、毎週楽しめたという意味ではまずまずの2010年スタートだったと思います。
逆に、今のところ2月に出走してきそうなのは、続戦予定のプラチナメーンと“出られれば”の条件付ですがスプラッシュエンドぐらいですから、1月に比べれば少し静かな1ヶ月になりそうです。
個人的には、2010年最初の1勝を期待していたスプラッシュエンドに是非頑張って欲しいと思っています。
別に感慨深くなっているわけではないのですが、ふと思い立ったので今月の出資馬成績をまとめてみました。
【日付 レース 出走馬 着順】
1/10 3歳以上500万下(ダ1200m) スプラッシュエンド 11着
1/16 岩清水ステークス(1600万下・芝1600m) ブリッツェン 2着
1/17 紅梅ステークス(3歳オープン・芝1400m) ステラリード 8着
1/24 若竹賞(3歳500万下・芝1800m) バシレウス 2着
1/31 大津特別(1000万下・ダ1800m) プラチナメーン 6着
1月は、北海道でお休み中のアルシラートを除く稼動馬5頭が、それぞれ一度ずつ走ってくれました。
残念ながら勝ち星はありませんでしたが、ブリッツェンとバシレウスの2着もありましたし、毎週楽しめたという意味ではまずまずの2010年スタートだったと思います。
逆に、今のところ2月に出走してきそうなのは、続戦予定のプラチナメーンと“出られれば”の条件付ですがスプラッシュエンドぐらいですから、1月に比べれば少し静かな1ヶ月になりそうです。
個人的には、2010年最初の1勝を期待していたスプラッシュエンドに是非頑張って欲しいと思っています。
日中歴史共同研究のニュースが流れ、再び両国間の歴史事実認定における深い隔たりが明らかになりました。
南京事件の犠牲者数
中国の主張:20万人以上または30万人以上
日本の主張:20万人を上限として4万人、2万人など諸説あり
日本国内では、“当時の国際常識に鑑みて非難されるべき虐殺事件は無かった”という説もかなり有力ですので、この表現は、日本側が中国の事情に配慮して大幅に譲歩した内容になっていると思います。(本来は、こういう譲歩をせざるを得ない“共同研究”など意味がないのですが・・・。)
私自身もこの問題について調べた時期がありますが、いまだに、『当時(昭和12年末)多くても25万人程度だった南京市の人口が、南京事件終了後(昭和13年)に30万人近くまで増えているのは何故か?』という疑問に対する論理的な説明を聞いたことがありません。
(つまり、犠牲者数に限って言えば、“中国の主張は全く荒唐無稽な絵空事だと思わざるを得ない”のです。)
ただし、日本国内でも、この手の話をした後には必ず(何故かは不明ですが)どうしても南京大虐殺を事実だと認定したい人が出てきて、『数の問題ではない。日本がひどいことをしたのは間違いがないのだから文句を言ってはいけない。』という主張を聞くことになります。
そういう方たちに、『まあ、気持ちは分からないではありませんが、そもそも犠牲者数が荒唐無稽で信憑性がないという話をしているんです。』と言っても聞く耳など持ってくれません。
その時は仕方がないので、『数が問題でないのであれば、犠牲者数3人とか5人とか10人でも良いですね?』と言って話を切り上げるしかなくなります。(そう言うと、さすがに相手もそれ以上議論するのは面倒なようです。)
話が脱線しましたが、こんな荒唐無稽な話を押し付けてくる相手と歴史を共同研究するなんてナンセンスです。
中国社会がもっと成熟して、“世の中にはいろいろな考え方がある”、“相手の主張にも耳を傾けなければ共同研究など成立しない”、ということが普通の感覚になってから、改めて共同研究を始めれば良いと思います。
南京事件の犠牲者数
中国の主張:20万人以上または30万人以上
日本の主張:20万人を上限として4万人、2万人など諸説あり
日本国内では、“当時の国際常識に鑑みて非難されるべき虐殺事件は無かった”という説もかなり有力ですので、この表現は、日本側が中国の事情に配慮して大幅に譲歩した内容になっていると思います。(本来は、こういう譲歩をせざるを得ない“共同研究”など意味がないのですが・・・。)
私自身もこの問題について調べた時期がありますが、いまだに、『当時(昭和12年末)多くても25万人程度だった南京市の人口が、南京事件終了後(昭和13年)に30万人近くまで増えているのは何故か?』という疑問に対する論理的な説明を聞いたことがありません。
(つまり、犠牲者数に限って言えば、“中国の主張は全く荒唐無稽な絵空事だと思わざるを得ない”のです。)
ただし、日本国内でも、この手の話をした後には必ず(何故かは不明ですが)どうしても南京大虐殺を事実だと認定したい人が出てきて、『数の問題ではない。日本がひどいことをしたのは間違いがないのだから文句を言ってはいけない。』という主張を聞くことになります。
そういう方たちに、『まあ、気持ちは分からないではありませんが、そもそも犠牲者数が荒唐無稽で信憑性がないという話をしているんです。』と言っても聞く耳など持ってくれません。
その時は仕方がないので、『数が問題でないのであれば、犠牲者数3人とか5人とか10人でも良いですね?』と言って話を切り上げるしかなくなります。(そう言うと、さすがに相手もそれ以上議論するのは面倒なようです。)
話が脱線しましたが、こんな荒唐無稽な話を押し付けてくる相手と歴史を共同研究するなんてナンセンスです。
中国社会がもっと成熟して、“世の中にはいろいろな考え方がある”、“相手の主張にも耳を傾けなければ共同研究など成立しない”、ということが普通の感覚になってから、改めて共同研究を始めれば良いと思います。
MSN産経ニュース 『【日中歴史研究】舞台裏は…決裂回避で「苦渋の譲歩」』
----ここから引用(抜粋)----------------------
歴史認識問題を政治から切り離し、日中の関係改善に舵を切る-。双方が一致した狙いで始まった歴史共同研究だが、3年余の応酬で日本は中国に振り回され続けた。
平成20年7月末、中国側が突然、会合を要求。中国側は、すべての論文の非公開を要求し、「数枚の報告書で総括したい」などと言い出した。「出す」「出さない」の応酬は約1年間続き、21年8月末、「戦後の現代史の論文の発表を見合わせる」ことで日本側が妥協した。
だが波乱はさらに続いた。双方は9月4日に最終会合を東京で開き、現代史をのぞく論文を9月末に発表することを決めていたが、最終会合も中国側は一方的にキャンセルした。
背景には、日本側の政権交代があるとみられている。「親中的な鳩山政権の出方の見極めたいという事情があったようだ」(協議関係者)。
曲折を経て昨年末の12月24日にようやく開かれた最終会合。このとき日本側は中国側が何を言い出すか分からないと構え、岡田克也外相に「決裂もあり得る」と報告。これ以上の譲歩を求めてきた場合は「決裂も辞さず」の外相の了解まで取り付けて臨んだという。
中国側は「実際に論文を出し合ってみて、改めて論文公表の内政への影響力に中国政府が懸念を強めたようだ」(外交関係筋)とみられている。首脳の判断というより、外交当局の保身との見方が強い。
----ここまで引用(抜粋)----------------------
過去に起きたことは、事実としてはひとつしかありません。
しかしながら、その事実をどう解釈するか、つまり、“歴史をどう認識するか”は、もともと十人十色ほどに違うものだと思います。
ましてや中国は、本来はひとつしかないはずの事実を、自分たちの政治的目的達成のために原形をとどめないほどに歪めてきた国です。そのような国と“歴史の認識”について共同で研究することは、日本にとって何のプラスにもなりません。
(そもそも、研究の入り口である事実の認定が天と地ほどに違うのですから話になりません。)
この日中歴史研究は、平成18年に当時の安倍首相と胡錦濤国家主席の間で合意し、同年始められたものです。
しかしながら、当初期待した“共同研究”の趣旨を全く斟酌せずに、一方的に自分たちの主張を押し付けるだけの中国側の態度を考えれば、これ以上続けることに何の意味もないのは明白です。
(中国の出方は最初から分かっていたので、そもそも始めたこと自体が間違いだったのですが・・・。)
そして、今もっとも留意すべきなのは、過去に例を見ないほどの親中政権である鳩山政権が、中国共産党の意向に沿った形で研究成果の発表を推し進めてしまうことです。
もしもそんなことになったら、日本は今後、中国にとって一方的に都合の良い歴史認識によって、糾弾され続けることになるでしょう。
今からでも遅くありません。そういうことをさせないためにも、この不毛の歴史研究は即刻中止し、研究成果の発表などやめるべきです。
そして、この研究を通じて中国側が何を主張し、どういう態度だったか、その検証と総括をすることが今後の日本のためにはより重要なことだと思います。
----ここから引用(抜粋)----------------------
歴史認識問題を政治から切り離し、日中の関係改善に舵を切る-。双方が一致した狙いで始まった歴史共同研究だが、3年余の応酬で日本は中国に振り回され続けた。
平成20年7月末、中国側が突然、会合を要求。中国側は、すべての論文の非公開を要求し、「数枚の報告書で総括したい」などと言い出した。「出す」「出さない」の応酬は約1年間続き、21年8月末、「戦後の現代史の論文の発表を見合わせる」ことで日本側が妥協した。
だが波乱はさらに続いた。双方は9月4日に最終会合を東京で開き、現代史をのぞく論文を9月末に発表することを決めていたが、最終会合も中国側は一方的にキャンセルした。
背景には、日本側の政権交代があるとみられている。「親中的な鳩山政権の出方の見極めたいという事情があったようだ」(協議関係者)。
曲折を経て昨年末の12月24日にようやく開かれた最終会合。このとき日本側は中国側が何を言い出すか分からないと構え、岡田克也外相に「決裂もあり得る」と報告。これ以上の譲歩を求めてきた場合は「決裂も辞さず」の外相の了解まで取り付けて臨んだという。
中国側は「実際に論文を出し合ってみて、改めて論文公表の内政への影響力に中国政府が懸念を強めたようだ」(外交関係筋)とみられている。首脳の判断というより、外交当局の保身との見方が強い。
----ここまで引用(抜粋)----------------------
過去に起きたことは、事実としてはひとつしかありません。
しかしながら、その事実をどう解釈するか、つまり、“歴史をどう認識するか”は、もともと十人十色ほどに違うものだと思います。
ましてや中国は、本来はひとつしかないはずの事実を、自分たちの政治的目的達成のために原形をとどめないほどに歪めてきた国です。そのような国と“歴史の認識”について共同で研究することは、日本にとって何のプラスにもなりません。
(そもそも、研究の入り口である事実の認定が天と地ほどに違うのですから話になりません。)
この日中歴史研究は、平成18年に当時の安倍首相と胡錦濤国家主席の間で合意し、同年始められたものです。
しかしながら、当初期待した“共同研究”の趣旨を全く斟酌せずに、一方的に自分たちの主張を押し付けるだけの中国側の態度を考えれば、これ以上続けることに何の意味もないのは明白です。
(中国の出方は最初から分かっていたので、そもそも始めたこと自体が間違いだったのですが・・・。)
そして、今もっとも留意すべきなのは、過去に例を見ないほどの親中政権である鳩山政権が、中国共産党の意向に沿った形で研究成果の発表を推し進めてしまうことです。
もしもそんなことになったら、日本は今後、中国にとって一方的に都合の良い歴史認識によって、糾弾され続けることになるでしょう。
今からでも遅くありません。そういうことをさせないためにも、この不毛の歴史研究は即刻中止し、研究成果の発表などやめるべきです。
そして、この研究を通じて中国側が何を主張し、どういう態度だったか、その検証と総括をすることが今後の日本のためにはより重要なことだと思います。