10日は欧州の午後、NYの早朝の時間帯に中国が米国債の購入を減らすか停止するとの報道が流れたことから、米国債に売りが膨らみ長期金利が急騰する中でドルも売られ金市場では買いが膨らんだ。具体的には、定期的に外貨準備の運用方針を見直している中国当局者の話としてブルームバーグが流したもの。一般的には、国家外為管理局(SAFE)の担当者ということになる。
伝えられたところでは、「中国人民銀行に対し財務省証券(米国債)の購入減額ないし停止を勧告」というもので、勧告が採用されたか否かは不明としている。理由としては、「米国債が他の資産と比較で魅力が低くなったことのほか、米国との貿易摩擦が購入を減額したり停止したりする理由になるとしたとされる。
このニュースを受けた市場では米国債は売られ金利は急騰し、米長期金利(10年債金利)は一時昨年3月以来の2.6%に接近し、しばらくこの水準で滞留することになった。一連の流れの中でドル安も進み、ドル指数はこのところの安値水準となっている91ポイント台へ低下。ドル円相場も昨年11月28日以来となる111.27円まで売られた。
金は上昇に転じ、NYの通常取引が始まる前のロンドンの中盤には上げが加速し直近の高値を抜き1328.60ドルまで買われることになった。しかし、上値はここまで。NYの時間帯に入って以降は、ドル安の動きが一服したこともあり、売り買い交錯の中で徐々に売りに押される展開で上げ幅を縮小しながら推移することになった。NY株が取引を開始する時間帯には1320ドル割れまで値を切り下げたものの、前日比プラス圏は維持し、中盤から終盤には買い優勢の流れに転じ安定的に推移し取引を終了した。NYコメックスの通常取引は前日比5.60ドル高の1319.30ドルで終了した。
10日の市場で波乱の主役となった米国債だが、この日はちょうど10年債の入札が午後に予定されており、結果は好調だった。長期金利は2.557%で終了。週明けの8日の2.479%からは大きく上昇している。上げ幅を削ったとはいえ、金価格が1320ドル近辺にとどまっているのは、昨日書いたようにドルの水準が上がっていないことによる。
なお、ブルームバーグの報道からすると、米国債の買いに関して米国との貿易摩擦も判断材料として挙げていることから、多分に政治色の強い発言といえるもの。対中貿易赤字の大きさからトランプ政権がこの先中国にプレッシャーを強める可能性があるが、その際の対抗措置を示したという側面がある。国債の売り、金利急騰も立派なタタカイの武器になるというわけだ。もっとも米国側も、こうした状況は以前から研究しているとされる。実際に米軍の中に、こうした金融的混乱を研究しているグループもいるとみられる。
さらに思うのは、マーケットがことのほか神経質になったのは、国債の大口の買い手としてのFRBの姿は今はなく、むしろ実質的に“売りに回っている(資金回収)”という不都合な真実を改めて意識させられたことだろう。株高モメンタムに酔って忘れそうだが、中銀は舞台裏から目立たぬようにそっと退出しているところ。「潮が引いたときに、誰が裸で泳いでいるかがわかる」、というのはコーラとアイスクリーム好きの“オマハの賢人”の言葉。



















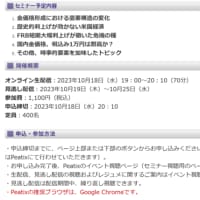






財政は赤字、貿易収支も赤字なんですよね。たしか…