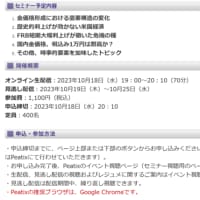先週は四半期末の9月30日にNY金は34.10ドル高で節目の1750ドルを上回って引けたことが目に付いたが、米長期金利(10年債利回り)が低下し、ドルインデックスもそれにつられて低下する中で水準を切り上げたものだった。ダウやS&P500種の下げも大きい中でのことだった。
この上昇に関連した話題から始めるなら、週末10月1日の引け後に米商品先物取引委員会(CFTC)が公表した9月28日時点まで1週間のNY金先物市場における投資主体別の持ち高のデータが示唆的だった。
ファンドはその1週間で、重量換算で50トン(オプション取引除く)と大きく売り建て(ショート)を増やしていたことが判明。前週も30トン増やしていたことから2週間で計80トンの増加になる。一方、買い建て(ロング)は2週間の合計で40トン強こちらは減っていた。その結果、「買い越し量」つまり「ネットロング」ということだが、9月28日までの2週間で122トンの減少となった。1800ドル前後から一時1720ドル台までの値下がり局面でロングの手仕舞い売りと新規のショートの増加が見られていたわけで、フレッシュ・ショートが手仕舞い売りの2倍の規模となっていたことを表している。この間にFOMCが開催され、年内のテーパリング着手は(織り込み済みとはいえ)確認され、ドットチャート(メンバー経済予測の分布図)により22年末までには利上げが見込まれていることが判明したことを受けた動きということになる。
何を言いたいかというと、まず、一連の経過から見て、前週9月30日の34.10ドル高は、ショートの買戻しによる上昇つまりショートカバー主体だったのではということ。それが四半期末であったことから、リバランシング(保有比率の見直し)に伴ったポジション調整なのか、単なる見込み違いの踏み上げなのかということ。後者であれば1700ドル割れを見込んだものの、その近辺での買い意欲の強さに方針変更といったところか。ならば、目先筋の動きということになる。いずれにしても、現状では上値は限定的ということになる。
今週は8日の雇用統計発表まで、注目指標が続くイベント週ということになる。
先週の動きから目に付いたのは、長期金利が1.5%台半ばまで行ったものの、その上が重かった。つまりFRBはじめBOE(イングランド銀行)など、欧米の中央銀行がタカ派姿勢を強めたことを受け、10年債は売られ利回りは急伸したものの、投資家はその下げ局面で押し目買いを入れていたということで、実際にダウジョーンズなどではそうした指摘がみられた。下値での米債の買い意欲の強さが長期金利の上昇を抑え、同時にドルの上値を抑えたことになります。今週発表のデータ如何で、レンジ内に留まるのか、レンジブレイクになるのか。当初の見通しから想定外になりつつあるものに、サプライチェーン問題つまり供給障害の長期化がある。それがインフレ押し上げ要因として、時間の経過とともに意識されることになりそうだ。もうひとつ、中国恒大に関連するチャイナリスクが側面の無視できない材料となるのか否か。
この上昇に関連した話題から始めるなら、週末10月1日の引け後に米商品先物取引委員会(CFTC)が公表した9月28日時点まで1週間のNY金先物市場における投資主体別の持ち高のデータが示唆的だった。
ファンドはその1週間で、重量換算で50トン(オプション取引除く)と大きく売り建て(ショート)を増やしていたことが判明。前週も30トン増やしていたことから2週間で計80トンの増加になる。一方、買い建て(ロング)は2週間の合計で40トン強こちらは減っていた。その結果、「買い越し量」つまり「ネットロング」ということだが、9月28日までの2週間で122トンの減少となった。1800ドル前後から一時1720ドル台までの値下がり局面でロングの手仕舞い売りと新規のショートの増加が見られていたわけで、フレッシュ・ショートが手仕舞い売りの2倍の規模となっていたことを表している。この間にFOMCが開催され、年内のテーパリング着手は(織り込み済みとはいえ)確認され、ドットチャート(メンバー経済予測の分布図)により22年末までには利上げが見込まれていることが判明したことを受けた動きということになる。
何を言いたいかというと、まず、一連の経過から見て、前週9月30日の34.10ドル高は、ショートの買戻しによる上昇つまりショートカバー主体だったのではということ。それが四半期末であったことから、リバランシング(保有比率の見直し)に伴ったポジション調整なのか、単なる見込み違いの踏み上げなのかということ。後者であれば1700ドル割れを見込んだものの、その近辺での買い意欲の強さに方針変更といったところか。ならば、目先筋の動きということになる。いずれにしても、現状では上値は限定的ということになる。
今週は8日の雇用統計発表まで、注目指標が続くイベント週ということになる。
先週の動きから目に付いたのは、長期金利が1.5%台半ばまで行ったものの、その上が重かった。つまりFRBはじめBOE(イングランド銀行)など、欧米の中央銀行がタカ派姿勢を強めたことを受け、10年債は売られ利回りは急伸したものの、投資家はその下げ局面で押し目買いを入れていたということで、実際にダウジョーンズなどではそうした指摘がみられた。下値での米債の買い意欲の強さが長期金利の上昇を抑え、同時にドルの上値を抑えたことになります。今週発表のデータ如何で、レンジ内に留まるのか、レンジブレイクになるのか。当初の見通しから想定外になりつつあるものに、サプライチェーン問題つまり供給障害の長期化がある。それがインフレ押し上げ要因として、時間の経過とともに意識されることになりそうだ。もうひとつ、中国恒大に関連するチャイナリスクが側面の無視できない材料となるのか否か。