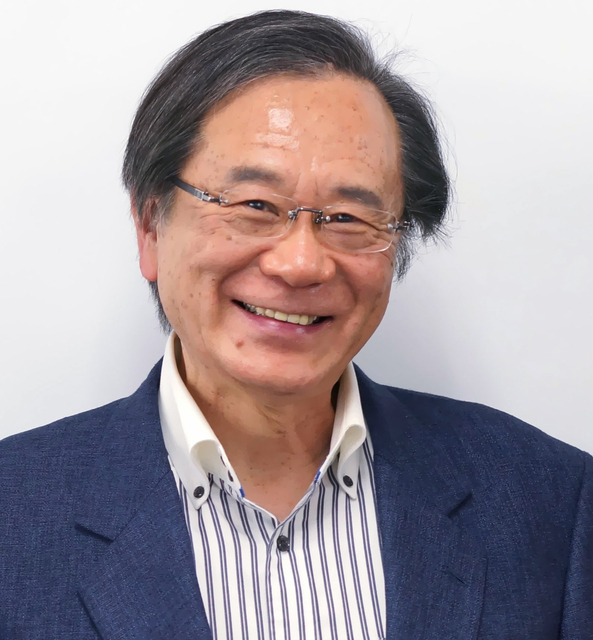以下は、「公共的良識人」紙12月号掲載予定の書評(4600字)です。公共哲学を、単なる「公共学」という社会学ではなく、哲学(恋知)にまで鍛えるために、「問題提起としての書評」を書きました。シリーズ「公共哲学」(東大出版会)の編者ー
金泰昌(キムテチャン)さんからの依頼によるものです。日本社会に最も欠けている「差異」の尊重に基づく忌憚のない「対話」、そこからしかほんものの思想は生まれないと確信するがゆえの生産的な批判です。
==問題提起としての書評==
「公共哲学とはなんだろう」桂木隆一著(
けいそう書房・2005年9月刊)
著者の桂木隆夫さんが「公共哲学とはなんだろう?」と自問自答することで生み出された本書は、平易で丁寧な叙述を特徴とします。
法哲学や公共哲学を論じるに必要なさまざまな思潮が取り上げられていますが、哲学的にはヒュームを中心とするイギリス経験論を基盤にしていることは一読すぐに分かります。大陸の合理論―ルソーやカントにも言及され、現代言語論の成果も背後には見えますが、それもまた経験論の視点から解釈されたものです。そこに本書の魅力もまた若干の物足りなさもある、と私には思えます。
私は、著者と同世代(私が一才年少)ですが、著者とは全く異なる人生を歩んできました。「私塾の精神」による教育を仕事とし、現実の只中で哲学する者としての生を貫いてきた私と、大学の中で法哲学や公共哲学を教授してきた桂木さんとは、好対照です。
さて本題ですが、桂木さんの結論は、おおむね妥当だと思われる部分が多いのですが、残念なことに、その思想の提示が弱々しく魅力的とは言い難いのです。それは何故なのか?実はそこに、一般の「言語的整理」の次元を超えた問題が潜んでいるのではないか、と私は見ます。したがってこの書評は、そこに照準を合わせて一つの「問題提起」を行おうとするものです。著者も言うように、「公共」の精神には、ぶつかり合うことへの信頼が含まれているはずだからです。以下に、失礼を承知で出来るだけ明瞭に私の考えを書いて見ます。桂木さんからの応答を期待しつつ。
まず、最初に取り上げられているハーバマスの思想の成果と問題点についてですが、ハーバマスの公共哲学という社会理論は、その根を言語論に持っているのですから、そこに着眼しなくてはなりません。ハーバマスの提唱する「超越論的言用論」は、イギリスで展開されてきた言語分析哲学をドイツの超越論的哲学の伝統の中に生かす試みと言ってもよいでしょう。そこでは「理想的発話状況」が理念として設定されていますが、この理念は、もちろん現実的・経験的次元での話ではなく、超越論的な次元での想定に過ぎません。したがって彼の思想を桂木さんのように「あまりに理想主義的だ」とか「普遍主義的だ」と言っても批判にはならないでしょう。
私は、彼らの問題点は、言語を全て「議論・討論」というレベルで捉えてしまう平面的な理論構成(ハーバマスは、コッミュニケーションとしての言語行為と討論としての言語行為の二つを並列して提示、説明するのみ)にあると見ます。同一の言語でもその機能のさせ方に着目すれば、日常言語と理論言語(または詩と物語の言葉)とは階層を異にしていることが分かります。次元が違うのですが、その点に無自覚な言語論は、言語を同一平面で捉えるために、立体的な人間の生における言語使用を、二次元化してしまうのです。言語の階層の違いを意識せずに、「発話場」の相違に無頓着になれば「言語至上主義」に陥ります。言語とは、ある特定の発話場の中ではじめてその「適否」と次に「意味」が確定するものであることが無視されると、言語の意味が浮遊してしまいます。ハーバマスは、言語の立体視ができずに「言語至上主義」に陥ったとみるべきでしょう。
私の見るところ、どうしても言語、とりわけ活字のもつ世界は、立体としての現実を平面化して捉えるために、一見明瞭になるのですが、「現実」とはズレてしまいます。実感、イメージ、直観=体験として掴んでいる全体的な見方からは離れていきます。
理念型の言説はその問題が見よい、というより本来は、意識的に理念次元を想定することでそれを超えようという工夫なので、それを経験論的次元に立って、「間違えだ」と指摘しても意味がないわけです。むしろ、理論的整理として当然のことを語っても、現実の変革においてそれが強い意味や力を持たないのが「経験論的」な思考―言説の弱点だと言えましょう。出方は逆ですが、やはり同じく言語使用の次元の相違に無自覚で、立体視ができない問題なのだと言えます。
また、桂木さんは、ルソーやカントの「理念型」の思想も批判的に紹介していますが、その捉え方は、「経験」主義的-平面的です。プラトンの「国家」に倣いわざと現実にはあり得ない紙の上の理念を提示したルソーの思想―強固な教会・王による支配を脱して、あらたな「市民」社会を生むための激烈な文明批評と新社会創造のための苦難の作業は、経験的現実を超えた「理念」の構築を不可欠なものとして要請するのですが、そこで理念として提示された哲学を、著者のように「ルソーの一般意志は、愛国心の純粋性を強調することによって偏狭なナショナリズムを生み出すことになりました。」と言うのは、次元の相違に無自覚な見解でしかないでしょう。また、その後に「カントの人権の理念は、そのあまりの理想主義によって、いわゆる啓蒙的専制主義を招くことになりました。」という言説が続きますが、これは、共に「理念的次元」の話を「経験的・現実的次元」に引き下ろしてしまうために起こる混乱ではないでしょうか。立体交差なのに、平面として捉えて「危険だ」と言っているようなもの、私にはそう思われます。
次に関連することですが、著者は、前記の経験論的な見方から、重要な発想転換を提示します。それは、従来の「正しい」法や社会という見方を捨て、替わりに「利益」をキーワードにすべきという主張です。原理的にはありえない「正しい」社会像の追求をやめようと言うのは当然で、私も賛同します。しかし、その代わりのキーワードとして「利益」を持ち出してもダメです。「利益」の追求はよいことですが、「正しい」の代わりにはなりません。観念動物である我々人間は、「利益」に代表される現実次元の価値だけでは生きられません。今まで人間を支えてきた理念的・ロマン的次元での価値=「正しい」に変わる価値にはなり得ないのです。私は、「正しい」社会ではなく、より「魅力的」な社会とは?を追求すべきだと思います。知識・履歴・財産の所有ではなく、存在そのものの魅力を!というのが私の哲学(恋知)の理論と実践ですが、人間の生とその社会のキーワードは「魅力」でしょう。魅力価値という「主観性」の追求は、主観性を深め広げることで普遍的な了解を生み出そうとする本来の哲学(恋知)の営みにピタリと重なる概念です。豊かで深い魅力を生み育てる思索と行為を目掛けたいもの。
次に、6章の「民主主義」ですが、この章が最大の問題です。「エリート」と「大衆の中のエリート」と「一般大衆」という三区分に基づく結語―「エリートの育成と知的大衆の熟議の活性化が代表民主制のあるべき姿である」。これは、とうてい受け入れがたい結語です。広く社会全体の問題に対しては、専門家としての「エリート」など存在しようがないのです。法律の専門家や統計経済学の専門家や学際的な社会学の学者ならいますが、社会・政治問題を解決する専門家!?とは言語矛盾でしかありません。全体知と専門知の相違については10月号の本紙巻頭に書いた通りです。ご参照下さい。
絶対者やエリートがいない社会制度である「民主制政治」を機能させるには、幼いころからの順を踏んだ教育が必須です。もしも、ただ親に従順に「受験塾」に通って東大法学部に入った受験秀才の青年が「エリート」の卵と思うのならば、笑止でしかありません。「知」とは何か?の基本をとらえ損なっているだけの話ですから。
民主制社会においては何よりも大切な能力=「自治」を子どもたちが身につけるためには、自分の頭で考え、議論し、決定する能力を育成する大胆な教育改革が必要です。偏狭な国家主義のエリート教育ではなく、精神的自立を生む市民教育が絶対的な要件です。もう一度言いましょう。全体的エリートなど存在しないのが民主制社会なのですから、自治への関心と能力を育て、それを高く評価する教育制度をつくること、それがキーポイントになるのです。したがって官僚を含む公務員の仕事とは、「一般的なよさ」を考え、実行することであり、それ以上でも以下でもありません。彼らは、主権者である市民が税金で雇っているサービスマンなのですから。
もう紙面がつきますので、手短に書きますが、最後の9章―「公共精神」には、傾聴すべき考えが幾つも出てきますが、日本的な心性―「多神教」の積極的評価はよいとしても、実はそれは人類文化としては「ふつう」のことであり、
むしろ「一神教」の方が特殊な想念だということを忘れてはならないと思います。
西洋の強い文化・文明を生んだ一神教に憧れ、近代天皇制=天皇教という「擬似一神教」をつくり出した明治政府。そのイデオロギーによる洗脳教育を行うことで生み出された近代日本社会の現実を真正面から見据えなければ、わが国における「公共性」は語れないと思いますが、残念なことに、本書はその点の掘り下げが極めて不十分です。
強権と文字言語による支配が生み出した「文明社会」の問題点をていねいに解決していくためには、一人ひとりの実存から出発する深く哲学する「公共思想」が求められます。言い換えれば、平面の緻密化としての専門知に支えられたから社会から、
立体的な全体知(民知―恋知)に支えら、ダイナミックな人間力によってつくられる社会への転換です。「公共」という思想とは、実存の力を解放することで、開かれた魅力ある社会を生み出すもの、私はそう考えています。
あえて、問題点を列挙しましたが、誠実で丁寧な叙述の本書からは、学ぶべきものが多いと思います。私の思想との対比という変わった書評になりましたが、お許し下さい。
最後におまけ。私もヒュームを高く評価しています。「経験論」を超えていると思うからです。
武田康弘