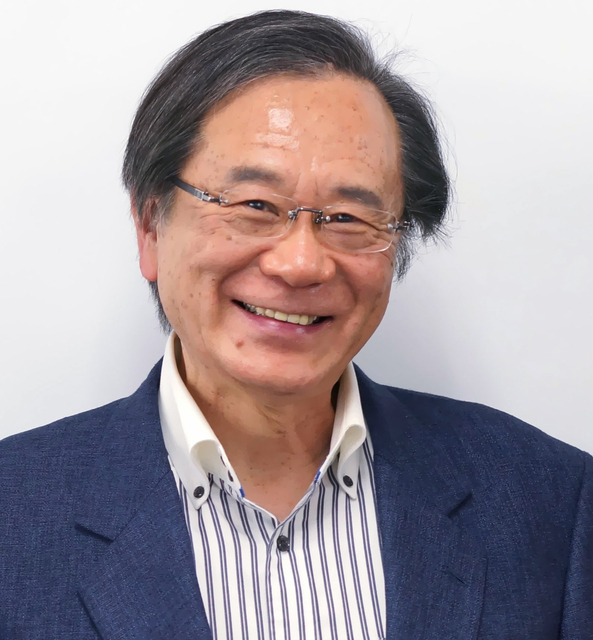「恋知」 第二章 恋知とは何か
(5) まとめ
第二章「恋知とはなにか」を終えるにあたり、どうしても知っておきたい幾つかの事実とそれが意味するもの、そこから得られる思想について書きます。
ソクラテスが死刑の判決を受け毒杯を飲んだ時、恐ろしいほどのショックを受けた弟子のプラトンは、書き言葉を残さなかったソクラテスの言動=思想を残すために、発言の背景と流れがわかるように「劇作」として対話編を書き始めますが、それと同時に私塾の延長としての学園『アカデメイア』をつくりました。エロースを主祭神とする自由で知的香気あふれるこの「友人たちの学校」(敬語ではなく友達同士のような会話ことばの授業)は、次第に発展し、史上最も有名な学園となりましたが、後に現れたキリスト教との対立によりローマ時代に禁止・廃校となります-「以後、何人も恋知(哲学)を教えてはならぬ」

(現在のギリシャ大学正門、左座像はソクラテスで右がプラトン、中野牧人君撮影)
自分自身の頭で考えようとするギリシャ出自の理性的態度は、ユダヤ出自の絶対神を信じるキリスト教とは水と油であったため、恋知(哲学)者とキリスト教徒は対立し、紀元前387年から900年間以上続いた『アカデメイア』は、東ローマ帝国皇帝のユスティニアス1世の命令により529年にその幕を閉じたのです。
ヨーロッパでは、「12世紀にはじまる翻訳の世紀」(アラビア語またはギリシャ語からヨーロッパの言語であるラテン語に翻訳する作業で、16世紀にはじまるルネサンスへと続く)において、古代ギリシャ出自の恋知は、キリスト教に適合するように根本的に変えられていきます。このキリスト教化された哲学は「スコラ哲学」(ラテン語のスコラとはschool=学校のこと)と呼ばれますが、この「キリスト教神学による恋知の換骨奪胎」は、古くは、キリスト教がローマの国教とされた313年のナント勅令の頃からはじまっていました。
(※ なお、ヨーロッパの翻訳の世紀の前は、7~8世紀にはじまるギリシャ語からアラビア語へのイスラムの翻訳の時代があり、ギリシャの学問は、最初はアラビア語に翻訳され、インド経由のゼロの発明による十進数や化学や医学や天文学などがイスラム文化として花開き、それが、12世紀頃からラテン語に翻訳されてヨーロッパ世界に伝えられたのです。)
こういう事情に無頓着な思想関連の学者は、「ギリシャ出自の恋知」と「スコラ哲学とその改革である近代ヨーロッパ哲学」を似たようなものとして扱う愚を平気で犯しますので要注意です。なお、学問史の分野では、村上陽一郎さんの研究・著作が優れていますので、ご参照ください。
わたしたちがよく耳にする哲学者といえば、近代哲学の祖と言われるデカルトであり、ドイツ哲学のビッグネーム、カントやヘーゲルですが、彼らはみなクリスチャンでしたから、ギリシャ出自の恋知と、世界を創ったキリスト教の神への信仰という相容れない思想を統合するために、大変な力業を用いることになりました。ほんらいは出来ない統一を図ろうとしたために、極めて難解な論理を必要とし、それが今日まで恋知(哲学)が具体的現実の中で働く有用な方法にまで進めず、「哲学書の読解」という狭い世界に留め置かれてしまう原因となっています。
もちろん、近代哲学は優れた思想をつくり、人類的な普遍性のあるアイデアに溢れていますし、じっくり読むことで思考の訓練にもなります。ただし、先にも述べました通り、哲学書の読解ばかりをしていると、自分の頭では考えないで、哲学書とその歴史世界を知ることに今を超える価値を感じてしまうという逆立ちをもたらしますので、要注意です。メデューサのごとく、文字による哲学体系が今を生きる「私」の存在=イキイキとした生を石化させてしまいます。言語=理念世界への集中・飛翔と、五感・心身全体で生きる現実生活とはバランスが取れないと人生がスポイルされてしまいますし、西ヨーロッパ哲学がキリスト教化された思想であることを忘れて読んでいると、知らぬ間に「神学的精神」に染まってしまいますので、危険です。神学的思考とは、裸の人間性を肯定し、心身全体で感じ知り、豊かに生きるという発想とは逆に、言葉や特定の観念・理論に縛られて自他を固い檻にいれるような思考と生き方のことです。理論=言語中心主義の強張った貧しい発想は、現実の生からエロースを奪います。 メデューサ(ギリシャ神話)は、見る者を石にしてしまう女神で、ペルセウスによって退治された(彫刻はルネサンス期の奇異な天才ベンベヌート・チェルリーニによる)。
メデューサ(ギリシャ神話)は、見る者を石にしてしまう女神で、ペルセウスによって退治された(彫刻はルネサンス期の奇異な天才ベンベヌート・チェルリーニによる)。
これからの哲学は、キリスト教化されたスコラ哲学とその改革である近代哲学の言語ゲームから、初心の恋知の営みへと変わらなければならないはずです。神学的=権威的発想とは無縁となり、自分の頭で考え・意味をつかむという生き方ですが、ではそのためにはどうしたらよいか。先に「哲学は、具体的現実の中で働く有用な方法にまで進めず」と記しましたが、「キリスト教などの一神教世界や特定の哲学体系、また日本の天皇史観(日本主義)などのイデオロギー」と折り合いをつけようという暗黙の意識・底意から自由になれば、思考は明晰化されスッキリと進みます。宗教や主義や思想の体系から解放されないと、イキイキ伸び伸び、自由で豊かな思考は始まらないのです。「女神メデューサ」を退治しないといけませんね。
では、スッキリと思考を進めるには何が必要かといえば、こどものころからの毎日の学習仕方です。
算数の学習を例にとれば、自分の頭を悩ませて解くのではなく、公式を暗記し当てはめて解答するというのは「外」からの方法で、「内」からの意味了解が得られません。また、音読の場合で言えば、アナウンサーのようにスラスラ読もうとするのは「外」を意識した読みでダメです。つっかえてもよいので、意味を捉えながら、情景を思い浮かべながら、読みます。教科の学習の具体的な方法について書き出すと際限がないので止めますが、ポイントは、自らの具体的経験に照らしながら、内からの了解・納得・意味把握を目がけるところにあります。そのような態度=頭の使い方を習慣として身につけることが何より大切です。暗記と公式、情報処理のスピードを競う「外」的な訓練を中心に生きると、内的な意味充実のない紋切型の「優秀者」にしかなれません。
 (集中して自らの力で数学を解く山田萌生君)
(集中して自らの力で数学を解く山田萌生君)
身体の動かし方もNHKの「みんなの体操」のように、外側の筋肉を使ったスタイル優先の方法はよくありません。脱力して腰からのモーメントで腕や足を動かすことで内側の筋肉を使えば、中からほぐれますし、体幹が強くなります。
心の用い方も同じで、「外」を気にして形優先では、中身の豊かな交流は出来ませんので、自他に悦びはやってきません。心の「内」から立ち昇る想い・考えに素直になると、世界は豊かに大きく広がります。
キーワードは「内」です。頭も体も心も、内からを心がけると芯の強さが得られます。
「外」を気にし、見栄えを優先し、外面的に生きるのは、日本の集団同調の世界ですが、それは、同時に神学的な絶対を求める生き方でもあるのです。前にも書きましたが、みなが言うからという「一般的な正しさ」を求めるという発想が、何かの理由でヒステリー化すると「絶対的な正しさ」を求める心に変わります。絶対的真理がないと生きられないというのは精神疾患ですが、心身全体で愛されたことがなく、疎外感・不全感が強い人は、多数派に同調するか、絶対的真理を求めて従うか、ということになりがちです。両者は一つメダルの表裏に過ぎません。
第三の生き方=「普遍的なよさ」を求めるのは、「私」からはじまる内発的な生を交感・交歓・交換しながら公共性をつくり出そうとする営みによりますが、そのためには、集団同調による「無思想」と、神学的精神による「絶対」を共に越えなければなりません。
哲学無しでも、神学や主義を隠し持つ哲学でもなく、裸の個人として「私」の存在を肯定し合うことで自他を活かし合い、愛情と理性に基づく人間性豊かな生を可能とする恋知の営みは、考え、試し、確かめ、対話しながらよりよい生き方を模索していくのです。権威者や権力者に従うのではなく、他者や周囲の空気に合わせるのでもなく、「私」の内なる良心の声=≪【善美への憧れ】という不動の座標軸≫につく生き方です。
強い一神教と集団同調を共に越えた「普遍性をもつ個性豊かな生き方」、それが、≪善美への憧れを不動の座標軸とする恋知の生≫です。
ここで少し知の歴史(学問史)の話をします。
紀元前6世紀、タレスに始まる古代ギリシャに起こった(現代のトルコのミレトス)「自然哲学」(自然の素材や動因とは何かを探る)は、200年ほど後、ソクラテスと弟子のプラトンによる発想の大転回で、「恋知」(善美のイデアに憧れ、人生を吟味する生き方)へと変わり、それはさまざまな面白い思想=実践を生みました。
ところが、ソクラテスにもプラトンにも教えを受けたアリストテレスは、恋知・哲学の核心であるイデア論を否定し、再び「自然哲学」を中心とする思想に戻ってしまいます。倫理学も自然哲学から導かれるものとなります。
彼の『自然学』(正式には『自然学講義』)は、自然研究の原理論ですが、『形而上学』第一巻は、『自然学』において定義された概念・思想を前提にしていますので、『自然学』は、アリストテレス哲学全体の原理を提示したもの、と言われます。
そこには、有名な「四種類の原因」が提示されています。生成と消滅、自然におけるすべての変化の「原因」は4つあり、それは、「質量・素材因」と「形相ないし範型」と「始動因」と「目的因」だとされます。いま詳しい説明は省きますが、問題は、最後の「目的因」です。当然、人間の製作物なら目的はありますが、自然(の変化)に目的があるとは?彼は、自然の研究者は、四原因をすべて知らなければならないと言い、雨が降るのも偶然ではなく、穀物を成長させるという目的がある、と言います。
 (「学問の祖」と言われるアリストテレスは、恋知の核であるイデア論を否定したため、哲学の神学化への道を開くこととなった。)
(「学問の祖」と言われるアリストテレスは、恋知の核であるイデア論を否定したため、哲学の神学化への道を開くこととなった。)
この「自然によって存在し生成するものの中には目的が内在する」という主張は、キリスト教が、水と油のギリシャ哲学を換骨奪胎していく原因となった、とわたしは見ています。神=創造神が人間を含む全自然をつくったとする一神教であるキリスト教(前身のユダヤ教・旧約聖書に始まる)にとって、人間と自然の一切を説明する「神学≒学問」をつくることは必須でしたが、そのためには、キリスト教思想とは全く異なるギリシャ哲学(世界最高峰の知)を使うほかありませんでした。ソクラテス・プラトンの「善美への希求という座標軸」(それがイデア論の核心)をもつ恋知においては、自然研究(研究者の知的好奇心による)と、人間の生き方(万人にとって必要な探求・吟味)とは次元を異にする知との考え方でしたので使えませんが、アリストテレスの哲学は、すべてにおいて「万能の神の計画」があるというキリスト教神学には好都合で、ピタリとはまります。自然学と倫理学とは一つになり、壮大な物語がつくれますので、全世界・全人類をキリスト教神学≒学問で覆う(支配する)ことが可能となったのです。
では、なぜ古代ギリシャのアリストテレスが「目的因」という非学問的な思想を哲学の中心に入れたのでしょうか。それは、彼が、知の核心であるイデア論を否定 することでタレスに始まるプラトンまでの全ギリシャの知を統一しようとする意図をもったからなのですが、今は詳しくは書けません。
問題の核心は、「善美のイデアへの希求」という座標軸がなくなると、人間の生の意味と価値について吟味する足場が失われてしまうので、人間と自然のすべてを貫く「目的因」という物語をつくらざるを得なくなったことにあります。これによって、倫理や政治までも自然学から演繹されることになりましたが、それは、近代のドイツ観念論を通して遠く戦前の日本を代表する哲学者・田辺元(数学・物理学・哲学)にも影響し、天皇制の正当化の理論=「天皇を中心とする日本の国体は、太陽系と同じで、宇宙の原理に合致する」にもなっています。
このように自然学から意味不明の演繹をする異様な思考は、すべてに目的があるとする神話的な考え=「目的因」と重なっていますが、わたしはそこに、幼児のもつ「万能感」の延長がつくる歪みを感じ、怖さを覚えます。 肥大した外的自我の怖さです。それは、国家主義の論理を生み、一人ひとりの生への抑圧を正当化します。更に言えば、自然征服という人類中心のエゴイズムが生じたのも、この「目的因」という強引な概念のねつ造に深因があるように思えます。
ここでさらに歴史を遡ってみると、キリスト教など世界の三大宗教(旧約聖書のユダヤ教、新約聖書のキリスト教、コーランのイスラム教)を生んだ【セム語族】の文化と、
 (三大宗教の誕生地・エルサレムの市旗)
(三大宗教の誕生地・エルサレムの市旗)
仏教やギリシャ哲学を生んだ【印欧語族】(インド・ヨーロッパ語族)とは、大きく異なることを言わなくてはなりませんが、数千年前のインド~中東~ヨーロッパの民族移動と二つの文化の型の大きな違いは、今はその事実の確認だけに留めます。押さえておきたいポイントは、インドの釈迦(ブッダ)による仏教とギリシャ哲学は親近性を持っていることです。
話を戻します。
わたしの提唱する恋知とは、善美への憧れを不動の座標軸とする生き方のことですが、それはまた知の方法でもあり、各教科・学問の中で生きて働くものです。それ自身が自立・独立した体系ではありません。あらゆる知と生活世界に価値と意味をもたらす優れた態度のことです。内的に、内側から、内発的にですが、それを可能にするよい方法は、近くを見るのではなく、視線を遠くに飛ばす(例えば、空・雲という不定形なものを見る)ことですので、習慣づけるとよいでしょう。
 ((内的充実の極み、自らの純粋な悦びの行為として彫刻をつくったマイヨールの「夜」・上野の国立西洋美術館で。撮影は筆者)
((内的充実の極み、自らの純粋な悦びの行為として彫刻をつくったマイヨールの「夜」・上野の国立西洋美術館で。撮影は筆者)
強い宗教(一神教)がつくる「神」という絶対観念ではなく、また、世間の価値観に呪縛される世俗教(例えば、東大教)でもなく、第三の道である恋知の生には、特権的な人や場は、一つも存在しません。人間の生のよし悪しの基準は、「生活世界」(日常生活、仕事、活動、趣味)の中にのみありますので、日々の生活において感じ想うことを繰り返しよ~く見つめ、反省のふるいにかけることで、「私」の意識を明瞭で豊かなものにすることが何より大切になります。それこそが不動の座標軸(真理というのではなく、「正しさ」が現実的意味を持つ生の基準)となり、わたしたちの人生を支えます。 善美への憧れと探求こそが人間的な徳と得をもたらすのです。
ナンバー1でなくてもよい、オンリー1であれば、ではありません。誰もがみなオンリー1であることを自覚するのが何より大切。ナンバー1としてのナンバー1では人間的には価値がありません。ナンバー1とは他との比較でしかなく、単一の基準で測った結果ですので、競争主義者(機械人)の思想です。オンリー1として生きる人が、結果としてナンバー1と評されるのは結構なことですが、さらに、そのような人間評価自体への異議を唱えた人もいます。実存主義者のジャン・ポール・サルトルは、ノーベル文学賞を辞退したのです。
それでは、『白樺教育館』の標語を貼り付けて、第二章「恋知とは何か」のシメとしましょう。
他と(ひかく)するな 
他と競争(きょうそう)するな。
自分の
深い納得(なっとく)を目がけよ!
あなたもわたしも、
オンリー ワン
Only Oneであることを自覚(じかく)しよう!
追記
わたしは、この章で、人間の人間的生の本質について書きました。人間の望ましい生のありようをできるだけ明瞭に示せれば、生をより魅力的なものへ、生きる価値の大きなものへ、豊かな意味を持つものへ、と動かすことができるのではないか、そう思い試みました。個々の活動や仕事、具体的な事柄の手法については、優れた人が大勢いますので、それらについては彼らにお任せします。
2013年 9月 25日 武田康弘