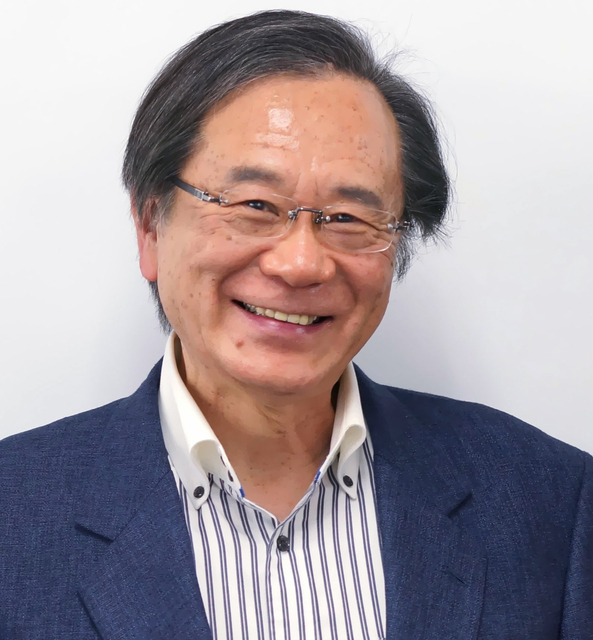以下の2008年市民アカデミアの総括は、豊富な写真入り(白樺教育館ホーム)で見ることができますので、以下をクリックしてください。
http://www.shirakaba.gr.jp/home/tayori/k_tayori97.htm
2008年「市民アカデミア」(大阪経済法科大学主催)『公務員を哲学する-市民社会と公共性を考える』の最後は、わたしが講師を務めましたが、わたしの企ては、従来の大学講座(一般市民を対象とした啓蒙)の発想とスタイルの双方を変えたいというものでした。「講義質疑応答」ではなく、参加者が講師の問題提起を受けて【共に哲学する実践】を目がけたのです。
残念ながら、参加者の意識はわが白樺同人を含めてまだまだ主体性が弱く、【生きた主観性の躍動】というレベルには達しませんでしたが、わたしは、企てをためらうことなく実行したのでした。
哲学とは「客観学」ではなく、ほんらい生きた対話であり、そのことは、理論=言語の次元で主張されただけでは意味を持たず、実際に主観性を鍛えあう熱い試み=生々しい実践でなくてなりません。「研究する」ものではなく、実際にやりあう=「躍動する生きた対話」なのです。大学講座で「勉強」する(教えてもらう)ことではないのです。
思想や哲学は、従来のスタイルそのものを変えなければ、いくら思想内容を変えたところでひとつの前進もない、それがわたしの不動の確信です。
ついでに言えば、倫理や道徳も同じです。古代の王制や封建社会や近代天皇制の下でつくられた「道徳」(為政者に都合のよいイデオロギー)を学んでもダメで、自由・平等・博愛の民主制社会にふさわしい新しい倫理は、ふつうの生活者の「生活世界から立ち昇る善美」につき、みなの話し合いによって生み出すものなのです。
本を読んだり本を書いたりすることは一つの手段であり、そのこと自体に価値があるのではないのです。しかし、この基本認識がきちんとできている人は極めてまれです。従来の知のスタイルの中に留まって、その中で「哲学する」ことは本質的には不可能だ、という認識を哲学に関与している人さえ未だに持てずにいるのですが、これは本当に困ったことです。「アカデミズム 内 哲学」では、生きた動詞としての哲学にはならず、哲学は死んでしまいます。
ヨーロッパの啓蒙時代は18世紀であり、日本の啓蒙時代は明治から敗戦までです。もうとっくに終わっているのが「教えるー教えられる時代」なのです。いま何より必要なのは、一人ひとりが自ら考える力を引き出しサポートする仕組み・態勢のはずです。「相互に考え・語り合う時代」をつくり・生きることが求められます。したがって、いま哲学は、哲学が大学内の一科目になる以前の「実際に人が生きている現場」から立ち昇ってくる問題にダイレクトに応答するという初心に戻らなければいけません。形而上学としての哲学では、趣味の世界にしかなりません。なぜ?どうして?なんのため?を具体的現実に即して考える営みが必要なのです。
互いの主観性を広げ、深め、豊かにするための実践はいかに可能か?
それに応える思想とそれを現実のものとするためのスタイルを考案し実践することーそれを目がける活動こそいま真に求められているのであり、それをわたしは恋知としての哲学=民知と呼んでいるわけです。
以上のような理念・考えから、
11月21日(金)のわたしが担当した講座では、わたしの話は40分に留めると宣言し(笑)、その通りに実行したのです。ただし、時間を短くした分、内容は、分明・明瞭でかつ刺激に富むものとしました。
また、当日参加された金泰昌(キム・テチャン)さん(「公共哲学」シリーズ全20巻の編集責任者)からも「15分間スピーチ」をしてもらいましたが、少し残念だったのは、わたしの話
=①「東大病」のこと。②ほんらい客観学は知の手段であり主観性の知こそが目的であること。③明治の国権派がつくった「天皇の官吏としての官僚制」に基づく政治は、客観学の支配により各人の主観性を無価値なものとみなすことが必要で、それが天皇教(=序列の絶対化による集団同調主義)という国家宗教と一体化した政治と軍事と教育を生んだこと。④キャリアシステムを支えているのは、未だに清算が済んでいないそのような想念であること。
から話題がそれてしまったことです。
わたしもまた、もっと明瞭に踏み込んで(キツク・笑)主題が浮かび上がるようにすべきだったと思います。それが反省点です。
【共に哲学する】を実現するには、まだまだ多くの創意工夫が不可欠だな、と強く感じました。今後の課題です。宿題としましょう。
武田康弘
http://www.shirakaba.gr.jp/home/tayori/k_tayori97.htm
2008年「市民アカデミア」(大阪経済法科大学主催)『公務員を哲学する-市民社会と公共性を考える』の最後は、わたしが講師を務めましたが、わたしの企ては、従来の大学講座(一般市民を対象とした啓蒙)の発想とスタイルの双方を変えたいというものでした。「講義質疑応答」ではなく、参加者が講師の問題提起を受けて【共に哲学する実践】を目がけたのです。
残念ながら、参加者の意識はわが白樺同人を含めてまだまだ主体性が弱く、【生きた主観性の躍動】というレベルには達しませんでしたが、わたしは、企てをためらうことなく実行したのでした。
哲学とは「客観学」ではなく、ほんらい生きた対話であり、そのことは、理論=言語の次元で主張されただけでは意味を持たず、実際に主観性を鍛えあう熱い試み=生々しい実践でなくてなりません。「研究する」ものではなく、実際にやりあう=「躍動する生きた対話」なのです。大学講座で「勉強」する(教えてもらう)ことではないのです。
思想や哲学は、従来のスタイルそのものを変えなければ、いくら思想内容を変えたところでひとつの前進もない、それがわたしの不動の確信です。
ついでに言えば、倫理や道徳も同じです。古代の王制や封建社会や近代天皇制の下でつくられた「道徳」(為政者に都合のよいイデオロギー)を学んでもダメで、自由・平等・博愛の民主制社会にふさわしい新しい倫理は、ふつうの生活者の「生活世界から立ち昇る善美」につき、みなの話し合いによって生み出すものなのです。
本を読んだり本を書いたりすることは一つの手段であり、そのこと自体に価値があるのではないのです。しかし、この基本認識がきちんとできている人は極めてまれです。従来の知のスタイルの中に留まって、その中で「哲学する」ことは本質的には不可能だ、という認識を哲学に関与している人さえ未だに持てずにいるのですが、これは本当に困ったことです。「アカデミズム 内 哲学」では、生きた動詞としての哲学にはならず、哲学は死んでしまいます。
ヨーロッパの啓蒙時代は18世紀であり、日本の啓蒙時代は明治から敗戦までです。もうとっくに終わっているのが「教えるー教えられる時代」なのです。いま何より必要なのは、一人ひとりが自ら考える力を引き出しサポートする仕組み・態勢のはずです。「相互に考え・語り合う時代」をつくり・生きることが求められます。したがって、いま哲学は、哲学が大学内の一科目になる以前の「実際に人が生きている現場」から立ち昇ってくる問題にダイレクトに応答するという初心に戻らなければいけません。形而上学としての哲学では、趣味の世界にしかなりません。なぜ?どうして?なんのため?を具体的現実に即して考える営みが必要なのです。
互いの主観性を広げ、深め、豊かにするための実践はいかに可能か?
それに応える思想とそれを現実のものとするためのスタイルを考案し実践することーそれを目がける活動こそいま真に求められているのであり、それをわたしは恋知としての哲学=民知と呼んでいるわけです。
以上のような理念・考えから、
11月21日(金)のわたしが担当した講座では、わたしの話は40分に留めると宣言し(笑)、その通りに実行したのです。ただし、時間を短くした分、内容は、分明・明瞭でかつ刺激に富むものとしました。
また、当日参加された金泰昌(キム・テチャン)さん(「公共哲学」シリーズ全20巻の編集責任者)からも「15分間スピーチ」をしてもらいましたが、少し残念だったのは、わたしの話
=①「東大病」のこと。②ほんらい客観学は知の手段であり主観性の知こそが目的であること。③明治の国権派がつくった「天皇の官吏としての官僚制」に基づく政治は、客観学の支配により各人の主観性を無価値なものとみなすことが必要で、それが天皇教(=序列の絶対化による集団同調主義)という国家宗教と一体化した政治と軍事と教育を生んだこと。④キャリアシステムを支えているのは、未だに清算が済んでいないそのような想念であること。
から話題がそれてしまったことです。
わたしもまた、もっと明瞭に踏み込んで(キツク・笑)主題が浮かび上がるようにすべきだったと思います。それが反省点です。
【共に哲学する】を実現するには、まだまだ多くの創意工夫が不可欠だな、と強く感じました。今後の課題です。宿題としましょう。
武田康弘