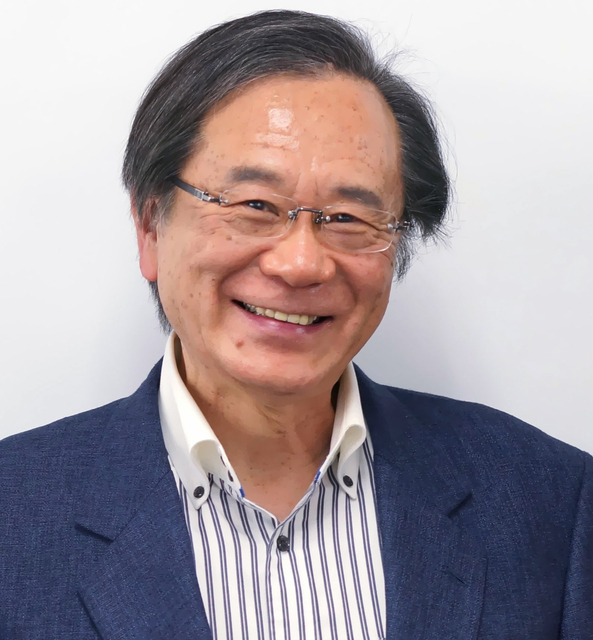『知らないと恥をかく世界の大問題5』(KADOKAWA/角川マガジンズ)
『知らないと恥をかく世界の大問題5』(KADOKAWA/角川マガジンズ)
LITERA(太字は武田による)
元経産官僚・古賀茂明の『報道ステーション』(テレビ朝日系)での発言以降、自民党の暴挙が続いている。自民党情報通信戦略調査会がテレビ朝日と『クローズアップ現代』のヤラセが指摘されたNHKを呼びつけ事情聴取を行ったが、それだけでは飽き足らず、BPOへの申し立ての検討、さらには政府自身がBPOに関与する仕組みを作るとぶち上げたのだ。
表現の自由が剥奪され、政府からの言論統制が敷かれるという恐るべき事態が進行しているわけだが、しかし、マスコミの動きは鈍い。
リテラは一貫して、安倍官邸の圧力とメディアの弱腰を批判してきたが、残念ながら弱小メディアがいくら叫んでも、相手にはしてもらえない。「報道の自由」をきちんと主張する影響力のあるメディア、言論人はいないのか。そう思っていたら、あの池上サンがこの問題について、かなり踏み込んだ発言をした。
4月24日、朝日新聞の連載「新聞ななめ読み」で「自民党こそ放送法違反だ」と政権与党への批判を展開したのだ。
〈これが欧米の民主主義国で起きたら、どんな騒動になることやら。放送局の放送内容に関して、政権与党が事情聴取のために放送局の幹部を呼び出す。言論の自由・表現の自由に対する権力のあからさまな介入であるとして、政権基盤を揺るがしかねない事件になるはずです。〉
池上はいきなり、こう断じたうえで、その理由を述べる。
〈では、なぜ自民党の行動は問題なのか。自民党が呼び出した理由は、放送法に違反した疑いがあるから。放送法の第4条第3項に「報道は事実をまげないですること」とあるからです。
しかし、実は放送法は、権力の介入を防ぐための法律なのです。
放送法の目的は第1条に書かれ、第2項は次のようになっています。「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」
つまり、「表現の自由」を確保するためのもの。放送局が自らを律することで、権力の介入を防ぐ仕組みなのです。〉
放送法の本来の理念は権力の介入を防ぎ、表現の自由を確保するもの。池上はそう明確に指摘する。そして同法は戦前の言論統制の反省から、権力から独立するためのもので、自民党の行為こそが、放送法違反だと批判するのだ。
だが、注目すべきは、池上が言論に介入する自民党を批判する一方で、メディアの対応をも批判していることだ。池上は新聞各紙の論調を取り上げながらこう指摘する。
〈いつもは論調に大きな違いのある新聞各紙が、この問題に関しては、自民党に批判的な立場で歩調を揃えています。それだけ重大な問題であるとの認識では共通しているのでしょう。〉
その上で、毎日新聞の〈放送は自主・自立が原則であり、放送局を萎縮させるような政治介入は控えなければならない〉(4月17日付社説)という主張について、こう疑問を呈するのだ。
〈ただ、毎日の社説を読むと、「放送局を萎縮させるような政治介入は控えなければならない」と書いています。では、萎縮させないような政治介入ならいいのか、と突っ込みを入れたくなる文章です。〉
池上は「政治介入は控えなければならない」ときっぱりと書くべきだったと指摘。そんな毎日新聞の態度が妙に微温的だとして、〈まさか萎縮なんか、していませんよね?〉と皮肉る。
読売新聞に対しても同様だ。同紙はやはり社説で〈放送免許の許認可権は、総務省が持っている。意見聴取は、政権側による「圧力」や「介入」との疑念を持たれかねない〉(4月18日付社説)という主張を、〈「本当はそうではないけれど」という文意が垣間見えます。〉と批判する。
確かに池上の指摘は本質をついたものだ。大手マスコミは表向き、批判のポーズをとっているが、実は完全に腰が引けている。
そもそも、古賀問題の本質は官邸から『報ステ』への圧力だ。菅義偉官房長官は、古賀が1月23日の放送で安倍首相のイスラム国問題への対応を批判した後、「オフレコ懇談」で「俺なら放送法に違反してると言ってやるところだけど」と放送法を使って恫喝をかけている。
また、放送中、菅官房長官の秘書官から『報ステ』の編集長あてに「古賀は万死に価する」という内容のショートメールが送りつけられてきたことも明らかになっている。
ところが、新聞・テレビはこうした圧力の明確な証拠があるにもかかわらず、一切報じようとしないのだ。
「各社ともそのときのオフレコメモはもっているんですが、官邸と癒着する政治部が絶対に記事にさせないんです。だから、当たり障りのない批判を書いてお茶を濁している」(全国紙社会部記者)
それでも、新聞は社説として主張を掲載するだけ、まだましかもしれない。最も直接的な当事者であるはずのテレビは、自ら論評することなく、事実と野党である民主党議員や学者のコメントをアリバイ的に垂れ流すのみだ。
特に呼び出された当の『報道ステーション』の惨状は目を覆うばかりだ。各社が事情聴取について報じるなか、この問題にようやく触れたのは事情聴取の当日。しかも民主党の細野豪志政調会長のコメントを紹介しただけで、司会の古舘伊知郎にいたっては「視聴者にまっすぐ向いてニュースを伝える」と腰砕けぶりを見せつけるしまつだった。
メディアだけではない。比較的、リベラルだと思われていたジャーナリストや評論家も同様だ。例えばジャーナリストの江川紹子は局側から制約を受けたことがないとして、古賀をこう批判している。
「公共の電波で自分の見解を伝えるという貴重な機会を、個人的な恨みの吐露に使っている」
衆院議員でジャーナリストでもある有田芳生もいち早く江川に賛同するかたちで違和感を表明。また経済評論家の森永卓郎も「古賀さんは番組を壊してしまった」と批判し、社会学者の古市憲寿は「僕の知ってる限りでは(圧力は)ない」として「古賀さん自体は勝手なこと言ってるだけだと思うんですね」と断じた。『モーニングバード』(テレビ朝日系)のコメンテーターなどをつとめながら、反権力的姿勢をつらぬいているジャーナリストの青木理も「基本的に楽屋の話でしょう」と古賀批判を口にしている。
繰り返すが、古賀が告発したのは『報ステ』への圧力であり、「個人的恨み」などではない。また、政権からの圧力は出演者に対して直接加えられるようなわかりやすいものでもない。彼らはこの騒動を古賀個人の問題に矮小化することで、結果的に政権による報道への圧力を正当化してしまっている。
そんななか、ジャーナリストとしてもっともメジャーな存在である池上彰が誰よりも踏み込んで、政権与党を批判したというのは、さすがという他はないだろう。実際、今回に限らず、池上はこれまでも一貫して報道の自由を守るための主張を展開してきた。
たとえば朝日新聞慰安婦報道に関しては、「週刊文春」(文藝春秋)14年9月25日号の連載コラムで、朝日バッシングに走るメディアをこう牽制した。
〈朝日の検証報道をめぐり、朝日を批判し、自社の新聞を購買するように勧誘する他社のチラシが大量に配布されています。これを見て、批判は正しい報道を求めるためなのか、それとも商売のためなのか、と新聞業界全体に失望する読者を生み出すことを懸念します。〉
さらに、メディアは「売国」などという言葉を使うべきではない、「国益」にとらわれるべきではないとも主張した。
〈メディアが「国益」と言い始めたらおしまいだと思います。(略)私は、国益がどうこうと考えずに事実を伝えるべきで、結果的に国益も損ねることになったとすれば、その政権がおかしなことをやっていたに過ぎないと思います。〉(「世界」岩波書店/14年12月号)
ほとんどのメディアが政権からの圧力を恐れ、批判を封印するなか、池上だけが正論を吐き続けているのだ。
しかし、その池上は、もともと左翼でもなんでもないニュートラルな解説者だったはずだ。そんな池上がいつのまにか一番リベラルなポジションにいるという事実が、日本の言論状況の危うさを証明しているというべきだろう。
(伊勢崎馨)
















 武田康弘
武田康弘 武田康弘
武田康弘