以下は、武田による「民主制の始源かつ本質」の定義です。昨日と一週間前の二回、わたしの地元・我孫子市の中央学院大学で講義しました。
古代ギリシャ(紀元前400年代)に起こったペリクレスによる民主制(市民による統治)も、ソクラテスの恋知=哲学(知への恋)も、共に、恋愛が象徴する「私」から始まります。
神への愛(アガペー)という宗教的な絶対感情や、
愛国主義=国家的集団主義の感情とは次元を異にする
恋愛(エロース)が象徴する「私」からはじまる公共性=相互性こそ が、人間性を肯定する民主制の政治(自覚したふつうの人々による統治) をつくる。
(※ 参考 厳しい必然の神・アナンケを打ち破ったのが恋愛の神・エロースです。したがって、エロース神とは、人間的自由の象徴でもあるのです。)

わたしたち日本人は、以上のような意味で「私」や「民主制における公共性」を捉えられないために、「私」の精神的自立を持てず、【形式と序列の支配】の中に埋没してしまうわけです。
集団的・仲間的「私」(あるいは宗教的「私」)しかないのでは、人間的魅力のない悦びに乏しい人生しか与えられません。「人間を幸福にしない日本というシステム」は、恋愛に象徴される「私」の脆弱さに由来しているのです。みなさん、「私」になりましょう!!
また、キリスト教という強い一神教により基礎づけられた人権と民主制をもつ欧米も、日本などとは逆の意味で歪んでいます。歴史的には近代民主制は欧米で現実化したわけですが、みなの納得を生む普遍的な了解を得る以上に、宗教的絶対の観念に縛られるために、民主制が豊かさや寛容性に向かわずに、主知主義的となり自己絶対化に陥りがちです。欧米人はその点を反省して、キリスト教のアガペーという愛よりも始原的なエロースの愛が開示する「私」に率直になることが求められます。「イデオロギー化された自我」ではなく、恋愛に象徴される「私」から公共性を考えなくてはいけません。
武田康弘
















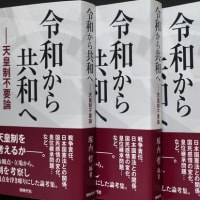

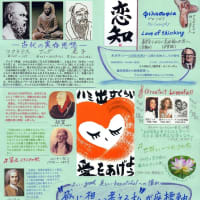







システムの中に埋没する人生など、まっぴらごめん! です。
日本は人間が人間らしく生きるにはあまりに生きづらい国と、息苦しさすら感じますが、おかしな権力に怯まずに私は「私」であり続けます。一度きりの大切な人生ですもの、囚われのない、心身から湧き出るよろこび、たのしみ多き生をおくりたいです。
私は大学で知的財産に関する仕事に携わっているのですが、業務の一環で「商標」に関する調査をしているうちに、このブログにたどり着きました。
「アナンケ」に関して商標を調べていたのですが、
ブログの内容が面白く、イロイロなページを拝読させていただきました。
ちなみに、(参考)に出てくる「厳しい必然の神・アナンケを打ち破ったのが恋愛の神・エロースです。」という内容について教えていただきたいのですが、
アナンケとエロースが実際に戦うというか、何か勝敗のつく事を行った記述があるのでしょうか?
参考までにご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
岩波の「プラトン全集」が出典です。
白樺教育館に置いてありますでの、
詳しくは後ほど、
楽しみにしております。
お尋ねの件ですが、
プラトン全集(岩波)5の十八です(58ページから61ページ)59ページの注の3がアナンケの説明。
早速近所の図書館で該当箇所を読んでみましたが、「注の3がアナンケの説明」は難解ですね。。。。
前後の文脈もあるかと思いますので、該当箇所以外も目を通してみます。
ご指導いただきありがとうございました。
ポイントは、「必然・厳禁の精神」 と 「恋愛が象徴する真面目・真剣」は、根本的に異なることです。
これが真に了解できると、人類の回心が起きるとわたしは見ます。
恋愛をキーワードにしたソクラテスは、その後の固真面目(必然と厳禁の精神によるキリスト教や近代になり誕生したマルクス主義)の狭さを超えています。
「恋知」が最大の人類的普遍性をもつのは、エロースという発想にある、わたしはそう確信しています。
大変参考になりました。
厚く御礼申し上げますとともに、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
「エロース(恋の神)が、神々の中に生まれ出たとき、神々のことは万事整え秩序だてられた。
それに反してそれ以前は、アナンケ(必然の神)の支配ゆえに、たくさんの怖ろしいことが起きていたのである。
ところが、エロースの神が生まれるや、美しいものを恋求めることからして、神々にも人間間にもすべてのよきことが生じたのである。」
以上は、「饗宴」の64ページ冒頭です(一部省略)、とても明快にソクラテス→プラトンの思想の芯が語られています。ここが肝です。