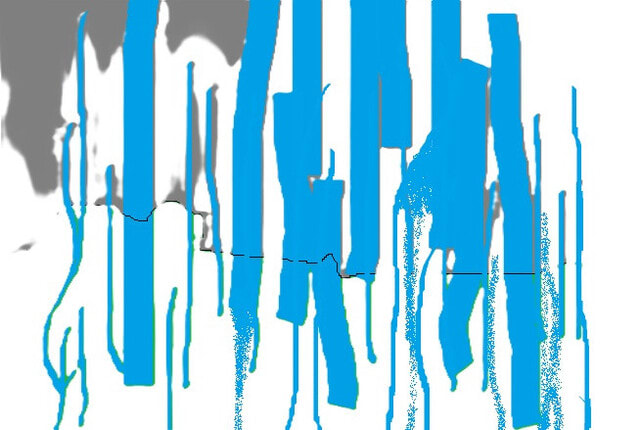商人が栄えるのはただ若者の乱費のためだし、百姓が栄えるのはただ麦が高いためだし、建築家が栄えるのは家が倒れるため、裁判官が栄えるのは世に喧嘩訴訟がたえないためである。聖職者の名誉とお仕事だって、我々の死と不徳から生ずるのだ。「医者は健康がきらいで、その友人が健康であることさえよろこばない。軍人は平和がきらいで、自分の町の平和をさえよろこばない」と古代ギリシアの喜劇作者は言ったが、その他何でもそんなわけである。いや、なお悪いことには、皆さんがそれぞれ心の底をさぐってごらんになるとわかるが、我々の内心の願いは、大部分、他人に損をさせながら生れ且つ育っているのである。
商人が栄えるのはただ若者の乱費のためだし、百姓が栄えるのはただ麦が高いためだし、建築家が栄えるのは家が倒れるため、裁判官が栄えるのは世に喧嘩訴訟がたえないためである。聖職者の名誉とお仕事だって、我々の死と不徳から生ずるのだ。「医者は健康がきらいで、その友人が健康であることさえよろこばない。軍人は平和がきらいで、自分の町の平和をさえよろこばない」と古代ギリシアの喜劇作者は言ったが、その他何でもそんなわけである。いや、なお悪いことには、皆さんがそれぞれ心の底をさぐってごらんになるとわかるが、我々の内心の願いは、大部分、他人に損をさせながら生れ且つ育っているのである。
そう考えているうち、ふとわたしは、自然がこの点においても、その一般的方針にそむいていないことに気がついた。まったく博物学者は、物の出生・成長・繁殖はそれぞれ他の物の変化腐敗であると説いているのである。
まことに物その形と性質とを変えるとき、
前にありしものの死のあらざることなし。(ルクレティウス)
――モンテーニュ「随想録」関根秀雄訳
トランプは商人だが、物をあっちからこっちに動かすときに生じる利益をくすねるようなやつではなく、悪徳とか死とか憎しみとかを消費する聖職者とか教師とかに近い。上のモンテーニュの「一方の得が一方の損になる」という感じである。これは一般には――というか本人にとっては道徳とか倫理とか正義とか呼ばれ得ると考えられるが、モンテーニュが思うように「それが自然じゃないか」という直感に裏打ちされているため、非常にやっかいなことなる。自らの正義を我々は唯単に盲信しているのではない。
これに対して、非自然的なものを構築するという意味で、官僚組織とモダニズム芸術は案外相性がよい。ソ連なんかをみればよい。だから、官僚をつくるための試験を、自然的なものを追求する科学者や医者の卵に受けさせているのはあまりよくないんじゃないか。対して、思うに、文士の場合は案外いいと思うのだ。文士に必要なのは想像力ではあるが、ジャンプ台がいつも必要であって、彼らは、非人間的なものを消費するのである。
最近、世界に冠たる映画「新幹線大爆破」をリメイクするらしいが、ほんと藤岡弘の運転手役の代わりとか居るのか?とおもっていたら、必殺能年玲奈だそうである。がんばって頂きたい。がっ、このリメイクを「シン」なんとかといって溜飲を下げているアーチストたちをみていると、彼らにとっての非人間的なものが作品以外の現実であることがよくわかる。もうはっきり申しあげたほうがよいが、この場合、その現実とは「リニア新幹線
大爆破」にほかならぬ。逃避ではなく、現実がタブー化しているから「新幹線大爆破」と言っているにすぎないのである。その保守性を、能年玲奈で埋めている。かんがえてみたら、もとの「新幹線大爆破」の新幹線より、現実の新幹線の顔が次第に不細工になっていくのはなんですかルッキズムへの抵抗ですかああそうですか。
高度成長の香り高い時代は「新幹線大爆破」でもよかったかもしれないが、もはや時代は貧乏な感じなので「新幹線代爆破」といわれてなにもすっきりしないそんなかんじである。爆発的なものはすでに想像力ではない。数ある爆発が起こるマンガでもすべてそうなっている。
在来の審美学なんか、その原子爆弾の微小なる破片によつてもぶち碎かれてゐる筈だ。最初の原爆体験者の日本に於ては、西洋にもまさつた異色ある新文学が起るべき筈だ。
――正宗白鳥『読書雑記』
正宗白鳥はいつも、おおくの人の想像力というものが、その「審美学」にすら達しないかたちで、爆発と自意識の間をふわふわ動いており、たいがい愛玩物を見つけて落ち着いているからくりを軽視している。昨日も書いたが、この愛玩物志向がわりと物に誠実なかたちをとると、変形とか変身への期待というかたちをとる。想像力についてモンテーニュは語る。
それから、寝る時には何ともなかったのに夜中に頭に角がはえたなどいう話は別に事新しくもないけれども、イタリア王キップスの事跡はやはり特筆するに足りるものである。彼は昼間熱心に闘牛を見物し、夜はよもすがら頭の上に角をいただいた夢を見たせいで、とうとう想像の力によってほんとうに額の真中に角をはやしたというのである。強い悲しみはクロイソスの息子に、自然が彼に拒んだ声を与えた。またアンティオコスは、その心にストラトニケの美しさをあまりに深く刻みこんだために熱を出した。プリニウスは、ルキウス・コッシティウスがその結婚の日に女から男に変じたのを、見たと言っている。ポンタノ及びその他の人々も、近世においてイタリアにおこった同様の変身を物語っている。それから、彼およびその母の切なる祈願によって、
イフィスは男となりて娘なりし日の誓いを果したり。(オウィディウス)
こういう真実は、次第にメディアの「映像」のなかに押し込められた。モンテーニュが言っているのは、実際に角が見える事態ではなく、実際に起きるという「カフカ」的な意味であった。現代の口承文芸的なものも、むしろネットのおしゃべりの中に実現したが、その実際におきる「カフカ」的な変身(はっきり申し上げると「差別」である)から逃避している。悪い意味で愛玩物的である。学校においてもSDGs関係の活動が愛玩物的になりがちであり、それらは差別の問題をスルーするための活動になってしまいがちである。SDGsの各問題がつながっているから問題だろうに。
そもそも問題を理解せずに実践するとろくな事にならないということは、実践してから分かることではなく、まずは言葉上で認識すべきである。実際に「起こる」ことは言葉上で起こるからだ。それが分かるために「勉強」しているのに、なんのために「勉強」をやっているかわからないじゃないか。そういえば、よく生徒や学生がその活動に於いて、半端な認識で市民に説教してもっと「意識高い系」に怒られるみたいなことがあるが、そうするともっと意識が低い人に啓蒙すればよいみたいに改心し、みずからもっと低い認識に墜ちてゆく――のは、むかしから飽きるほど繰り返されてきている事態でそういう事はまず体を動かす前に認識すべきなのである。だいたいその「意識高い系」は、問題が愛玩物のように単独で存在しているかのような錯覚に陥って居ることが多く、怒られる側もそうなのだ。そういう「系」の人間は、だいたい他人事をやめよとか自分事みたいな鈎語で他人を自分の問題に引っ張り込もうとするけれども、そこまでみんなバカじゃないのである。モンテーニュのいう想像の力で、現実が言葉のように見えているからだ。一見ジャーゴンにみえるけれどもそうでない場合があるのだ。
事務的な文書ばかりみてると、文学作品に対して、自由な解釈を許していて素晴らしいと言ってしまう人の気持ちも全くわからないではない。事務的なものは、それを作った側の運用上の自由がわりとあるが、与えられた側にあまり自由はない。あたかもコンプライアンスを無視する自由のようなパワーが必要なのである。それは想像力である。モンテーニュは、それを性の世界の妄想みたいなものから導き出そうとしている。コンプラの世界がそれを抑圧するのは当然のことだ。