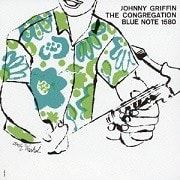本日はジョニー・グリフィンの少し変わった作品をご紹介します。名付けて「ジョニー・グリフィンズ・スタジオ・ジャズ・パーティ」。ニューヨークのスタジオに知り合いを招き、MCを入れたパーティ形式で演奏したものです。スタジオ録音なのかライブ録音なのかどっちやねん!とツッコみたくなりますが、この頃(1960年)のグリフィンは以前「ザ・ケリー・ダンサーズ」で書いたように少し変わった試みを色々していたようなので、その一環でしょうか?
メンバーはデイヴ・バーンズ(トランペット)、ノーマン・シモンズ(ピアノ)、ヴィクター・スプロールズ(ベース)、ベン・ライリー(ドラム)と言った顔ぶれ。グリフィンのリヴァーサイド作品の中では比較的地味なメンツですが、デイヴ・バーンズはビバップ期から活躍する隠れた実力者ですし、ノーマン・シモンズもシカゴ時代からのグリフィンの旧知で、「ザ・リトル・ジャイアント」や「ビッグ・ソウル・バンド」にも楽曲を提供しています。MCを務めるのはバブス・ゴンザレス。ジャズシンガー兼作曲家、さらにジャズクラブのオーナーを務めるなどマルチな活躍をする人物だったようで、彼のおしゃべりもたっぷり収録されていますが、残念ながら何を言っているのかよくわかりません・・・

全6曲。ただし、1曲目"Party Time"はバブス・ゴンザレスのおしゃべりなのでスキップしましょう。続くタッド・ダメロンの名曲”Good Bait"が実質的なオープニングです。ジョン・コルトレーン「ソウルトレイン」の名演でも知られるこの曲ですが、グリフィンはよりソウルフルに迫ります。デイヴ・バーンズとノーマン・シモンズも好調なプレイぶり。歓声や拍手も入って演奏を盛り上げます。3曲目は定番スタンダード”There Will Never Be Another You"をバーンズ→シモンズ→グリフィンのソロ順でドライブ感たっぷりに料理します。
4曲目”Toe-Tappin'"はデイヴ・バーンズのオリジナル。実にファンキーな曲でバーンズのパワフルなソロの後、シモンズを挟んでグリフィンが怒涛のテナーソロを披露します。聴衆も興奮していますね。5曲目は一転して大人の哀愁漂うバラード”You've Changed"。バーンズとグリフィンがダンディズム溢れるバラードプレイで魅了してくれます。6曲目”Low Gravy"はバブス・ゴンザレス作となっていますが、どこかで聞いたことある曲。グリフィンも参加した「ブルース・フォー・ドラキュラ」によく似たマイナー調のファンキーチューンです。以上、グリフィンはもちろんのことデイヴ・バーンズ、ノーマン・シモンズの隠れた実力も知ることのできる1枚です。