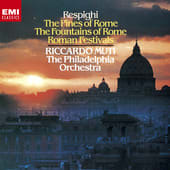最近すっかりはまっているヴァイオリン協奏曲シリーズ。今日はドヴォルザークです。ドヴォルザークはピアノ、ヴァイオリン、チェロと1曲ずつ協奏曲を残していますが、そのうちチェロ協奏曲が圧倒的に有名で、単に「ドヴォコン」と言えばこの曲を指すぐらいです。私もチェロ協奏曲は以前から愛聴しているのですが、一方でヴァイオリンについてはシカトしておりました。しかし聴いてみると一体なぜこの曲がもっとメジャーにならないのか不思議で仕方ないくらい素晴らしい曲です。
第1楽章、いかにもドヴォルザークらしい重厚なオーケストラをバックに哀愁たっぷりのヴァイオリンソロが繰り広げられます。第2楽章は一転ゆったりしたアダージョ。美しく叙情的な旋律が胸に沁みます。第3楽章はロンド形式で踊り出したくなるような旋律。随所にヴァイオリンの技巧の見せ所もあり、エンターテイメント性にあふれた名曲と言えるでしょう。

CDはフランク・ペーター・ツィンマーマンのヴァイオリン、フランツ・ウェルザー=メスト指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団のものを買いました。このCDにはもう1曲、ロシアの作曲家グラズノフのヴァイオリン協奏曲も収められていますが、この曲もまた名曲と呼ぶにふさわしい内容。20分弱の短い作品ですが、いかにもロシア的なロマンチシズムあふれる作品です。全体が切れ目なく演奏される単一楽章的な構成ですが、中間部の美しいアンダンテと華やかなロンド形式のフィナーレが最高です。ヴァイオリン協奏曲の名曲探し、まだまだ奥が深そうです!
第1楽章、いかにもドヴォルザークらしい重厚なオーケストラをバックに哀愁たっぷりのヴァイオリンソロが繰り広げられます。第2楽章は一転ゆったりしたアダージョ。美しく叙情的な旋律が胸に沁みます。第3楽章はロンド形式で踊り出したくなるような旋律。随所にヴァイオリンの技巧の見せ所もあり、エンターテイメント性にあふれた名曲と言えるでしょう。

CDはフランク・ペーター・ツィンマーマンのヴァイオリン、フランツ・ウェルザー=メスト指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団のものを買いました。このCDにはもう1曲、ロシアの作曲家グラズノフのヴァイオリン協奏曲も収められていますが、この曲もまた名曲と呼ぶにふさわしい内容。20分弱の短い作品ですが、いかにもロシア的なロマンチシズムあふれる作品です。全体が切れ目なく演奏される単一楽章的な構成ですが、中間部の美しいアンダンテと華やかなロンド形式のフィナーレが最高です。ヴァイオリン協奏曲の名曲探し、まだまだ奥が深そうです!