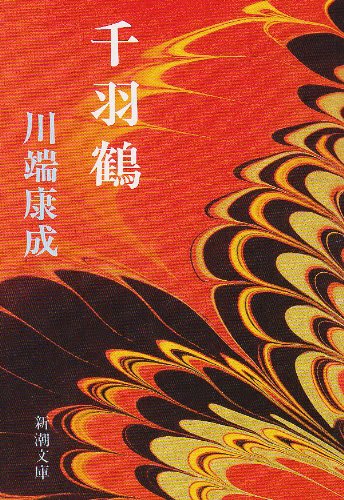
この本を読んでみようと思った動機の一つは、ときどき坐禅会に参加している円覚寺が舞台として出てくる有名な小説であること。もう一つは、この高名なノーベル賞作家の作品を一度は読んでおきたいと前から思っていたことである。
夏目漱石の「門」では円覚寺が物語の最後のほうに出てくるが、川端康成の「千羽鶴」では「鎌倉円覚寺の境内にはいってからも」と冒頭から円覚寺が出てくる。円覚寺の塔頭、仏日庵での茶会から小説は始まり、男女の間柄についてとんとんとんと物語は進んでいくが、尻切れトンボな終わり方をする。起承転結の結がない。読者は中途半端な場所に置いてきぼりにされる。だから読後感は気持ちのいいものではない。ストーリーの中に、人生の希望や救いは感じられない。主人公の菊治はまっとうな女性との平和な結婚生活を始めるのだが、自殺したある未亡人とその娘に対する甘美で狂おしい記憶にとらわれてしまって抜け出すことができない。
物語を構成している大きな要素は、志野や織部といった美しい陶器たちである。作られてから400年もの間、多くの人たちに所有されて半永久的な生を生きてきているようにも思える。それと対比して、人間の生のなんてはかないことか。死はいつも足元にある。ある織部の茶碗は、未亡人の夫、菊治の父、未亡人、未亡人の娘、そして菊治へと持ち主が変遷してきた。そのうちの3人はすでにこの世にいない。女と芸術の美、そして人生のはかなさが混然とした世界観が示された小説である。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます