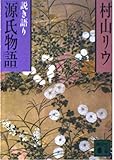昨日は23度、今日は28度、お店の中はがんがん冷房入っていますね、これは具合悪くなってしまいそうです。今日も電車には乗りませんでしたが、遅いお昼を外で食べるべく外に出ました。それから請求書の内容確認のために、苦手であまり行きたくない携帯・インターネットプロバイダのショップへ。商売ってほんとに上手くできているなあとため息。まだ陽が高かったのでもう一軒お店に入ってしばし過ごしてから帰宅。お仕事帰りのみなさんがお店に入ったり買い物したりする時間で正直羨ましかったです。わたしだって仕事する力がある、また仕事をしたいという気持ちが募りました。荷物減らしは自分の部屋でしかできませんがずっといるのは不健康だし、集合住宅はむずかしいし、お金がかかっても外に出る時間は必要。ほんの二週間前まで毎朝7時半過ぎには部屋を出て出勤していたわたしが、明日の朝めっちゃ不安で緊張しています。今夜眠れても眠れなくてもとにかく8時半には部屋を出ること。1時間かかりませんけどね、頭の中が煮詰まって飽和状態だし、一人でいるとどんどん自分を追いつめてしまって自信喪失になるばかり。荷物と洋服の準備をしたら考えない、考えない。無理ですけどね。二週間前まで朝早かったわたしがこうして日中いるようになったんだからヘンだよなあ、いやだよなあ。鍵神経症のところがあるし、不安。プリンス・エドワード島まで一人で旅する奴が何言ってんだよ、大丈夫、大丈夫、きっと。
ふたりのシシィ‐花ちゃん、宝塚を退団後舞台から離れて三年間に、また舞台に立つ時がくるとは思わなかった。蘭ちゃん、宝塚を退団直後、また舞台に立つとは全く思っていなかった。石丸幹二さん、劇団四季を退団後一年間は身動きとれず近所の公園を散歩するところからリハビリをはじめ再出発。現在(いま)、それぞれ舞台の上で輝いています。その姿に元気をもらっています。
誰にも沈黙の時、身動きのとれない時は訪れます。13年間も心身をすり減らしながら働いたカイシャから使い捨てにされて三年。わたしを弱らせるために登場した、その筋の筋金入りの弁護士にずたずたにされ、気力が失せてどうにも動きとれなくなったところから、運とタイミングでここまで立ち上がってくることができました。かなり手荒な1年3カ月のリハビリの時を過ごしました。去年の一月、郷里のお墓の前で泣き崩れていた時には全くまた働く自分の姿を全く想像できませんでしたが、わたし働ける力があるんだって確認できました。ここまででも十分にIt,s all right.どこにこれからのわたしの役割があるのか手探りですがこの1年3カ月の経験は大きいのできっと大丈夫。明日行くところが自分の役割なのか、そうでないのか。縁があれば役割なんだし、縁がなければ役割ではなかったということ。日中の居場所と収入がないのがやっぱりつらくって、でもまだまだ色々とぐちゃぐちゃなので少しずつ、少しずつ。ここまでやってきただけで十分にIt,s all right.明日の朝、無事に部屋を出られますように・・・。
今日もつまらない徒然日記でした。
ふたりのシシィの写真は、2015年夏、日比谷シャンテ『エリザベート』パネル展で撮影。

ふたりのシシィ‐花ちゃん、宝塚を退団後舞台から離れて三年間に、また舞台に立つ時がくるとは思わなかった。蘭ちゃん、宝塚を退団直後、また舞台に立つとは全く思っていなかった。石丸幹二さん、劇団四季を退団後一年間は身動きとれず近所の公園を散歩するところからリハビリをはじめ再出発。現在(いま)、それぞれ舞台の上で輝いています。その姿に元気をもらっています。
誰にも沈黙の時、身動きのとれない時は訪れます。13年間も心身をすり減らしながら働いたカイシャから使い捨てにされて三年。わたしを弱らせるために登場した、その筋の筋金入りの弁護士にずたずたにされ、気力が失せてどうにも動きとれなくなったところから、運とタイミングでここまで立ち上がってくることができました。かなり手荒な1年3カ月のリハビリの時を過ごしました。去年の一月、郷里のお墓の前で泣き崩れていた時には全くまた働く自分の姿を全く想像できませんでしたが、わたし働ける力があるんだって確認できました。ここまででも十分にIt,s all right.どこにこれからのわたしの役割があるのか手探りですがこの1年3カ月の経験は大きいのできっと大丈夫。明日行くところが自分の役割なのか、そうでないのか。縁があれば役割なんだし、縁がなければ役割ではなかったということ。日中の居場所と収入がないのがやっぱりつらくって、でもまだまだ色々とぐちゃぐちゃなので少しずつ、少しずつ。ここまでやってきただけで十分にIt,s all right.明日の朝、無事に部屋を出られますように・・・。
今日もつまらない徒然日記でした。
ふたりのシシィの写真は、2015年夏、日比谷シャンテ『エリザベート』パネル展で撮影。