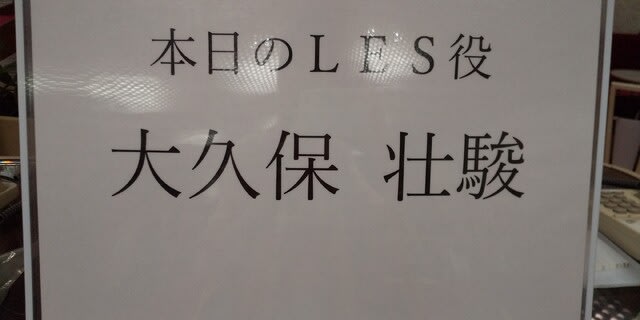フランクル『夜と霧』より-第一段階収容-最初の反応
「被収容者はショックの第一段階から、第二段階である感動の消滅段階へと移行した。内面がじわじわと死んでいったのだ。これまで述べてきた激しい感情的反応のほかにも、新入りの被収容者は収容所での最初の日々、苦悩にみちた情動を経験したが、こうした内なる感情をすぐに抹殺しにかかったのだ。
その最たるものが、家に残してきた家族に会いたいという思いだ。それは身も世もなくなるほど激しく被収容者をさいなんだ。それから嫌悪があった。あらゆる醜悪なものに対する嫌悪。被収容者をとりまく外見的なものがまず、醜悪な嫌悪の対象だった。彼はおおかたの仲間と同じように、ぼろの「おしきせを着」せられた。案山子のほうがよっぽどましだった。収容所の棟と棟のあいだは一面のぬかるみだ。泥をどかしたり、あるいは「地ならし」をするために、わたしたちは泥まみれになった。新入りは、往々にして便所掃除や糞尿の汲み取りを受け持つ作業グループに配属された。糞尿は、でこぼこの地面を運んでいくとき、しょっちゅう顔にはね返るが、ぎょっとしたり拭おうとしたりすれば、かならずカボーの一撃が飛んできた。労働者が「上品ぶる」のが気にさわったのだ。
こうして、正常な感情の動きはどんどん息の根を止められていった。被収容者は点呼整列させられ、ほかのグループの懲罰訓練を見せられると、はじめのうちは目を逸らした。サディスティックに痛めつけられる人間が、棍棒で殴られながら決められた歩調を強いられて何時間も糞尿のなかを行ったり来たりする仲間が、まだ見るに耐えないのだ。
数日あるいは数週間もたつと、被収容者はもう変わっていた。朝、まだ暗いうちに、作業グループとともにゲートの前で行列の出発を待っているとき、彼は叫び声を耳にする。そちらを見ると、仲間が何度も地べたに殴り倒されていた。立ちあがってはまた殴り倒される。なぜだ。その男が熱を出したからだ。それがゆうべのことだったので、期限内に(診療所で)熱を処置してもらうことも、病気を報告することもできなかったからだ。そして朝になって、所外労働に出なくてすむよう、病気届を出してもらおうと無駄な試みをしたために、今、罰を受けているのだ。ながめる被収容者はすでに心理学で言う、反応の第二段階にはいっており、目を逸らしたりしない。無関心に、なにも感じずにながめていられる。心に小波(さざなみ)ひとつたてずに。
あるいはまた、被収容者は夕方、診療所で押しあいへしあいして立っていた。彼らは、怪我か飢餓浮腫か熱のために、二日間の「静養」を処方してもらえないだろうか。そうすれば、二日は労働に出なくてすむのだが、というはかない望みを追っていた。そこに12歳の少年が運びこまれた。靴がなかったために、はだしで雪のなかに何時間も点呼で立たされたうえに、一日中所外労働につかなければならなかった。その足指は凍傷にかかり、診療所の医師は壊死(えし)して黒ずんだ足指をピンセットで付け根から抜いた。それを被収容者たちは平然とながめていた。嫌悪も恐怖も同情も憤りも、見つめる被収容者からはいっさい感じられなかった。苦しむ人間、病人、瀕死の人間、死者。これらはすべて、数週間を収容所で生きた者には見慣れた光景になってしまい、心が麻痺してしまったのだ。
短期間、わたしは発疹チフス病棟に入っていた。まわりじゅうが高熱を発し、せん妄状態にある患者で、多くは死を待つばかりだった。またひとり死んだ。するとなにが起こるか。X回目に。感情的な反応など、もはや呼び覚まされない。いったいなにが起こるのか。見ていると、仲間がひとりまたひとりと、まだあたたかい死体にわらわらと近づいた。ひとりは、昼食の残りの泥だらけのじゃがいもをもせしめた。もうひとりは、死体の木靴が自分のよりましなことをたしかめて、交換した。三人目は、同じように死者と上着を取り替えた。四人目は、(本物の!) 紐を手に入れて喜んだ。
わたしはなにもせずにただ見ていた。そしてやっとのことで起きあがり、「看護人」に死体を、文字どおりの掘っ立て小屋から出してくれるよう、頼んだ。看護人はしばらくしてようやくやる気を起こすと、死体の足をつかみ、右にも左にも50人の高熱を発している人びとが横たわっている板敷きのあいだの狭い通路に転げ落とし、でこぼこの土の床を棟の入り口まで引きずっていった。外に出るには階段を二段、上がるのだが、これがわたしたち慢性的飢餓状態にあり衰弱しきっている者にとっては大問題だった。何か月も収容所で過ごした今、わたしたちはみな、両手で柱にすがって体を引きあげないと、足の力だけでは自分の体重を20センチだけ二回持ちあげることなど、とっくにできなくなっていた。
看護人が死体を引きずってやってきた。まずは自分がやっとの思いで段を上り、それから死者を外へと引きずりあげた。足のほうから、ついで胴体、最後にごんごんと不気味な音をたてて頭部が、二段の階段を越えていった。
その直後、スープの桶が棟に運びこまれた。スープは配られ、飲み干された。わたしの場所は入り口の真向いの、棟の奥だった。たったひとつの小さな窓が、床すれすれに開いていた。わたしはかじかんだ手で熱いスープ鉢にしがみついた。がつがつと飲みながら、ふと窓の外に目をやった。そこではたった今引きずり出された死体が、据わった目で窓の中をじっとのぞいていた。二時間前には、まだこの仲間と話をしていた。わたしはスープを飲みつづけた。
もしも職業的な関心から自分自身の非情さに愕然としなかったとしたら、このできごとはそもそも記憶にとどまりもしなかったと思う。感情喪失はそれほど徹底していた。
こんなふうに、わたしたちがまだもっていた幻想は、ひとつまたひとつと潰(つい)えていった。そうなると、思いもよらない感情がこみあげた。やけくそのユーモアだ! わたしたちはもう、みっともない裸の体のほかには失うものはなにもないことを知っていた。早くもシャワーの水がふりそそいでいるあいだに、程度の差こそあれ冗談を、とにかく自分では冗談のつもりのことを言いあい、まずは自分自身を、ひいてはおたがいを笑い飛ばそうと躍起になった。なぜなら、もう一度言うが、シャワーノズルからはほんとうに水が出たのだ・・・!
やけくそのユーモアのほかにもうひとつ、わたしたちの心を占めた感情があった。好奇心だ。わたし自身は、生命がただならぬ状態に置かれたときの反応としてのこの心的態度を、別の場面で経験したことがあった。それまでにも生命のの危険に晒されると、たとえば山で岩場をよじ登っていてずるっと足を滑らせたときなど、その数秒間(あるいはたぶん何分の一秒間か)、ある心的態度でこの突発的なできごとに対処していたのだが、それが、自分は命拾いするだろうか、しないだろうか、骨折するなら頭蓋骨だろうか、ほかの骨だろうか、といった好奇心だった。
アウシュヴィッツでもこれと同じような、世界をしらっと外からながめ、人びとから距離をおく、冷淡と言ってもいい好奇心が支配的だった。さまざまな場面で、魂をひっこめ、なんとか無事やりすごそうとする傍観と受身の気分が支配していたのだ。わたしたちは好奇心の塊だった。」
(ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧(新版)』2002年 みすず書房、30-37頁より)