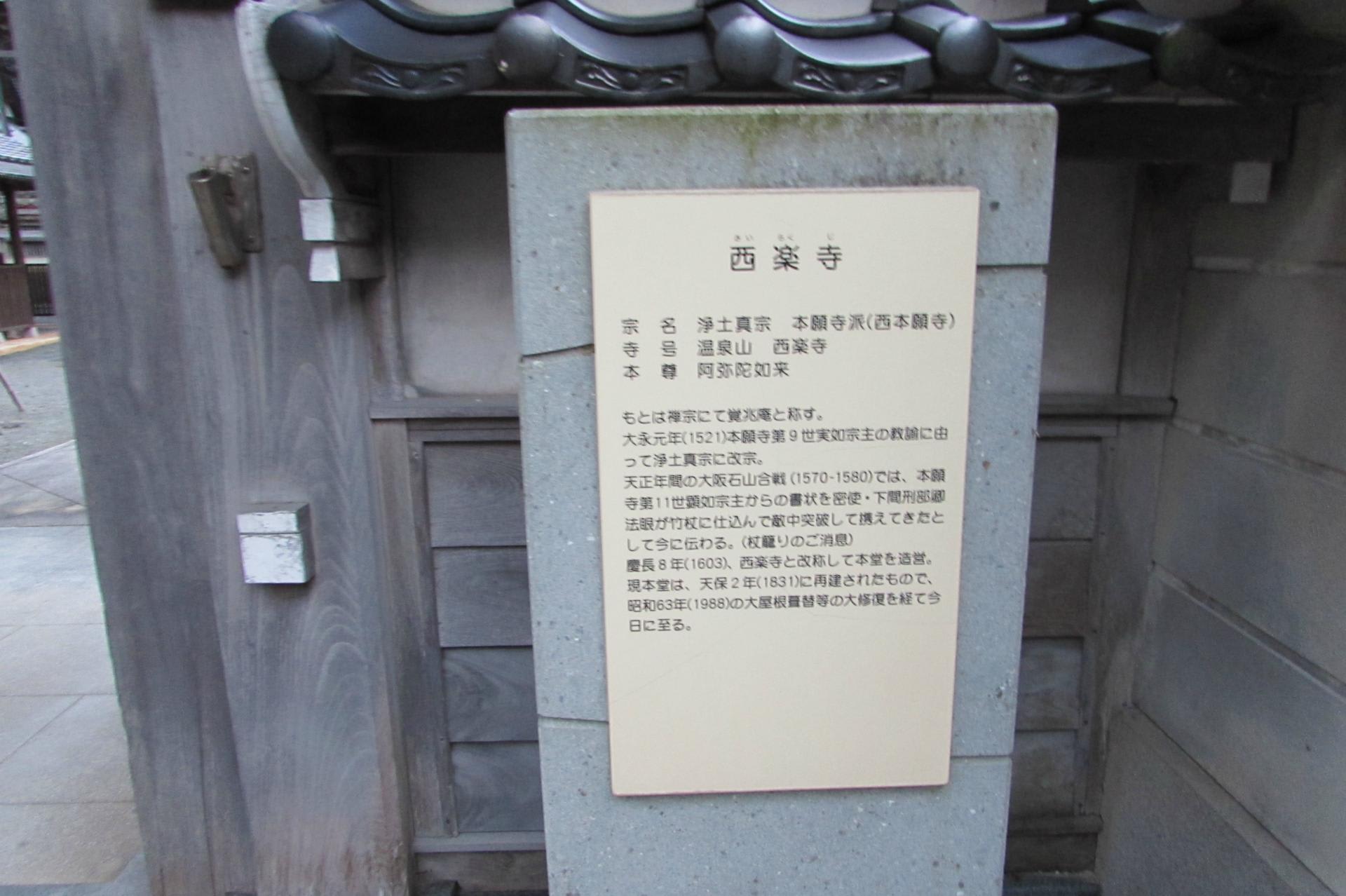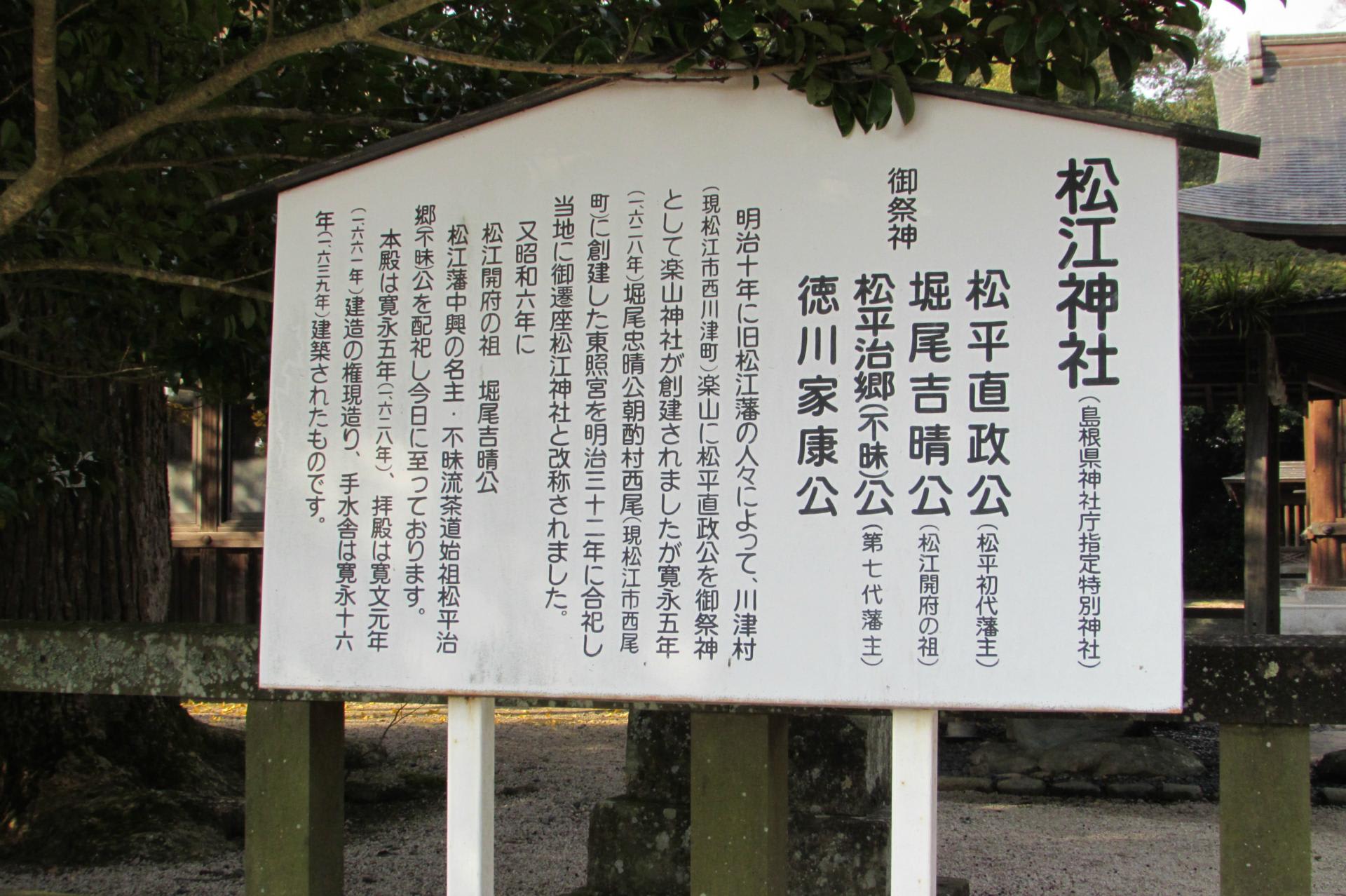2015年12月6日、5日に温泉津温泉に宿泊し、今日は、石見銀山の町並みを散策します。石見銀山公園無料駐車場に自動車を止めます。観光案内所でマツプと説明を聞きました。一部遊歩道が通れないとのことでした。
map
案内図

観光案内所

羅漢寺










町並みに進みます。















金森家(島根県指定史跡)、石見銀山御料郷宿泉家遺宅
『江戸時代、石見銀山附御料150余村は支配上六組に分けられていた。18世紀の中頃には、大森には六軒の郷宿(ごうやど)が設けられ、公用で出かける村役人等の指定宿として、また代官所から村方への法令伝達等の御用を請け負っていた。文献から、泉家の主人川北氏は文化7年(1810)まで「波積組(主として現在の江津市の一部)」の郷宿を勤めていたことが知られている。建物は外壁を漆喰で塗籠め、軒瓦には家紋を入れるなど堂々たる風格を備えている。敷地は、寛政12年(1800)の大火を免れた位置にあり、町並みの中で最も古い建物のひとつと考えられる。』








阿部家(島根県指定史跡)、石見銀山地役人遺宅
「阿部氏初代の清兵衛は甲斐国(山梨県)の出身で慶長6年(1601)に初代奉行大久保石見守に銀山附地役人として召抱えられ、子孫は代々銀山支配に携わった。」




栄泉寺
「曹洞宗の寺院で、慶長元年(1596)の開山と伝えられており、禅の修行道場でした。第19代の代官である井戸平左衛門が享保の大飢饉(1732)の際に、ここを訪れた旅の僧「泰永」から飢饉の備えとして薩摩芋のことを教わったところと伝わっています。大森町は寛政の大火(1800)で町の大半が焼失しましたが、栄泉寺も土蔵ひとつ残して焼失しました。現在の本堂は文化4年(1807)に再建されたものです。」


竜宮門
「石段の上に見える山門は、嘉永6年(1853)に画僧であった仏乗禅師が再建したものです。日光の大猷院(家光の廟所)の皇嘉門に姿が似ていることから当時の代官から取り壊しの命令が出されましたが、住職留守を理由にして筵や板で囲い、幕末の混乱に紛れて取り壊されずすんだと伝えています。」




本堂






再び町並みに



三宅家(島根県指定史跡)、石見銀山地役人遺宅
「建物は、代官所の銀山方役所に勤務する銀山附役人田邊氏の居宅であった。」

















柳原家(島根県指定文化財)、石見銀山代官所同心遺宅
「柳原氏は代官所の同心を勤めた武家である。」








旧河島家(島根県指定史跡)、石見銀山地役人遺宅







伝統的建造物群保存地区の説明書

旧大森区裁判所




観世音寺
「岩山の上にあり、江戸時代には大森代官所が銀山の隆盛を祈願するための祈願寺でした。本堂のほか山門と鐘楼が残されています。町並みの大半が焼失した寛政の大火(1800年)により、観世音寺も全ての建物が焼失しました。そのためもとの創建年は不詳ですが、現在の本堂や山門は万延元年(1860)に再建されたものです。」


山門

仁王像



本堂

鐘楼

境内からの町並み



map
案内図

観光案内所

羅漢寺










町並みに進みます。















金森家(島根県指定史跡)、石見銀山御料郷宿泉家遺宅
『江戸時代、石見銀山附御料150余村は支配上六組に分けられていた。18世紀の中頃には、大森には六軒の郷宿(ごうやど)が設けられ、公用で出かける村役人等の指定宿として、また代官所から村方への法令伝達等の御用を請け負っていた。文献から、泉家の主人川北氏は文化7年(1810)まで「波積組(主として現在の江津市の一部)」の郷宿を勤めていたことが知られている。建物は外壁を漆喰で塗籠め、軒瓦には家紋を入れるなど堂々たる風格を備えている。敷地は、寛政12年(1800)の大火を免れた位置にあり、町並みの中で最も古い建物のひとつと考えられる。』








阿部家(島根県指定史跡)、石見銀山地役人遺宅
「阿部氏初代の清兵衛は甲斐国(山梨県)の出身で慶長6年(1601)に初代奉行大久保石見守に銀山附地役人として召抱えられ、子孫は代々銀山支配に携わった。」




栄泉寺
「曹洞宗の寺院で、慶長元年(1596)の開山と伝えられており、禅の修行道場でした。第19代の代官である井戸平左衛門が享保の大飢饉(1732)の際に、ここを訪れた旅の僧「泰永」から飢饉の備えとして薩摩芋のことを教わったところと伝わっています。大森町は寛政の大火(1800)で町の大半が焼失しましたが、栄泉寺も土蔵ひとつ残して焼失しました。現在の本堂は文化4年(1807)に再建されたものです。」


竜宮門
「石段の上に見える山門は、嘉永6年(1853)に画僧であった仏乗禅師が再建したものです。日光の大猷院(家光の廟所)の皇嘉門に姿が似ていることから当時の代官から取り壊しの命令が出されましたが、住職留守を理由にして筵や板で囲い、幕末の混乱に紛れて取り壊されずすんだと伝えています。」




本堂






再び町並みに



三宅家(島根県指定史跡)、石見銀山地役人遺宅
「建物は、代官所の銀山方役所に勤務する銀山附役人田邊氏の居宅であった。」

















柳原家(島根県指定文化財)、石見銀山代官所同心遺宅
「柳原氏は代官所の同心を勤めた武家である。」








旧河島家(島根県指定史跡)、石見銀山地役人遺宅







伝統的建造物群保存地区の説明書

旧大森区裁判所




観世音寺
「岩山の上にあり、江戸時代には大森代官所が銀山の隆盛を祈願するための祈願寺でした。本堂のほか山門と鐘楼が残されています。町並みの大半が焼失した寛政の大火(1800年)により、観世音寺も全ての建物が焼失しました。そのためもとの創建年は不詳ですが、現在の本堂や山門は万延元年(1860)に再建されたものです。」


山門

仁王像



本堂

鐘楼

境内からの町並み