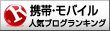ボランティアガイドの説明を聞く参加者(蘭学事始の地)
豊島法人会の健康セミナーの最後は、観光で築地・明石町コースを選んだ。
案内役は東京シティボランティアガイド所属の大塚守さん。
我々第1班は9名であった。
すしざんまい奥の院を出発して最初は築地本願寺。
築地本願寺は京都の西本願寺の別院として建立された。現在の建物は関東大震災で焼失したことにより、昭和9年に古代インド仏教様式で完成したもの。
本堂の上部にはパイプオルガンが設置されている。3メートルから1センチまで大小2000本のパイプ(笛)で構成され、繊細で荘厳な音色を織りなす仏教音楽を奏でる。
築地居留地のはじまりは、安政5年(1858年)、米国総領事ハリスをはじめ、米、蘭、露、英、仏の5ヵ国と江戸幕府の井伊直弼大老との間に結ばれた修好通商条約によって日本の七箇所に外国人居留地を設置することが決まった。江戸築地居留地の設定は明治元年、明治新政府の手によって開設された。
現在の明石町には多くの記念碑が残っている。
シーボルトの胸像、アメリカ公使館跡の記念碑、聖路加看護大学トイスラー記念館、カトリック築地教会、蘭学事始の地、ガス街灯柱、築地居留地跡等々。
また学校の発祥地としても多数の記念碑がある。
慶応義塾発祥の地、立教学院発祥の地、女子学院発祥の地、明治学院発祥の地、双葉学園発祥の地、立教学院発祥の地、女子聖学院発祥の地、指紋研究発祥の地等々。
その他には、浅野内匠頭邸跡、芥川龍之介生誕の地。
江戸から東京へと移り行く中で多くの原点がこの築地や明石町にあったことを再認識した勉強になる観光散策であった。
(11月5日記)
豊島法人会の健康セミナーの最後は、観光で築地・明石町コースを選んだ。
案内役は東京シティボランティアガイド所属の大塚守さん。
我々第1班は9名であった。
すしざんまい奥の院を出発して最初は築地本願寺。
築地本願寺は京都の西本願寺の別院として建立された。現在の建物は関東大震災で焼失したことにより、昭和9年に古代インド仏教様式で完成したもの。
本堂の上部にはパイプオルガンが設置されている。3メートルから1センチまで大小2000本のパイプ(笛)で構成され、繊細で荘厳な音色を織りなす仏教音楽を奏でる。
築地居留地のはじまりは、安政5年(1858年)、米国総領事ハリスをはじめ、米、蘭、露、英、仏の5ヵ国と江戸幕府の井伊直弼大老との間に結ばれた修好通商条約によって日本の七箇所に外国人居留地を設置することが決まった。江戸築地居留地の設定は明治元年、明治新政府の手によって開設された。
現在の明石町には多くの記念碑が残っている。
シーボルトの胸像、アメリカ公使館跡の記念碑、聖路加看護大学トイスラー記念館、カトリック築地教会、蘭学事始の地、ガス街灯柱、築地居留地跡等々。
また学校の発祥地としても多数の記念碑がある。
慶応義塾発祥の地、立教学院発祥の地、女子学院発祥の地、明治学院発祥の地、双葉学園発祥の地、立教学院発祥の地、女子聖学院発祥の地、指紋研究発祥の地等々。
その他には、浅野内匠頭邸跡、芥川龍之介生誕の地。
江戸から東京へと移り行く中で多くの原点がこの築地や明石町にあったことを再認識した勉強になる観光散策であった。
(11月5日記)