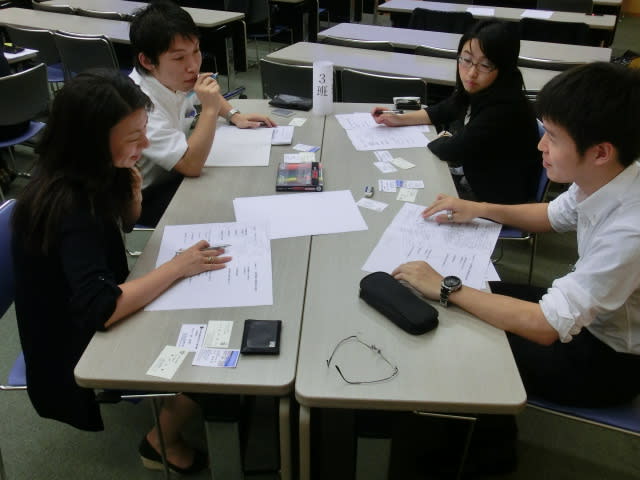授業「メディアと文化(大衆文化論)」の秋学期は、ドラマ研究を行っている。
その中で、履修している2~4年生の学生たちに、アンケートを実施した。
お題は「私のベストドラマ」。
これまでの人生の中で(と言っても20年前後だけど)、「私にとっての、この1本」というドラマを、その理由と共に挙げてもらったのだ。
結果は以下の通りです。
全体としては、かなりバラけて、1票のドラマが大多数でした。
そんな中で、7票とトップだったのが、松嶋菜々子、堤真一の「やまとなでしこ」(フジテレビ、2000年秋)。
へ~、そうなんだあ(笑)。
大学生が選ぶ「私のベストドラマ」
やまとなでしこ(7)
踊る大捜査線(3)
ビューティフルライフ(3)
花より男子(2)
銭ゲバ(2)
流星の絆(2)
篤姫(2)
ウオーターボーイズ(2)
僕の生きる道(2)
池袋ウエストゲートパーク(2)
美女か野獣(2)
有閑倶楽部(2)
結婚できない男(2)
ごくせん(2)
リッチマン・プアウーマン(2)
ラストフレンズ(2)
時効警察(2)
相棒(2)
新撰組(2)
お金がない
タイガー&ドラゴン
木更津キャッツアイ
ナースのお仕事
みにくいアヒルの子
ブレイキングバッド
14歳の母
君といた未来のために
GOOD LUCK!
流転の王妃と最後の皇弟
マイボス・マイヒーロー
愛という名のもとに
ホ・ジュン
恋のチカラ
龍馬伝
JIN―仁―
野ブタ。をプロデュース
ガラスの仮面
アテンションプリーズ
ライアーゲーム
ROOKIES
BOSS
SP
蒼穹の昴
女王の教室
恋のチカラ
フルハウス
荒川アンダーザブリッジ
マンハッタンラブストーリー
春のワルツ
Mother
それでも生きていく
鹿男あおによし
プロポーズ大作戦
奥様は魔女
天才柳沢教授の生活
SPEC
HEROS
未成年
3年B組金八先生
妻の幸せ時代 中国
救命病棟24時
TRICK
ボーイズオンラン
官僚たちの夏
1リットルの涙
ユウキ
ヴォイス~命なき者の声
バツ彼
家政婦のミタ
世界の中心で愛を叫ぶ
明日の光をつかめ
やまとなでしこ(7)
踊る大捜査線(3)
ビューティフルライフ(3)
花より男子(2)
銭ゲバ(2)
流星の絆(2)
篤姫(2)
ウオーターボーイズ(2)
僕の生きる道(2)
池袋ウエストゲートパーク(2)
美女か野獣(2)
有閑倶楽部(2)
結婚できない男(2)
ごくせん(2)
リッチマン・プアウーマン(2)
ラストフレンズ(2)
時効警察(2)
相棒(2)
新撰組(2)
お金がない
タイガー&ドラゴン
木更津キャッツアイ
ナースのお仕事
みにくいアヒルの子
ブレイキングバッド
14歳の母
君といた未来のために
GOOD LUCK!
流転の王妃と最後の皇弟
マイボス・マイヒーロー
愛という名のもとに
ホ・ジュン
恋のチカラ
龍馬伝
JIN―仁―
野ブタ。をプロデュース
ガラスの仮面
アテンションプリーズ
ライアーゲーム
ROOKIES
BOSS
SP
蒼穹の昴
女王の教室
恋のチカラ
フルハウス
荒川アンダーザブリッジ
マンハッタンラブストーリー
春のワルツ
Mother
それでも生きていく
鹿男あおによし
プロポーズ大作戦
奥様は魔女
天才柳沢教授の生活
SPEC
HEROS
未成年
3年B組金八先生
妻の幸せ時代 中国
救命病棟24時
TRICK
ボーイズオンラン
官僚たちの夏
1リットルの涙
ユウキ
ヴォイス~命なき者の声
バツ彼
家政婦のミタ
世界の中心で愛を叫ぶ
明日の光をつかめ