起訴されてから判決が下るまで
①被告人に、弁護人が必要な場合は弁護人を付ける
弁護人が必要なのは、一定以上の重い容疑の場合。(必要的弁護事件)
死刑、無期懲役はもちろん、上限が懲役または禁固3年以上の刑となっている事件。
それより軽いものは弁護人なしでも裁判できる
②弁護人の選定<私選と国選>
・私選が原則だが、被告人が貧困、未成年、老齢のときには国選で弁護人をつけることができる
(被告人国選弁護)
・①で示した、「軽いもの」に入る事件で、かつ国選弁護人をつけたいときは、「資力申告書」を
提出しなくてはいけない
※被疑者国際弁護
逮捕されて起訴するまでの間、つまり容疑者が「被疑者」の段階でも、(私選はもちろん)
一定以上の重い容疑の場合には国選弁護人をつけることができる(2006年から)。
そのラインは、「死刑、無期、懲役または禁固が最短で1年」。
このラインが2009年、裁判員制度導入時から「死刑、無期、懲役または禁固が上限3年以上」になる。
=必要的弁護事件の場合、すべてに被疑者段階から国選弁護人がつけられる
これにより、どんどんと「被疑者の権利主張」は強くなっていくだろう。
たとえば、勾留理由開示請求とか?否認事件も増えそう。
マスコミにとっては、「容疑者の言い分」により耳を傾けざるをえなくなってくるだろうと
思われます、いいのか悪いのかは別として、ね。
③公判準備手続き
④冒頭手続き
・人定質問(裁判官が被告人に、名前、住所、職業などを尋ねる)
・起訴状の朗読(by検察官)
・黙秘権の告知(by裁判官)
・罪状認否(by裁判官、被告人が「認めます」「起訴状のこことここは違います」などと述べる)
⑤証拠調べ手続き
・検察官が冒頭陳述・・・検察側が、証拠によってどんな事実を明らかにしようとしているのかを
具体的に述べる
・弁護人の冒頭陳述(ない場合も)
・証拠調べの請求・・・検察が、供述書や、犯行時の写真など、捜査資料の一部などを、
(by検察官) 明らかにしようとしている事実にとって証拠となるものを「証拠としてください」
と裁判所に申請、裁判所が採用したり、却下したりする
(by弁護人)
・証拠調べ・・・「証拠方法」と「証拠資料」がある。証拠方法には、物証と人証があり、それぞれ
押収した物とか、証人や被告人の尋問によって得る証拠。
証拠資料には、供述証拠、非供述証拠(指紋とか)がある
⑥最終手続き
・論告・・・検察が、主張や証拠調べの結果をふまえ、適応すべき法律などを述べながら
「・・・相当に厳重な処罰が必要と考えます」などと言う
・求刑・・・「よって被告人を、懲役何年に処するのが相当です」などと、量刑を述べる
・最終弁論・・・弁護側も、同様に弁護側が考える事実、諸事情(情状)をのべ、
減刑や、ときには無罪を訴える
・被告人の最終陳述・・・言いたいことがあれば、被告人当人も最後に話す
(これらが終わることを「結審する」という)
⑦判決
ところで昨日の毎日新聞の一面(三重で)。
第一印象は、刑務所の管理費削減?と思いましたが、賛否はよくわかりません。
とりあえず、拘置所、刑務所はあふれんばかりの満杯状態という実情はあるみたいです。
刑法改正:懲役・禁固に新制度 社会で更正
犯罪者を刑務所内でなく社会の中で更生させるため、法務省は、懲役・禁固刑の一部を一般社会での更生期間とする新たな制度「刑の一部の執行猶予制度」を導入する方針を固めた。現在の実刑と執行猶予の中間に位置づける。来年に法相の諮問機関の法制審議会で結論を出し、早ければ2010年にも刑法改正案を国会に提出する。【石川淳一】
同省などによると、現在の執行猶予は、刑の執行を一定期間猶予し、期間内に新たな犯罪行為を起こさなければ、実刑を科さない。これに対し、新制度は、実刑と執行猶予を組み合わせる形で導入する。懲役または禁固の実刑を科した後に、残りの刑を猶予して、その猶予期間中は、保護観察所で処遇プログラムを受けるなどして社会で更生を図る。プログラムの内容は、再犯防止に向けた座学などが検討されている。刑務所などで一定期間の改善更生を図った上でその効果を社会でも持続させる狙いがある。
判決言い渡しは、懲役・禁固期間と保護観察下の猶予期間を合わせた量刑になる見通し。刑務所に入る期間は減るが、必ず刑務所に入ることになる。現在の執行猶予は別に残す方針。
この新制度の対象者は、主にこれまで刑務所に入ったことのない人を想定。道路交通法違反や覚せい剤取締法違反を重ねて初めて実刑となったり、執行猶予中の再犯で執行猶予を取り消された人のほか、実刑と執行猶予の境界線上の罪を犯した人も検討されている。
刑務所に多くの実刑確定者が入る過剰収容対策を話し合ってきた法制審が、「刑務所での処遇と社会生活がかけ離れている」と指摘したことから、法務省は、刑務所と社会生活との中間的な処遇方法を検討していた。
一方、法制審はこの制度とは別に街頭清掃や介護などのボランティア作業を保護観察に取り入れる「社会奉仕命令」を導入することも検討している。
◇ことば 懲役と禁固
いずれも刑務所に拘置し自由をはく奪するため自由刑と呼ばれる。懲役(刑法12条)は労役に服することを義務づけられるが、禁固(同13条)には労役がない。禁固の適用は交通事故などの過失犯などに限定。いずれも有期なら1月以上20年以下(複数の罪を併科されると最長30年)で無期もある。
①被告人に、弁護人が必要な場合は弁護人を付ける
弁護人が必要なのは、一定以上の重い容疑の場合。(必要的弁護事件)
死刑、無期懲役はもちろん、上限が懲役または禁固3年以上の刑となっている事件。
それより軽いものは弁護人なしでも裁判できる
②弁護人の選定<私選と国選>
・私選が原則だが、被告人が貧困、未成年、老齢のときには国選で弁護人をつけることができる
(被告人国選弁護)
・①で示した、「軽いもの」に入る事件で、かつ国選弁護人をつけたいときは、「資力申告書」を
提出しなくてはいけない
※被疑者国際弁護
逮捕されて起訴するまでの間、つまり容疑者が「被疑者」の段階でも、(私選はもちろん)
一定以上の重い容疑の場合には国選弁護人をつけることができる(2006年から)。
そのラインは、「死刑、無期、懲役または禁固が最短で1年」。
このラインが2009年、裁判員制度導入時から「死刑、無期、懲役または禁固が上限3年以上」になる。
=必要的弁護事件の場合、すべてに被疑者段階から国選弁護人がつけられる
これにより、どんどんと「被疑者の権利主張」は強くなっていくだろう。
たとえば、勾留理由開示請求とか?否認事件も増えそう。
マスコミにとっては、「容疑者の言い分」により耳を傾けざるをえなくなってくるだろうと
思われます、いいのか悪いのかは別として、ね。
③公判準備手続き
④冒頭手続き
・人定質問(裁判官が被告人に、名前、住所、職業などを尋ねる)
・起訴状の朗読(by検察官)
・黙秘権の告知(by裁判官)
・罪状認否(by裁判官、被告人が「認めます」「起訴状のこことここは違います」などと述べる)
⑤証拠調べ手続き
・検察官が冒頭陳述・・・検察側が、証拠によってどんな事実を明らかにしようとしているのかを
具体的に述べる
・弁護人の冒頭陳述(ない場合も)
・証拠調べの請求・・・検察が、供述書や、犯行時の写真など、捜査資料の一部などを、
(by検察官) 明らかにしようとしている事実にとって証拠となるものを「証拠としてください」
と裁判所に申請、裁判所が採用したり、却下したりする
(by弁護人)
・証拠調べ・・・「証拠方法」と「証拠資料」がある。証拠方法には、物証と人証があり、それぞれ
押収した物とか、証人や被告人の尋問によって得る証拠。
証拠資料には、供述証拠、非供述証拠(指紋とか)がある
⑥最終手続き
・論告・・・検察が、主張や証拠調べの結果をふまえ、適応すべき法律などを述べながら
「・・・相当に厳重な処罰が必要と考えます」などと言う
・求刑・・・「よって被告人を、懲役何年に処するのが相当です」などと、量刑を述べる
・最終弁論・・・弁護側も、同様に弁護側が考える事実、諸事情(情状)をのべ、
減刑や、ときには無罪を訴える
・被告人の最終陳述・・・言いたいことがあれば、被告人当人も最後に話す
(これらが終わることを「結審する」という)
⑦判決
ところで昨日の毎日新聞の一面(三重で)。
第一印象は、刑務所の管理費削減?と思いましたが、賛否はよくわかりません。
とりあえず、拘置所、刑務所はあふれんばかりの満杯状態という実情はあるみたいです。
刑法改正:懲役・禁固に新制度 社会で更正
犯罪者を刑務所内でなく社会の中で更生させるため、法務省は、懲役・禁固刑の一部を一般社会での更生期間とする新たな制度「刑の一部の執行猶予制度」を導入する方針を固めた。現在の実刑と執行猶予の中間に位置づける。来年に法相の諮問機関の法制審議会で結論を出し、早ければ2010年にも刑法改正案を国会に提出する。【石川淳一】
同省などによると、現在の執行猶予は、刑の執行を一定期間猶予し、期間内に新たな犯罪行為を起こさなければ、実刑を科さない。これに対し、新制度は、実刑と執行猶予を組み合わせる形で導入する。懲役または禁固の実刑を科した後に、残りの刑を猶予して、その猶予期間中は、保護観察所で処遇プログラムを受けるなどして社会で更生を図る。プログラムの内容は、再犯防止に向けた座学などが検討されている。刑務所などで一定期間の改善更生を図った上でその効果を社会でも持続させる狙いがある。
判決言い渡しは、懲役・禁固期間と保護観察下の猶予期間を合わせた量刑になる見通し。刑務所に入る期間は減るが、必ず刑務所に入ることになる。現在の執行猶予は別に残す方針。
この新制度の対象者は、主にこれまで刑務所に入ったことのない人を想定。道路交通法違反や覚せい剤取締法違反を重ねて初めて実刑となったり、執行猶予中の再犯で執行猶予を取り消された人のほか、実刑と執行猶予の境界線上の罪を犯した人も検討されている。
刑務所に多くの実刑確定者が入る過剰収容対策を話し合ってきた法制審が、「刑務所での処遇と社会生活がかけ離れている」と指摘したことから、法務省は、刑務所と社会生活との中間的な処遇方法を検討していた。
一方、法制審はこの制度とは別に街頭清掃や介護などのボランティア作業を保護観察に取り入れる「社会奉仕命令」を導入することも検討している。
◇ことば 懲役と禁固
いずれも刑務所に拘置し自由をはく奪するため自由刑と呼ばれる。懲役(刑法12条)は労役に服することを義務づけられるが、禁固(同13条)には労役がない。禁固の適用は交通事故などの過失犯などに限定。いずれも有期なら1月以上20年以下(複数の罪を併科されると最長30年)で無期もある。
















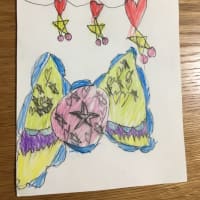


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます