「法」という開かれた門の前に番人が立っていて、男はその前で、番人に尋ねる。
「入れてくれないか」
「今はだめだ、後でならいいが」
その門の前で待つうちに、男はすっかり老いてしまう。そして死ぬ間際に知る。
その門は男のためだけにあったのだということを。
映画の導入で紹介される話。
原作の小説を書いたカフカが何を言わんとしていたのか、それを
理解したかは大いに疑問だが、彼がこのストーリーで言っていたことは
「人が人を裁くことのばかばかしさ」だろうか。
ある日突然、銀行員の男、ジョゼフは逮捕され、審判を受けることになる。
検察官は罪名を言わず、なぶり殺しにされるようにジョゼフは弁護士や傍聴人、裁判官や
裁判官だけを書くという肖像画家の元を訪れる。
しかし、勤務先である銀行--常にタイプライターをたたく音しか聞こえない、
広大なフロアに机と人が並べられた場所--を含めて、すべての場所が気づけばなぜか、
裁判所と隣接している。そして・・・人々も、裁判所とつながっている。
「この世界から抜け出すことが、今はもう無意味に思える」
そんな境地に陥って、ジョゼフは最後を迎える。
そのラストシーンが強烈に印象的だ。
2人の男に両腕をつかまれ、荒廃した土地の穴に陥れられる。
そこでジョゼフは、何も言われないのに服を脱ぎ始める、、これは最大の降伏行為だと思う。
それを上から見ていた2人の男は下に降りてきて、ジョゼフを寝かせ、その目上で
ナイフを交互に渡しあう・・・どっちが、どうやるか。どっちの男が取ったとしても、
ジョゼフはそのナイフで殺される・・・弁護人が話そうが、検察官が話そうか、
結論は決まっている、と言いたいかのように。
そのあげく何もせずに穴から出て行ってしまった男らにジョゼフは、
ついに「俺を殺せ、早く刺せ!」と自ら叫んでしまうのだ。
最後には、2人の男に放り投げられたダイナマイトで死ぬ。
罪を発見し、立証し、裁く。
そんなことは、不可能だし無意味だし、それを行うべき組織はあまりにも
乾燥しきっていて、ベルトコンベアのように結果を用意する。
そんなことを表していたのか、、な、自信はないが。
・・・
話はそれるが、最近「刑罰は何のためにあるのか」と考える。
罪を償わせ、被害者感情をなだめるため?
「罪を犯せばこんなひどい目に遭う、だからするなよ」という見せしめ?(再発防止?)
犯罪者当人を更正させるため?
つまり、「応酬刑」という性格なのか「教育刑」ということなのか。
応酬刑なら、死刑は最もということになるし、12月から始まった「被害者参加制度」は肯定できる。
「あなたの罪はこんなにひどいんだ、だからもっともっと重罰を与えるべきだ」
教育刑なら、死刑は論理的におかしい。死なせては本人の更正の余地はない。
「どっちの要素もある、でも本来、応酬刑と考えるべきだろうね。
法律によって罰するというのは、復讐の連鎖が起こらないように、
公的機関が被害者に変わって罰するというところから出来たものだろうし。」
というある警察官。そうか、なるほど。終身刑という刑だって、応酬刑を前提としないと通らない。
そんなわけで、仕事に戻ります。思考を途中放棄。
















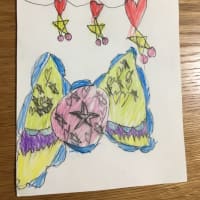


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます