注目とした1日のNY株式はダウが引け間際の30分間に200ドル買い上げられ結局プラス圏に。M&Aやその他リスク投資の原資の蛇口は閉められたものの、完全に止まったわけではなく、この上半期(1-6月期)の状況が異常だったとすると、その異常値を基準に見れば流動性は低下したものの、通常の姿に戻りつつあるということ。足元の好業績を素直に好感するなら買える銘柄もあるということだろう。とりわけ多国籍企業の塊であるダウ指数はそういうこと。そちらが落ち着けば「波及リスク」で売られて・・・あるいは「波及リスク」を恐れた売りものに値を消したドル建て金価格も戻り符丁に。むしろ強制手仕舞いということになったので、買われ過ぎを示していた内部要因は一気に整理が進んだ模様。英紙フィナンシャル・タイムスが財政赤字削減を目的にイタリアが保有金の売却を検討との記事を流していたが、おそらく中銀サイドは反対するのではないだろうか。もっとも来年以降の話なので足元の市況への影響は小さい、それよりワシントン協定の500トン枠が今年は埋まりそうという見方の方が相場には影響がある。
さてこの1週間の乱高下ドサクサの中で、NY上場の金ETF「street TRACKs Gold Shares」の残が1日で10トン超増えた。このところロンドンもヨハネスもシドニーも増えているので残は静かに過去最高を更新。下げ局面を買い向かったということ。誰が見てもマイナスの材料ではあるまい。そういえば原油が過去最高値と騒がれているが問題はこの上を誰が買うのかということ。
さてこの1週間の乱高下ドサクサの中で、NY上場の金ETF「street TRACKs Gold Shares」の残が1日で10トン超増えた。このところロンドンもヨハネスもシドニーも増えているので残は静かに過去最高を更新。下げ局面を買い向かったということ。誰が見てもマイナスの材料ではあるまい。そういえば原油が過去最高値と騒がれているが問題はこの上を誰が買うのかということ。



















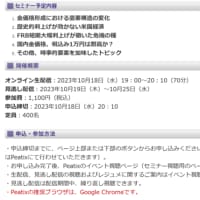






日経ネットに気になるニュースが二つ。
○欧州中銀のトルシェ総裁が、最近のインフレに対抗するため、9月にも再度の利上げをする見解を示したそうです。
○ドイツの中堅銀行がサブプライム投資に失敗して1兆3千億円相当の損失を出し、政府系金融機関が支援に乗り出したそうです。
日本の1990年代初頭とどこか似ていませんか。
いずれにせよ為替の乱高下の原因の一つと思われます。
コメントによっては、現在の金融市場を売春宿呼ばわりするところもあります。実際、去年まで誰も聞いたことがないサブプライムなる存在もこれほど大きな影響を与えるとは思いもよらなかったと思います。マクロモメンタムを感じていたので、調整なき上昇に多少気をかけていたので事なきを得ました。しかし、今日の中国市場は強かった。あまりの超強気に最後の買い手となる意志を感じます。中国が世界を支えるか?彼らの金融に対するテクニックが問われるかもしれないと思っています。ただ、シンガポールなどは中国を捨て石にしていないかと気がかりですが・・・