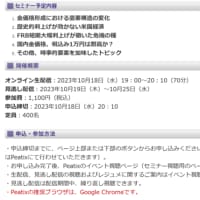先週末金曜日のNY金は反落で下げ幅も18.70ドルとやや大きくなった。引値は1783.90ドルだった。発表された米経済指標を受けて、利上げ前倒し観測が再び強まったことから、長期金利が上昇、つれてドルも対ユーロを中心に上昇しドル指数(DXY)が強含みに推移、金は売られた。。先週は連日取引時間中に1800ドルを越えたものの終値ベースで維持できたのは2営業日のみ、心理的節目の1800ドルがテクニカル面で改めて抵抗ライン(レジスタンス)となっていることを印象付けた。一連の動きがファンド主導であることも示している。
29日の下げ幅がやや大きくなったのは、米商務省が発表した9月の個人消費支出が前月比0.6%増と、市場予想の0.5%増を上回ったこと。8月の消費支出も当初発表の0.8%増から1.0%増に上方改定され、消費支出が底堅く推移していることが示されたことがある。結果を受けて、米10年債利回りが一時1.623%まで急騰したことが金売りのきっかけとなった。さらに月末の利益確定売りも重なったと思われる。ちなみに、米債市場では押し目買いが入り終盤に利回りは急低下し結局1.560%で終了と、こちらも変動幅は大きくなった。
この日の米商務省発表のもう一つの注目データ、9月の個人消費支出(PCE)価格指数は前月比0.3%、前年同期比4.4%上昇となった。米連邦準備理事会(FRB)が物価の目安としている変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数は前年同月比で4カ月連続で3.6%の上昇となった。さらに同じ日に米労働省が発表した7~9月四半期の雇用コスト指数(ECI)は前期比で1.3%上がり、2001年以降で最大の上昇率となった。賃金インフレの高まりを思わせるデータといえる。
これらの指標は現時点でFRBが想定していた水準を超えるインフレが続いていることを示し、インレフ高進はコロナ禍からの回復過程での「一時的なもの」とするFRBに、政策上の忍耐を強いるもの。一方で、FRBは早晩インフレ抑制に向け積極的な政策措置(利上げ)を実施するとの市場の見方を裏付けるものとなる。
今週のFOMCにてテーパリングが決まり、早ければ今月中旬から着手。さらに来年半ばに買い付けが終了した後の利上げ時期を早めるとの解釈が、市場で増えている。つまり想定を超える持続的なインフレ高進によりインフレに強い金が買われるのではなく、インフレ抑制に向けFRBが取る積極的な利上げ策が、金価格の売り要因になるとの判断が市場で優勢になっている。その見方が金の上値を抑えている。
ただし、インフレ抑制に向けFRBのタカ派的スタンスが強まることは、株式市場にとっても悪材料となり市場が不安定化するリスクがある。いわば諸刃の剣となるもので、(株価暴落など)不安定の度合いによっては、金の買い材料(安全資産としての金)となる。そのあたりが、いつものように前のめりに政策方向を織り込もうとする市場とFRB間の温度差の違いとして浮上し、時に金価格の上下動の大きさにつながる。