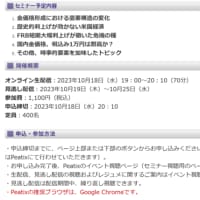本日のNY金は、NY時間外のアジア午後、さらにロンドン時間を通して断続的に売り優勢の流れとなっている。
この3週間ほどで46トンの売り越しから330トンの買い越しまでロングのポジションを膨らませたファンドの投げが下げをもたらしていると見られる。
週明け6日のNY市場は、終盤に持ち直したもののドルが一時対ユーロで約8週間ぶりの安値まで下落した。この動きにドル指数(DXY)は一時、9月20日以来の安値となる104.848まで下落し、終盤は105.2前後まで戻した。一方、米長期債利回りは上昇した。指標となる10年債利回りは11月3日には一時4.481%と9月25日以来の低水準を付けていた。週明けは複数の国債入札を控え、需給悪化懸念も相場の重荷だった。利益確定売りが利回りを押し上げ4.649%で終了。
ドル指数の下げはNY金のサポート要因だが、米長期金利の上昇を手掛かりに買い残の重荷に耐えかねるようにNY金は低下ということになった。
その流れが7日の市場で続いている。ファンドのプログラムなので、米長期金利上昇でもドル高でも、ゴールドにとってネガティブな材料には何にでも反応する状況にある。膨らみ過ぎた買いの調整局面という流れ。1950ドルの節目を試す動きになっても不思議はないと思われる。
今週は米国関連で主要統計の発表はなく、本日以降米地区連銀総裁の発言が多く予定されており、その内容が注目される。特に9日(木)にはパウエル議長の講演が予定されている。
あと注目されているのは週内に実施される入札総額3230億ドル(約48兆円)に上る米国債の入札。十分な引き合いがあり、利回りを押し上げないかが注目されている。6日は1430億ドルの3カ月物と6カ月物の財務省証券の入札を実施し、いずれも堅調な需要がみられた。短期物は銀行預金などより条件のいいMMFなどからの引き合いも強く、もともと消化に問題はない。本日は3年債(480億ドル)、8日に10年債(400億ドル)、9日に30年債(240億ドル)の入札を実施する。10年債、30年債の入札結果がポイントに。
いずれにしても、NY金にとっては、このところ積み増されたフレッシュロングの“投げ”がどこで一巡するか、仕切り直しのような、(材料面で)空白の週になりそうだ。