天狗も人に騙され、ふんだりけったりの存在。
<天狗の隠れ蓑編>
・天狗の隠れ蓑(定本日本の民話12 佐渡の民話/浜口一夫編/未来社/1999年初版)
外国の昔話にはみられない天狗。中国の昔話には出てきてもおかしくなさそうだが、あまりお目にかからない。もっとも中国の昔話といっても日本で読むことのできるものは、ごくごく少数ということがあるのかも知れない。
天狗がもつという隠れ蓑。この隠れ蓑をうまく手に入れるというのも、いろいろなものがあるが、佐渡版では盛りだくさんの要素が入っていて、落語にあっても(もしかしたらあるかも・・・)もおかしくない。
男が天狗の隠れ蓑をうまく手に入れるが、あとで押しかけられるのを見越して、何がこわいか話し合う、男はまんじゅうがこわいという。
男がいう遠眼鏡がインチキだったのに はらをたてた天狗が、男を怖がらせようと家にまんじゅうを投げ込む。まんじゅうをはら一杯食べた男が、死んだふりをすると、それをみた天狗は山にかえっていく。
佐渡版は、ここで終わらない。
隠れ蓑をきて、酒屋の酒蔵に潜り込んで、たらふく酒を飲んだ男は、ねむくなって横になる。その拍子に隠れ笠が頭からすっぽりはずれる。酒屋の小僧が酒蔵にはいってみると、酒樽のそばには、赤ら顔の生首がごろり。
おどろいた酒屋のおやじが、生首を始末したものに、5両だすというが、誰もこわがって手をだそうとしない。
男がこの話を聞いていて、5両だしてくれると一人ででていくというと、おやじが5両を投げ出す。男はそのお金をもって酒蔵をでていくという結末。
伝承者の方が、複数の話を、うまく組み合わせたものでしょうか。
・てんぐのかくれみの(岐阜のむかし話/岐阜県児童文学研究会編/日本標準/1978年)
どえらい酒飲みが、天狗のうちわと隠れ蓑を手に入れ、ただ酒をのむが、おかあが、蓑を燃やしてしまう。男が灰を体に塗ったら体が隠れ、また酒を飲み放題。ところが寝小便で体が現れ、追い回されるはめに。
男が天狗をだますセリフ。男の本性?
「うわ、こりゃきれいなむすめがみえる」「江戸城にゃそりゃあ どえらいべっぴんな女子しゅがおおぜいいる」
うちわは千里をいっきにとべるので、あっというまに 天狗から逃げてしまう。
・足の化けもの(長野のむかし話/長野県国語教育学会編/日本標準/1976年)
むかし、遊んでばかりいた男が、近くの神社の庭で竹筒をみながらサイコロをころがし、大坂が見える、京も見えるとほらをふいて、天狗の隠し蓑と隠れ傘を手に入れます。天狗がサイコロや竹筒をのぞいても何も見えないので男のところへいくと、男は天狗の一番きらいなサイカチのやぶの中にいるのでちかずけません。
男が隠し蓑と隠れ傘をつけると姿がみえなくなるので大喜び。男は隠し蓑と隠れ傘をタンスの中にしまい、こっそり出しちゃ ニタニタ笑って喜んでいましたが、男が遊びにいったとき、かかあが、きたないからと隠し蓑と隠れ傘を燃やしてしまいます。
帰ってきた男が、泣きべそをかいて、灰をかき集めると、不思議なことに灰がついたところが、見えなくなってしまいます。「こりゃ、たまげた。おもしれえな」と、体中に灰をぬってみると、男が見えなくなってしまいます。男は、体が見えないことをいいことに酒屋で酒を飲んだり、飯屋でごちそうを食ったりとやり放題。
家に帰る途中、道端でしょんべんして、酒蔵に入り込んで、眠ってしまいます。
酒屋の小僧さんが、酒をだそうとやってくると、酒樽のうえで足の化け物がいびきをかいて寝ているのでびっくり。みんなが大声でわめきちらします。
しょんべんしたとき、足のあたりにひっかけて足が見えていたのです。
酒屋では、足の化け物がつかまらなく、大騒ぎ。そこへ男のかかあが、人払いし男を逃がします。化け物が消えてよろこんだ酒屋は、かかあに お礼に しこたま銭をやります。
姿が見えなくなったら、やり放題かと思うと、男はやや控え目。この事件以降、男がよく働くようになったという最後は、語り手のねがいでしょうか。
<てんぐのうちわ編>
・てんぐのうちわ(奈良のむかし話/奈良のむかし話研究会/日本標準/1977年)
一人の男がサイコロを転がしながら「こりゃ、面白いわい、京都が見える。大阪が見える」と、独り言を言っていると、高い岩の上にいた天狗が、男のところに近づいてきて、団扇を取り出し、サイコロとかえようといいます。男が天狗に、何が一番恐ろしいかと聞くと、タラの木が一番怖いといい、逆に天狗が、男の怖いものは、と聞くと、男は「あんころもち」と答えます。
天狗はすぐにだまされたことに気がつきますが、男はタラの木の林に入り込んでかくれてしまいます。天狗は、男が怖いというあんころもちを どんどん投げ込みますが、男はよろこんでもちをとって食べます。天狗は、地団太ふんで残念がりますが、とうとうあきらめてどこかへいってしまいます。
男は、あまいおもちをどっさり食べたので、のどが渇きます。そこで天狗にもらった団扇をあおぎながら「水をくれ、水をくれ」というと、目の前に、お茶碗一杯の水がでてきました。つぎに「お金出ろ、お金出ろ」というと、こんどはザラザラお金が出てきます。
うれしくなった男は、女の人の鼻をのばしたりして、喜んでいました。自分の鼻でためしてみると、鼻はみるみるうちに高くなっていきます。調子に乗って天狗の団扇をあおぎつづけると、雲をとおりこし、天までのびてしまいます。天上では神さまが橋を架けていて、そこへ、へんなものがにょきにょきのびあがってきたので、橋げたにその鼻を打ち付けました。急に鼻の先がいとうなったので、男はびっくりぎょうてん。
「おれの鼻、低くなれ、低くなれ」と、いっしょうけんめい、団扇をあおぐと、鼻が短くなるにつれて、からだが、すこしづつ上へ上へとあがっていきます。男が「助けてくれ!助けてくれ!」と、大声で悲鳴をあげると、天上の神さまたちは、「切り落とせ!」と、鼻の真ん中を刃物で打ち切ったので、男は、天からまっさかさまに落ちて、とうとう死んでしまいます。
この男、天狗の団扇を、人を騙すのに使わないのが救い。自業自得の結末。
・生き針・死に針(茨城のむかし話/茨城民俗学会編/日本標準/1975年)
タイトルだけは想像できませんが、天狗の団扇を手に入れ、団扇をかえすかわりに生き針と死に針を手に入れた男の話。
病人に生き針を打ってやって病人を助けていた三郎のところへ婿話が持ち込まれます。三郎は笑っていて聞こうともしませんでしたが、なんどもなんども頼まれて、二軒のうちへ婿になることに。さいわいなことに二軒は庭続きなので、二階の屋根から屋根へ、梯子をかけて行ったり来たりしていました。ところが、ある朝、三郎は、梯子を渡ろうとして、ねぼけて 梯子を踏み外して・・・。
この話には前段があります。
三郎は三人兄弟の末っ子。元旦の夜、初夢を見たら、その夢の話をすることを約束した兄弟。上の二人は、初夢を話しますが、三郎はだまって話そうともしません。約束が違うと、三郎は、村はずれにあるお宮の一番太い松の木に縛られてしまいます。そこに天狗があらわれます。
しばれていた縄をといてもらいながら、天狗のすきをみて団扇をとってしまった三郎は、生き針と死に針とひきかえに、団扇を天狗にかえします。
死に針の出番があってもおかしくありませんが、使われる場面はありません。そして夢の話にふさわしい結末です。














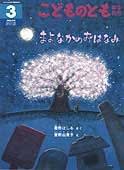

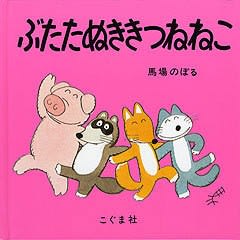




 陽光桜の実
陽光桜の実





