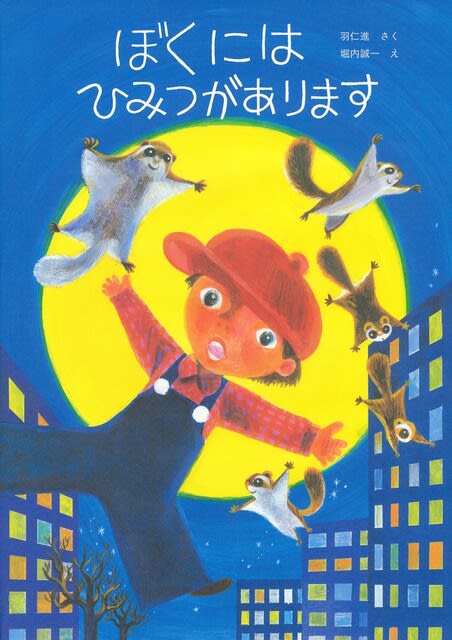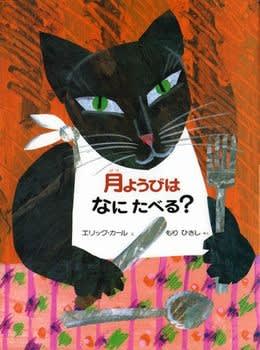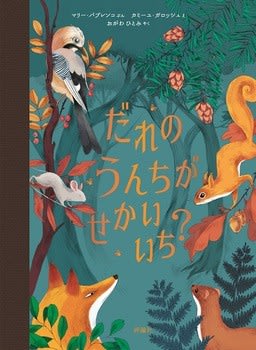ふしぎな はな/脚本・絵 藤田勝治/童心社/2009年
ジャワの月下美人にまつわる花の話。
むかしジャワ島の王さまは、優しい王さまでしたが、国が栄えるにしたがって 横暴になりました。
大臣たちが、キアイというえらい坊さまに相談すると、キアイはさっそく お城にやってきて王さまを戒めます。
王さまは、生意気な坊さまを懲らしめようと、おおぜいの兵隊とキアイを取り囲みますが、海からあらわれた龍が暴れまわり、「じぶんは、すべてが 思い通りになるとおもっていたが、それは まちがっていた」ことを 思い知らされます。
風がおさまり、龍は消え、何事もなかったような、キアイの 姿が ありました。王さまはキアイに、「わたしは いままで、ひどく 威張っていました。でも、本当は なんて ちっぽけで 弱いのでしょう。いったい どうすれば よいのでしょうか」と相談すると、「向こうに見える島に、真夜中 ほんのいっときしか 咲かない花がります。その花を持ち帰ることができるなら 王さまのこたえは 見つかるでしょう」といわれ、小舟で、その島をめざします。
ふしぎなことに、いくらこいでも なかなかちかずくことができず、幾日も幾日も舟をこぎすすめ、やっと島にたどりつきました。そこには、魔物がいて 王さまを 口々に ののしりました。それでも くじけずにすすんでいきますが、花は見つかりません。暑い陽に照らされ、大雨にあい、風に たたきつけられながら歩きますが、やはり花はみつかりません。ついに、王さまは動けなくなりますが、そのとき、かぐわしい香りが ただよいはじめ、光の中に、女神があらわれ、花を 手にすることができました。
「わたしは 民のための王に なろう」と誓った王さまは、その後、だれからも慕われるようになり、国も栄えたという。
表紙は壁画風、龍や女神も独特の絵で、すんなりはいっていけるか心配なところもありました。立派な王さまになるためには たいへんな 試練がまっているというのが、後半にでてきます。