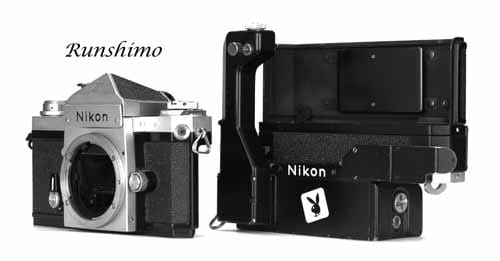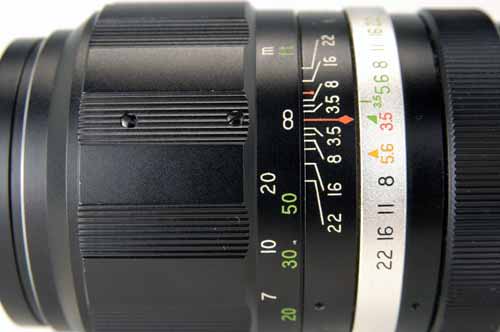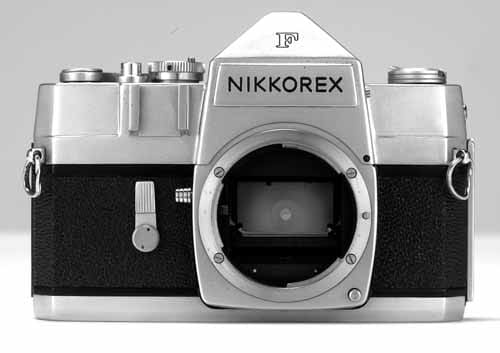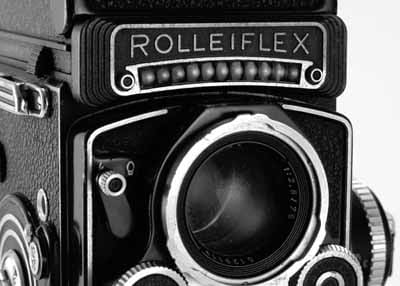つちのこカメラ16②
Nikon F MD の追加記事です。使い方や機構を詳しく解説しました。
NikonFを語る記事は多いけど、FのMD付はあまり見かけません。プロカメラマンが実際に使っていたのはMDをつけていたから、これ抜きにはFの全貌は語れません。
モータードライブが珍しかったころです。
Fの時代のカメラは角ばったものが多かった。その中でもFは特別にカクカクだった。
手にもつと指が痛くなるくらい角ばっていた。
MDのグリップに指が挟まって痛いぐらいだ。よく怪我しなかったものです。
端正な姿ですが、MD付はメカニカルを前面に出していた。
ビスなど当たり前に表面に出ていた。
上がFの本体で、真ん中下のパーツがMD本体。下にあるグリップと一体なのだが、その部分は単三電池のケースです。
直結バッテリーケースと言っていた。
バッテリー別体ケースも確か製品としてあった。 ただ別体ケースはコードでカメラ本体を結ばなきゃいけないので、一般的とは言いがたい仕様でその方が初期の設計なのだろう。
ビスやらリベットが表面にあって、実に今見ると原始的なマシンです。
これが、40年前、エッポメイキングな、時代の先端を行ったカメラ。
シャッターボタンや切り替えスイッチ、コンセントなど、、、家電のパーツじゃないの!
マイクロスイッチがMDには2個使われていた。
直結バッテリーはMD本体にいろんなパーツを介して電気を供給している。
直結バッテリーと言うことは、コードで連結するバッテリーもありました。
それはポケットにでも入れるのかな?
サイドにある白いスイッチは、Cがシャッターの連続でSが一枚切りの切り替え。
一番下にあるコンセントは結線するとシャッターが落ちます。簡単に長いコードのシャッターが作れました。
底を見ると、右から裏蓋をはずすロックノブ、電池室の蓋、
三脚ネジ、直結バッテリーをMD本体への取り付けネジです。
三角形のトンがリがFのあかし。
キャノンのF1も尖がり頭でしたね。
シャッターボタンは建て増ししています。この建て増しシャッターの感触がよかった。
コットってシャッターが落ちるんです。
三角形のプリズムをはずしました。
ファインダースクリーンはF2と共通。プリズムはどうだったかわすれました。
スリットがきっていないので水や砂には弱いでしょう。同じような設計のF3のファインダーに細かい砂が入って、見える視野が楕円形になっていたことがあった。水は意外に入らなかったが、サラサラの砂には弱かった。砂に弱いのは接点の多いMDも一緒です。
貧乏だったので、なけなしのお金をはたいて買ったNikonFです。
そのご仕事に使うようになってMDを購入。15年は一線で使っていました。
倉庫から出してきたので梨地が汚れたまま。拭いたらきれいになった。
キレイニしてから撮ったらよかった。
MDは使いにくかったですねー。
フィルムチェンジは悩ましい作業でした。
裏蓋をパカーンと外さなきゃいけないのだもの。外でのチェンジは、雨でも降っていたらたいへん。
ただし、機械的には丈夫だった。カメラが水没してもダイジョーブ。今の電気カメラには考えられないことです。
本体のシャッターとMDのマイクロシャッター(マイクロ接点)。
本体はそれなりの感触ですが、MDのはただのスイッチです。
ただ、、、タイムラグは恐ろしく少ない!
それは動体写真のプロには戦力になりました。
タイムラグは、、カメラによって違うので、0.1秒の遅れは問題外、0.01秒の違いがプロにはわかります、、、。
MDについているつっかえ棒は、文字ドウリつっかえ棒。
接点が複雑で、FP、FX、MXといろいろ。フラッシュからストロボへの過渡期なので 仕方ないでしょう。
シャッター、巻き上げ周りはNikonMシリーズのままですね。
Mシリーズを一眼レフ化したのがFだから、、、。
このパーツもMシリーズと同じ。
正面から見ると逆テッパーがついている。
アクセサリーシューをつけるようになっているが、巻き戻しノブが使えなくなるので、、、どーなの?
このシンプルなファインダーのほかに、露出計内臓のフォトミックファインダーがあった。
MDを外すと、ただのFに戻ります。
MDを連動させるには底の改造が必要でした。
オリンパスペンと同じフィイルムチェンジ方法です。
良いわきゃないと思うが、、、。
キレイな設計です。
当時の考えられることを全て注入したカメラでした。
これが時代のエッセンスなのです。
直結バッテリーを外して、電源をコードでつなげばMDは使えました。
35mmカメラなのでこれが本来の姿だとは思いますが。
下のスイッチ類は切り替えとシャッターボタンとフィルムカウンター 。
フィルムの巻き戻しは手動だった。
カメラ本体とMD部はこんな形で分離します。
フィルム裏蓋がMDについていくのだから、ナンともおかしな形です。
後側のMDを見ればわかりますが、建て増し状態なのがありあり。
設計の最初からMDは考えていただろうが、Mシリーズを母体にしているので このスタイルになった。
MD本体と直結バッテリーのセット。
さらに分解すると、後ろがMD本体で前部分がバッテリー部。
バッテリーは単三電池を8本です。右端のパーツは無理やりMD本体に連結するパーツ。
接点があちこち多くて埃でもついたら即止まります。
どうなっているかと言うと、、、。
原始的なメカなので、雨などには強かった。水没しても乾燥して接点を復活させれば動き出しました。
雨の日には隙間はビニールテープでぐるぐる巻きにします。
そうすれば、ケッコウな雨でもカサをさしながら片手でモータースポーツを追っていました。熟練度が要求されますが、、、。
MD本体です。
これだけだと実にあっさりしたパーツ。
今日のモーターや電池の発達は目覚ましいものがあります 。
細かなパーツを介して連結します。
この平行ジャックなど、、、家電そのものでしょう。
アップで見ると歴戦のツワモノの感があります。
F本体とMD本体の組み合わせ。
これだけだと、けっこうスマートでコンパクト。
あまり見かけない姿(セット)です。
左のボタンがシャッターをSとCとロックに切り替えるもの。
マイクロスイッチです。
右はフィルムを入れたら自分でカウンターをセットします。
長巻、短めのフィルムなど自分で入れる人がいますから。
Hで毎秒4駒が限度。
私は自動巻上げと考えて使っていました。スポーツでは、いくらMDでも連続シャッターは無意味だったんです。
連続してピントは追えません。今のオートフォーカスだったら意味はあります。
今でも単三電池を入れれば、完全動作します。
チタン幕のシャッターがバウンドするので、外ではムラができますが、ストロボ撮影では全くOK。
私の大事な記念のカメラです。
Nikon D5300
https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/90f6ee141db8fa119081fe775455142f
Nikon D700
https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/e54308fb8d569a17163741ceba84613d
Nikon D40x
https://blog.goo.ne.jp/photostudioon/e/06b238a05f744cbd25aea3b867258822
Nikon F4 MD
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20140113
Nikon D100
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20130428
Nikon F MD ①の記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080224
Nikon F3p MDの記事は(F3本来の姿です)
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080919
Nikon FM ポラボディーの記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070804
Nikon FE2 の記事は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080510
Nikkorex Fの記事は(50年前の機種)
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20090530
Nikkorex 35の記事は(レンズシャッタの一眼レフ)
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20060223
ニッコール24mm、28mm、トキナー28mmテスト
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20091210
ニッコール50mm、マクロ55mm、マクロ60mmテスト
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20110710