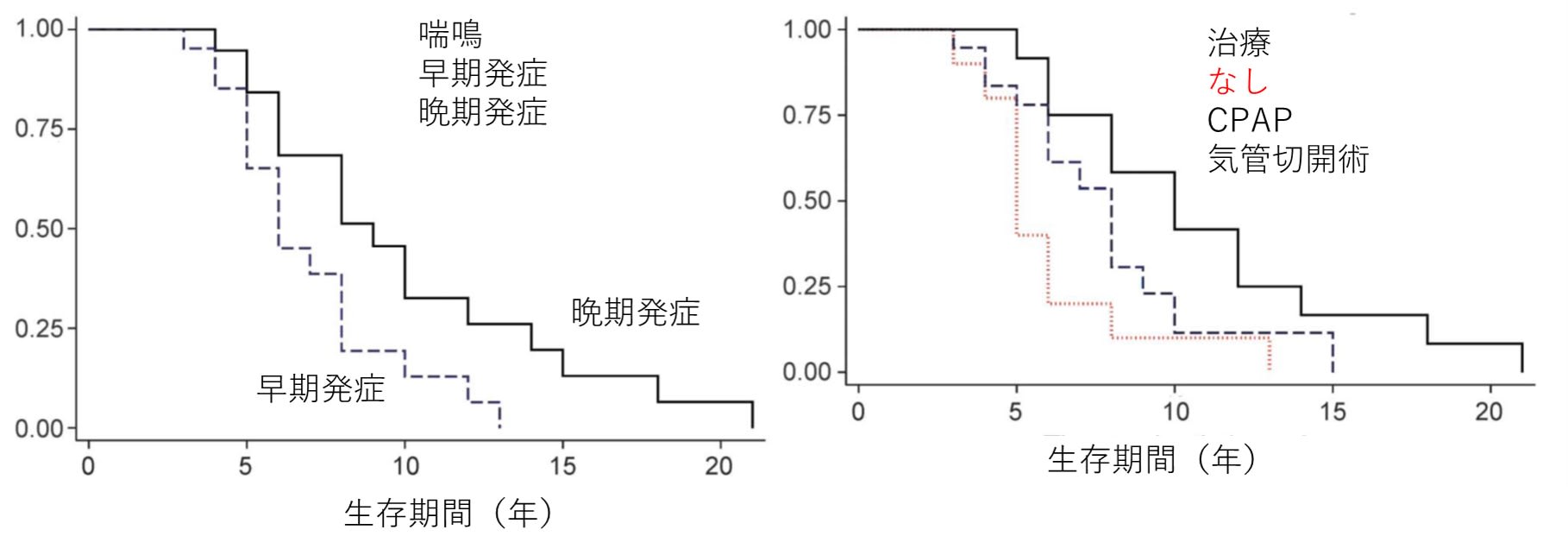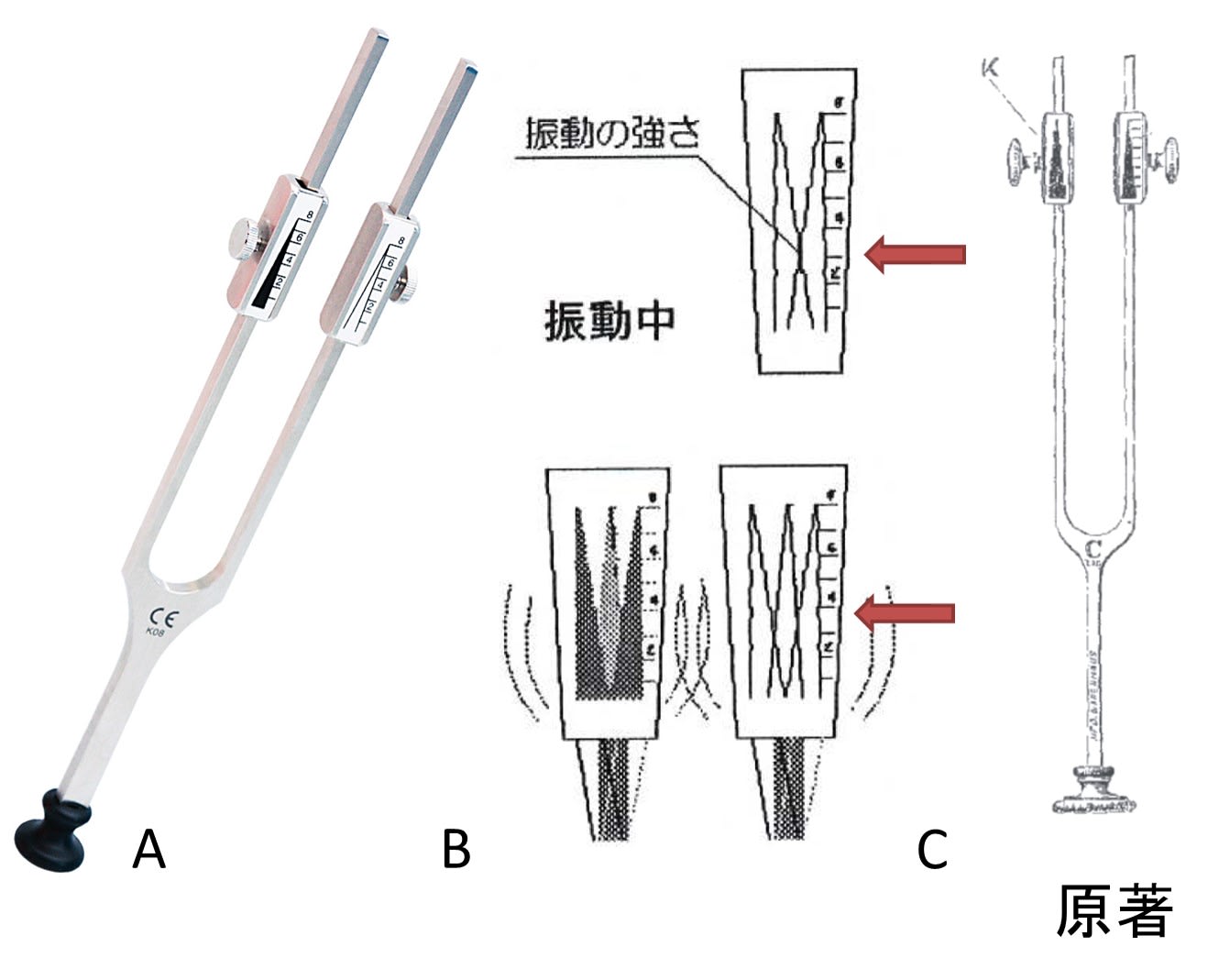外国の病院や大学を見学することは私の趣味である.今回,第5回欧州頭痛・片頭痛学会国際会議@グラスゴーに参加し,その帰途,ロンドン・ロイヤル・ホスピタルに立ち寄った.この病院を訪問した理由は2つある.ひとつは神経内科の領域で,もっとも有名な医師のひとりであるジェームス・パーキンソン(James Parkinson, 1755―1824)が学んだ病院を見たいと思ったため,ふたつめは,アカデミー賞最多8部門にノミネートされた映画「エレファントマン」のモデルが最後の数年を過ごした病院であり,その資料を見ることができるためだ.
地下鉄ホワイトチャペル駅(ディストリクト/ハマースミス&シティ線)を降りると,すぐ右手に古い建物(写真A)と新しい高層のビルが見えてくる.病院までの道は,ロンドンの街なかと明らかに異なるエスニックな雰囲気で,院内も有色人種が多く,ムスリムと分かるスカーフをつけた女性も多かった.患者層が豊かな人ばかりではないという印象を受けたが,そもそもこの病院は1740年にロンドン東部初の貧困層の救済を目的とした無料の病院として作られたことを考えると当然かも知れない.パーキンソンは1789年に始まったフランス革命の影響をうけて,政治運動に活躍したと言われているが,この病院で政治の改革を必要とするような貧困と人間の苦悩を目撃したことがその活動に影響したのだろうと想像することができる.
ジェームス・パーキンソンについて,分かっていることを書きたい.彼は薬剤師兼外科医の息子として,1755年4月11日に生まれた(4月11日は,世界パーキンソン病の日となった).彼の医学の師は,「ドリトル先生」や「ジキル博士とハイド氏」のモデルとなった有名な外科医ジョン・ハンター(John Hunter, 1728-1793)である.「実験医学の父」として知られる優秀な外科医で,多数の動物実験や標本の作成も行った一方,解剖教室のためには法を犯して死体を調達するという裏の顔をもつのだが,ハンターについて書かれた「解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯 (河出文庫) 」は強烈に面白いのでご一読をお勧めする.ちなみに種痘を開発したエドワード・ジェンナーの師もジョン・ハンターである.
」は強烈に面白いのでご一読をお勧めする.ちなみに種痘を開発したエドワード・ジェンナーの師もジョン・ハンターである.
パーキンソンは29歳のときに外科医の資格を得て,父の跡を継ぎ,ロンドンの開業医になり,以後,全生涯をロンドンで暮らす.外科医としても優秀で,やはり医師となる息子とともに虫垂炎で死んだ子供を解剖し,虫垂炎から腹膜炎が起こることをはじめて明らかにしたのも彼である.つまり意外なことに,彼は神経内科の専門家ではなかったのだが,外科医でありながら,精神・神経疾患にも関心を持っていた.
驚くべきことに,彼は医学や政治のみならず,地質学や化石学の研究にも一流で,彼の名前のつく化石の学名(Parkinsonia parkinsoniなど;写真B)も複数残されている.また恐竜の名前を最初に命名したのもパーキンソンだと言われており,メガロサウルス(大きなトカゲの意味)という名前をつけている.イグアノドンの化石を最初に発見したギデオン・マンテルがパーキンソンの親友で,彼がいちばん最初にイグアノドンの化石を見せたのもパーキンソンだったらしい.
そして彼がパーキンソン病について報告したのは62歳,このとき1817年,日本では解体新書の杉田玄白が亡くなった年である.6名の患者に関して「振戦麻痺に関するエッセイ(An Essay on the Shaking Palsy)」という66ページの小冊子を記載した.「振戦麻痺(Shaking palsy)」という用語はパーキンソンが命名したわけではなく,それ以前から使われていたようだ.この小冊子は5章からなり,1章が定義・病歴,6例の症例提示,2章が特有の症状(振戦と加速歩行),古来からの観察,3章が鑑別診断,4章が原因,5章が治療を記載している.「ジェームズ・パーキンソンの人と業績(豊倉康夫編著,診断と治療社)」のなかに原文と日本語訳があるが,これを読むと彼はこの疾患が脊髄由来であると考察している.この報告は当時は正当に評価されなかった.しかしその論文の序文の最後に次のような一文があり,きわめて印象的である.
「こうしてもし必要な知見が得られさえするならば,単なる推論的な示唆にすぎないこの小論文の時期尚早かも知れない発表に対して,いかなる酷評を受けても甘んじてこれに堪えるであろう.それどころか,この厄介で苦悩に満ちた病気をいやすもっとも適切な方法を指摘できるであろう諸賢の注意を喚起したとすれば,私は充分に報われるのである」
パーキンソンの死後の1868年,フランスのシャルコーが「神経病に関する連続講義」で,特徴的な症状として筋強剛を追加し,また「麻痺」ではなく運動の緩慢,開始の遅れであるから「振戦麻痺」という名はふさわしくないとして「パーキンソン病」と呼ぶことを提唱した.彼の業績は死後60年以上経過して初めて評価された.
さて最後にパーキンソンの写真や肖像画について記載したい.Googleで画像検索をすると2つ顔が容易に検索される(写真C, D).しかし,両者とも名前の似た別人であることが2つの小論文により報告されている(Pract Neurol 2011, Pract Neurol 2015).肖像写真の技術が開発されたのはパーキンソンの死後15年経ってからであることと,衣服が19世紀半ばのもので時期的にも合わないのだそうだ.しかし後者の論文の中で,‘The Villager’s Friend and Physician’というパーキンソンが書いたという小冊子が紹介されていて,根拠はやや乏しいものの,村人に講義をする中央に立つ人こそが,パーキンソンだと指摘している(写真E).残念ながらロンドン・ロイヤル・ホスピタルの博物館で尋ねても,パーキンソンについての資料のありかは分からず,肖像画もなかった.しかし開設当時の病院の資料を見て,こんな病院でパーキンソンは勉強をしたのか,彼の姿を空想しつつ愉しい時間を過ごした.
ジェームズ・パーキンソンの人と業績(豊倉康夫編著,診断と治療社)
解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯 (河出文庫)
医学界新聞第2338号1999年5月17日
神経学の歴史

地下鉄ホワイトチャペル駅(ディストリクト/ハマースミス&シティ線)を降りると,すぐ右手に古い建物(写真A)と新しい高層のビルが見えてくる.病院までの道は,ロンドンの街なかと明らかに異なるエスニックな雰囲気で,院内も有色人種が多く,ムスリムと分かるスカーフをつけた女性も多かった.患者層が豊かな人ばかりではないという印象を受けたが,そもそもこの病院は1740年にロンドン東部初の貧困層の救済を目的とした無料の病院として作られたことを考えると当然かも知れない.パーキンソンは1789年に始まったフランス革命の影響をうけて,政治運動に活躍したと言われているが,この病院で政治の改革を必要とするような貧困と人間の苦悩を目撃したことがその活動に影響したのだろうと想像することができる.
ジェームス・パーキンソンについて,分かっていることを書きたい.彼は薬剤師兼外科医の息子として,1755年4月11日に生まれた(4月11日は,世界パーキンソン病の日となった).彼の医学の師は,「ドリトル先生」や「ジキル博士とハイド氏」のモデルとなった有名な外科医ジョン・ハンター(John Hunter, 1728-1793)である.「実験医学の父」として知られる優秀な外科医で,多数の動物実験や標本の作成も行った一方,解剖教室のためには法を犯して死体を調達するという裏の顔をもつのだが,ハンターについて書かれた「解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯 (河出文庫)
パーキンソンは29歳のときに外科医の資格を得て,父の跡を継ぎ,ロンドンの開業医になり,以後,全生涯をロンドンで暮らす.外科医としても優秀で,やはり医師となる息子とともに虫垂炎で死んだ子供を解剖し,虫垂炎から腹膜炎が起こることをはじめて明らかにしたのも彼である.つまり意外なことに,彼は神経内科の専門家ではなかったのだが,外科医でありながら,精神・神経疾患にも関心を持っていた.
驚くべきことに,彼は医学や政治のみならず,地質学や化石学の研究にも一流で,彼の名前のつく化石の学名(Parkinsonia parkinsoniなど;写真B)も複数残されている.また恐竜の名前を最初に命名したのもパーキンソンだと言われており,メガロサウルス(大きなトカゲの意味)という名前をつけている.イグアノドンの化石を最初に発見したギデオン・マンテルがパーキンソンの親友で,彼がいちばん最初にイグアノドンの化石を見せたのもパーキンソンだったらしい.
そして彼がパーキンソン病について報告したのは62歳,このとき1817年,日本では解体新書の杉田玄白が亡くなった年である.6名の患者に関して「振戦麻痺に関するエッセイ(An Essay on the Shaking Palsy)」という66ページの小冊子を記載した.「振戦麻痺(Shaking palsy)」という用語はパーキンソンが命名したわけではなく,それ以前から使われていたようだ.この小冊子は5章からなり,1章が定義・病歴,6例の症例提示,2章が特有の症状(振戦と加速歩行),古来からの観察,3章が鑑別診断,4章が原因,5章が治療を記載している.「ジェームズ・パーキンソンの人と業績(豊倉康夫編著,診断と治療社)」のなかに原文と日本語訳があるが,これを読むと彼はこの疾患が脊髄由来であると考察している.この報告は当時は正当に評価されなかった.しかしその論文の序文の最後に次のような一文があり,きわめて印象的である.
「こうしてもし必要な知見が得られさえするならば,単なる推論的な示唆にすぎないこの小論文の時期尚早かも知れない発表に対して,いかなる酷評を受けても甘んじてこれに堪えるであろう.それどころか,この厄介で苦悩に満ちた病気をいやすもっとも適切な方法を指摘できるであろう諸賢の注意を喚起したとすれば,私は充分に報われるのである」
パーキンソンの死後の1868年,フランスのシャルコーが「神経病に関する連続講義」で,特徴的な症状として筋強剛を追加し,また「麻痺」ではなく運動の緩慢,開始の遅れであるから「振戦麻痺」という名はふさわしくないとして「パーキンソン病」と呼ぶことを提唱した.彼の業績は死後60年以上経過して初めて評価された.
さて最後にパーキンソンの写真や肖像画について記載したい.Googleで画像検索をすると2つ顔が容易に検索される(写真C, D).しかし,両者とも名前の似た別人であることが2つの小論文により報告されている(Pract Neurol 2011, Pract Neurol 2015).肖像写真の技術が開発されたのはパーキンソンの死後15年経ってからであることと,衣服が19世紀半ばのもので時期的にも合わないのだそうだ.しかし後者の論文の中で,‘The Villager’s Friend and Physician’というパーキンソンが書いたという小冊子が紹介されていて,根拠はやや乏しいものの,村人に講義をする中央に立つ人こそが,パーキンソンだと指摘している(写真E).残念ながらロンドン・ロイヤル・ホスピタルの博物館で尋ねても,パーキンソンについての資料のありかは分からず,肖像画もなかった.しかし開設当時の病院の資料を見て,こんな病院でパーキンソンは勉強をしたのか,彼の姿を空想しつつ愉しい時間を過ごした.
ジェームズ・パーキンソンの人と業績(豊倉康夫編著,診断と治療社)
解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯 (河出文庫)
医学界新聞第2338号1999年5月17日
神経学の歴史