〔山本薫先生の授業・続き〕
二名法
ヒト Homosapiens Linnaeus
現在でもこの命名法が国際命名規約にのっとった正式な種名の表記方法として使われています。ラテン語オンリーから最近では英語でも可となりました。
たとえば分類してみると、レモン(ミカン科)・イチゴ(バラ科)・モモ(バラ科)パイナップル(パイナップル科)ナス(ナス科)、ユズ(ミカン科)トマト(ナス科)
亜種とは種の下位に必要に応じて設けられる分類単位です。
変種(Variety)とは形体的に差異があり地理的にも異なるものです
品種とは自然状態で区別できるものを言います。
ソメイヨシノ(染井吉野)江戸の染井村(現在の駒込)はヤマザクラとは異なる種の桜であり、エドヒガシとオオシマザクラの雑種といわれています。(エドヒガシではなくコマツオトメとの雑種だとも)
ソメイヨシノは花弁5枚・葉が出る前に花が咲き満開となる。咲き始めは淡黄色だが満開になると白色になる。開花しても果実はなりにくく、まれに多少有毒なものもあります。
横須賀の学名をもつ植物にヘビノネゴザ (Asplenum Yokosuka Frach et Savat)などがあります。テリハノイバラ (Asarum Savatei Franch)のように人名が入った命名が多かったのですが、最近は地名重視の命名になっています。
三浦半島の成り立ちとしては12・3万年前であり、最終間氷河期でさえ陸地であった。海流は黒潮で、比較低温暖・平均気温は15℃・最低気温0℃、南部では3℃以上、最暖日の8月でも平均26℃です。
代表的な樹としては照葉樹林・最近まで私たちの生活と最も密接な関係にあった落葉広樹林。
ハマユウをはじめとして多様な海岸植物があり、豊かで美しい植生が見受けられます。
ワダン・スナビキソウ・ハイネズ・イズアザミ・ハママツナ・エビアマモ・タチアマモ・ウミヒルモ・イソギク・ハマカンゾウ・ヤブカンゾウなどがあります。
砂浜・海岸ではツルオオバアサギなど水分が逃げていかない葉の形態。
葉が厚く地面を這うような根(ハマゴウ・オカヒジキ・ハマボウフウ・ハマニガナ・ハマグルマ・ツルナ・ナガミノオシバ)
磯の植物・ハマンデシコ・ハマエノコロ・ハマゼリ・テリhノイバラ・タイトウメ・オニヤブソテツ・ヤブソテツなどがあります。ナガバヤブソテツなどはクローンで広く繁殖しています。
クローンとは無性生殖・地下茎・走出枝・無融合繁殖などを言います。
彼岸花は根を伸ばして繁殖しますが、中国では雌雄があるということです。
三浦半島を北限とするものにハマボウなどがあります。
海流によって散布される植物にハマオモト・ハマユウなどがあります。
塩沼地の植物にはアマモ・コアマモといった海草があります。半冠水地では根の発達が悪く茎や葉が多肉化しています。トウオオガ・ハマカンゾウ・スカシユリなどがあります。
海岸沿いにはエノカズラ・クロマツ・マルバシャリンバイ・イソギク・ハナイソギク・ヤマラッキョウ・イズアサツキ・ハマサワヒヨドリ・マルバハマシャジン・ソナレマツムシソウなどがあります。
三浦半島を特色付ける海岸植物としてウバメガシ(北限)があります。消えた海岸植物にはクロマツなどがあります。分布を広げつつある植物としてはハマアザミ(秋谷)などがあります。
海草とは一生を海中で過ごし、花を咲かせ身を実らせる植物を言います。タチアマモ・コアマモ・エビアマモ・ウミヒルモなどは果実や種子も水中に分布され、耐塩性があります(茎や葉に気孔がない)
渓流にはネコノネソウ・ワサビ・ユリワサビ(クレソン)・オランダガラシ(クレソン)
池や沼の植物としてはミズキンバイ・タコノアシ・ミゾソバ・ハンゲショウ・ミズワラビなどがあります。
絶滅種としてはイヌクログワイがあります。
河口の植物としてはハマボウ・アイアシなどがあります。
帰化植物として繁茂したものにはトキワツユクサなどがあります。
ヘビノネゴザは鉱山の標識とされていますが、それはカドミウムやアルミニウムなどの金属イオンを吸収するためです。
西洋タンポポは在来タンポポの花粉を取り込むため急増しました。
沢山のお話、覚えきれませんが、嬉しく拝聴いたしました。ありがとうございました。










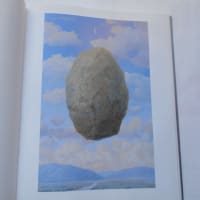
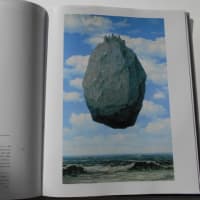
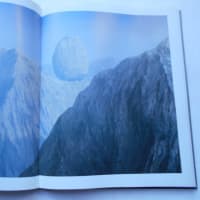
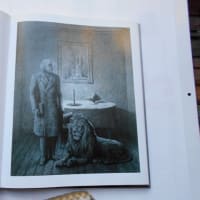

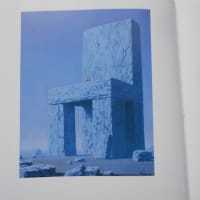
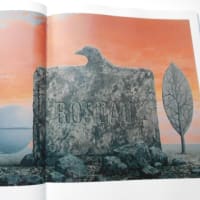
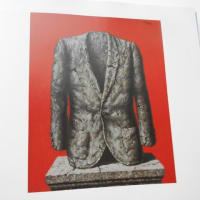
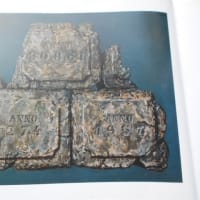
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます