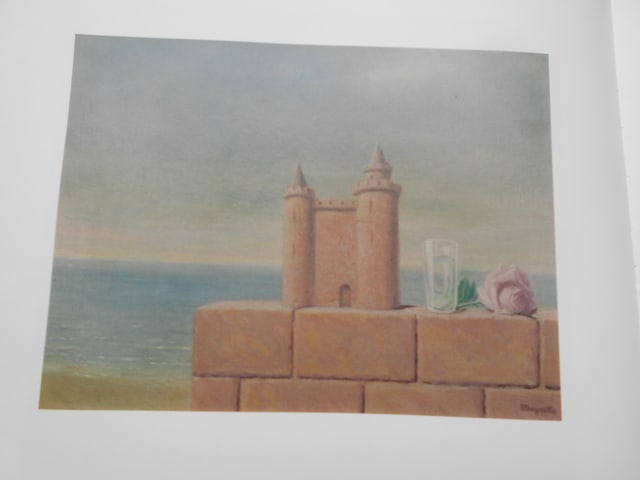葡萄垂れ天上をゆく強き櫂
葡萄垂れはブ・トウ・スイと読んで、武、党、推。
天上をゆく(天上行)はテン・ショウ・アンと読んで、諂、掌、案。
強き櫂はゴウ・トウと読んで、傲、頭。
☆武(強い)党(仲間)を推(前におしだし)諂(へつらう)。
掌(支配する)案(考え)で傲(偉そうにする)頭(トップ)。
葡萄垂れはブ・トウ・スイと読んで、舞、踏、粋。
天上をゆく(天上行)はテン・ショウ・コウと読んで、添、娼、行。
強き櫂はキョウ・トウと読んで、嬌、蕩。
☆舞踏に粋を添える娼(ホステス)の行い。
嬌(艶めかしく)蕩(揺れ動く)。
葡萄垂れはブ・トウ・スイと読んで、部、統、遂。
天上をゆく(天上行)はテン・ショウ・コウと読んで、展、承、講。
強き櫂はキョウ・トウと読んで、協、謄。
☆部(区別して)統(ひとすじにまとめること)を遂(やりとげる)。
展(顧みて)承(受け継ぐ)講(話)を協(併せて)謄(書き写す)。