〔山本薫先生の授業〕
「生物の多様性ですが、総数150万種、陸上植物・約280万種、実際には1000万種くらいはあるであろうと言われています。これらは同じ種でも形や模様、生態など最近に至るまで様々な個性があるという区分けです。
生態学の多様性としては、森・林・里山・河川・湿原・干潟などがあり、北東部はリアス式、南東部は平坦、頭部にはお小楠山があり滑川・田越川など、比較的広い沖積地があります。
多様性を知る上の分類ですが、種類・性質・系統などに従って分けることを言います。
たとえば《食べられるor食べられない》という風です。
古代ギリシャの哲学者であるアリストテレスが初めて動物分類をしたと言われています。植物分類に関しては多くはないようです。
人為分類、つまり人間の利用面を重視して便宜的に分けるという法です。(無毒か有毒か)
リンネは種の範囲の輪郭づけをし、分類体系の公安を成した人です。
種 Species ウメ
属 Genus 種の集まり サクラ科
科 Family 属の集まり バラ科
目 Order 科の集まり バラ目
綱 Class 目の集まり 双子葉植物
門 Division 綱の集まり 被子植物
界 Kingdom 門の集まり 植物界
マイア(1942)生物学的種概念
①形体的に共通したつくりを持つ個体の集まり。
②自然状態で交配がおこなわれ子孫を残していく繁殖集団。
二名法とは、国際命名・規約にのっとった正式な種名(学名)の表記方法です。かつてはラテン語と定められていましたが、現在では英語でも可となっています。
色々体系的な命名法についてのお話など多義にわたり詳細。聴講生の質問にもよく答えてくださり、不明な点は「わたくしの宿題としましょう」などと超真面目な先生。
聞いている方もすごく新鮮な気持ち。
山本先生、ありがとうございました。(これからもよろしく)
最新の画像[もっと見る]










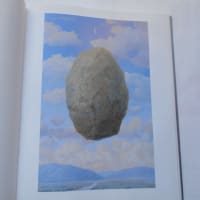
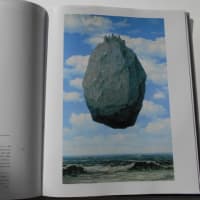
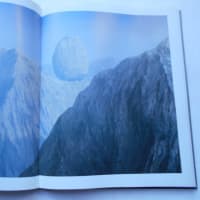
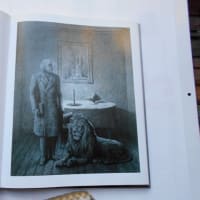

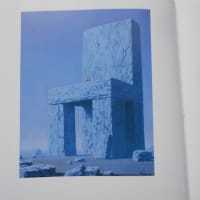
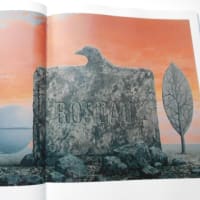
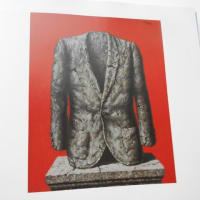
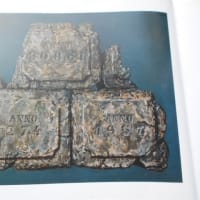
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます