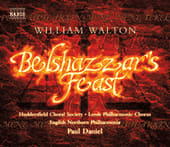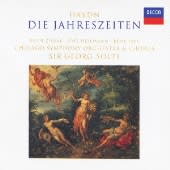前々回でシャルル・グノーの交響曲2曲を紹介しましたが、今回は彼の残した代表的な宗教曲である「聖チェチーリア荘厳ミサ曲」をご紹介します。荘厳ミサ曲はラテン語でミサ・ソレムニスとも言い、本ブログでも過去に紹介したベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」やロッシーニの「小荘厳ミサ曲」等が有名です。グノーの作品に冠されている聖チェチーリアとはローマ時代の3世紀に殉教した聖女で、音楽の守護聖人としてキリスト教世界で古来から崇拝されてきました。彼女の名を関したローマにあるサンタ・チェチーリア国立アカデミーは世界的に有名な音楽学校ですね。
さて、オペラ作曲家として大成功を収めたグノーですが、宗教曲も多く手掛けておりオラトリオを9曲、ミサ曲も10曲以上残しています。ただ、それら宗教曲が演奏される機会はほぼなく、辛うじてこの「聖チェチーリア荘厳ミサ曲」だけが一部で愛好されているぐらいです。ディスクの数もそんなになく、出回っているのはジャン=クロード・アルトマン指揮パリ音楽院管弦楽団による本CDぐらいですね。1963年収録なのでもう50年以上前の演奏ですが、未だにこの曲の決定盤となっています。
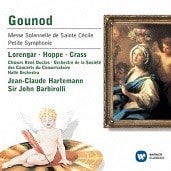
内容については素晴らしいの一言。さすがにベートーヴェンのミサ・ソレムニスと比べるとスケール感には劣りますが、メロディの親しみやすさと美しさでは引けをとりません。曲は敬虔な雰囲気に満ちた「キリエ」で静かに幕を開け、続く第2曲「グローリア」と第3曲「クレド」で最初のクライマックスを迎えます。とりわけ「グローリア」の美しいソプラノ独唱の後に現れる大合唱、思わず一緒に口ずざんでしまうほど歌心にあふれた「クレド」冒頭の合唱が感動的です。「クレド」に続く第4曲「オッフェルトリウム」は歌はなくインストゥルメンタルのみですが、静謐な美しさが胸に沁みる珠玉の名旋律です。続いて、終盤に向けて静かに盛り上がる第5曲「サンクトゥス」、敬虔な雰囲気に満ち溢れた第6曲「ベネディクトゥス」と第7曲「アニュス・デイ」、そして最終曲「ドミネ・サルヴム」の感動的なフィナーレへとつながっていきます。45分弱と宗教曲にしてはコンパクトですが、ギュッと魅力が詰まった名曲中の名曲だと思います。
なお、このCDには同じグノーの「小交響曲」という作品も収録されており、こちらはジョン・バルビローリ指揮ハレ管弦楽団の演奏です。題名からすると短めの交響曲かと思いますが、実際は9つの管楽器による室内楽作品です。古楽的な雰囲気が魅力なのかもしれませんが、感動的な「聖チェリーリア」のあとに聞くと地味過ぎて印象に残りません。
さて、オペラ作曲家として大成功を収めたグノーですが、宗教曲も多く手掛けておりオラトリオを9曲、ミサ曲も10曲以上残しています。ただ、それら宗教曲が演奏される機会はほぼなく、辛うじてこの「聖チェチーリア荘厳ミサ曲」だけが一部で愛好されているぐらいです。ディスクの数もそんなになく、出回っているのはジャン=クロード・アルトマン指揮パリ音楽院管弦楽団による本CDぐらいですね。1963年収録なのでもう50年以上前の演奏ですが、未だにこの曲の決定盤となっています。
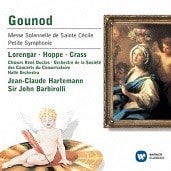
内容については素晴らしいの一言。さすがにベートーヴェンのミサ・ソレムニスと比べるとスケール感には劣りますが、メロディの親しみやすさと美しさでは引けをとりません。曲は敬虔な雰囲気に満ちた「キリエ」で静かに幕を開け、続く第2曲「グローリア」と第3曲「クレド」で最初のクライマックスを迎えます。とりわけ「グローリア」の美しいソプラノ独唱の後に現れる大合唱、思わず一緒に口ずざんでしまうほど歌心にあふれた「クレド」冒頭の合唱が感動的です。「クレド」に続く第4曲「オッフェルトリウム」は歌はなくインストゥルメンタルのみですが、静謐な美しさが胸に沁みる珠玉の名旋律です。続いて、終盤に向けて静かに盛り上がる第5曲「サンクトゥス」、敬虔な雰囲気に満ち溢れた第6曲「ベネディクトゥス」と第7曲「アニュス・デイ」、そして最終曲「ドミネ・サルヴム」の感動的なフィナーレへとつながっていきます。45分弱と宗教曲にしてはコンパクトですが、ギュッと魅力が詰まった名曲中の名曲だと思います。
なお、このCDには同じグノーの「小交響曲」という作品も収録されており、こちらはジョン・バルビローリ指揮ハレ管弦楽団の演奏です。題名からすると短めの交響曲かと思いますが、実際は9つの管楽器による室内楽作品です。古楽的な雰囲気が魅力なのかもしれませんが、感動的な「聖チェリーリア」のあとに聞くと地味過ぎて印象に残りません。