私は民間会社の中小業のある会社に35年近く奮戦し2004年(平成16年)の秋に定年退職し、
最後の5年半はリストラ烈風の中、出向となったりし、敗残者のようなサラリーマン時代を過ごした。
その上、私の半生は、何かと卑屈と劣等感にさいなまれ、悪戦苦闘の多かった歩みだったので、
せめて残された人生は、多少なりとも自在に過ごしたと思い、年金生活を始めた・・。
この間、私たち夫婦は自分たちの老後の生活の改めて話し合ったのは、
1999年(平成11年)の新春の当時で、私が54歳あった。
私が勤めてきた中小業の多い音楽業界の各レコード会社は、1998年(平成10年)に売上の主軸となるCDがピークとなり、
この少し前の年から各社はリストラ烈風となり、業務の大幅な見直し、会社間の統廃合もあり、人員削減も行われはじめた。
私の勤めた会社も同様に、早期退職優遇制度の下で、上司、同僚、後輩の一部が業界から去ったりし、
人事異動も盛んに行われたりし、 私も50代のなかば1999年(平成11年)の新春、
取引先の物流会社に出向を命じられた。
こうした時に、私が定年退職を出来た後、どのような生活をしたいか、そして生活資金などを話し合った。
具体的には、私たち夫婦の第二の人生は、どのように過ごしたいのか、主題であった。

やがて結論としては、定年退職後の60歳以降は、
私は働くことを卒業し、お互いのささやかな趣味を互いに干渉することなく、
共通の趣味のひとつの国内旅行を四季折々できればよいなぁ、と漠然に念願したりした。
こうしたことを実現するためには、この当時も各出版社から数多くの本が発売されていたので、私なりに買い求めた。
そして『定年後』~「もうひとつの人生」への案内~(岩波書店)、『間違いだらけの定年設計』(青春出版社)、
『「定年後」設計 腹づもり ~50代から考えておきたい~』(三笠書房)などを購読した。
或いは雑誌としては、 『ほんとうの時代 ~50代から読む「大人の生き方誌」~』(PHP研究所)であり、
こうした本を読んだりしながら、現在の我が家の貯金の確認、定年退職までの年収、退職金など、そして年金の推定額も算出し、
収支概算表を年別に作表し、この当時の夫婦平均寿命までの年を総括表にしたりした。
そして、毎年の月別は、家計簿の応用で収入の項目、支出の保険、税金等を含め、予定表も作成したりした。
この時の私は、幸いに住宅ローンを終えていたが、私は1944年(昭和19年)9月生まれであるので、
年金の満額の支給は62歳であり、それまでの2年間は満額のほぼ半分となるので、このことも配慮した。
そして年金が満額となった62歳からの生活の収支は、
私たち夫婦の共通趣味である国内旅行費、そして冠婚葬祭など諸経費は例外として、
原則として生活費は年金を頂く範囲として、収支の概要を作成したりした。
こうした結果、私の年齢、家内の年齢を主軸に、1998年(平成10年)から私が80歳を迎えるまで、
年次別の収支と残額を作成し、パソコンに入れて、計画、実績、差額を毎月入れたりしていた。

こうした中、不慣れな遠い勤務先の出向会社に私が奮戦している時、
出向先の物流会社も大幅なリストラが実施されたり、
私が30年近く勤めてきた出向元のレコード会社会社でも、リストラ烈風となる中、
私の同僚、後輩の一部が定年前の退社の連絡、或いは葉書で挨拶状を頂いたりし、
私は出向先で2004年〈平成16年〉の秋に定年退職を迎えたのである。
そして、私は出向身分であったので、何とか烈風から免れたのも事実であり、
定年前の退社された同僚、後輩に少し後ろめたく、退職後の年金生活に入った理由のひとつとなった。
こうした中で、経済にも疎(うと)い私が、信愛している経済ジャーナリストの荻原博子さんなどの数多く著名人の寄稿文を読み、
デフレ経済の蔓延している中、公的年金を受け取りながら堅実に年金生活をし、
預貯金が3000万円あれば、少しづつ取り崩して生活すれば、少しはゆとりのある年金生活ができるかしら、
と学んだりした。
しかしながら私はつたないサラリーマン時代の軌跡であったので、もとより一流大学を卒業され、大企業、中央官庁などに
38年前後を邁進し栄達されたエリートの年収、そして退職金などは、遥かに及ぶことなく、遠い存在である。

2004年(平成16年)の秋に定年退職し、年金生活を始めた直後、私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、
銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした時、ある銀行の窓口で私の退職金を引き出した時、支店長から応接間に招待され、
支店長から『一時払い終身保険』を私たち夫婦に説明して頂ながら、勧誘させられたりした。
しかし10年間の運用利回りが良いと言われても、長期に及び資金が固定されてしまうので、
魅力は感じることなく、対象外とした。
この直後、支店長から3分の2はある投資信託で高い金利、残りの3分の1を安全利回りで運用されれば確実に増えます、
と勧誘するように助言されたりした。
そして支店長が自分もしていますよ、と自身の投資額と金利の推移表のカードを
私たち夫婦に見せて、先月は5万少し・・と提示して、微笑みながら勧誘した。
しかし私たち夫婦は、もとより金利の変動は良いことあれば悪いこともあり、
悪化しマイナスになった場合は、残された人生に狂いが生じるので、安全な国債などした。
私は小心者のせいか株、投資信託などのハイリターン、ハイリスクで、
残された大切な人生に一喜一憂するのは、何よりも心身によくないと思ったりした。
そして、貯金関係は殆ど国債の元本保証プラスわずかな金利、そして定期貯金を選定したのである。

こうした私たち夫婦の根底には、バブル期の終了まじかに、投資信託に失敗したことがあったことが主因であった。
バブル期、私は現役のサラリーマンであり、同僚たちが盛んに株の売買で、高揚していた。
私は基本的な私たちの生活資金として、この当時は預貯金は1000万に到達していない上、
小心者の為に株のハイリターン、ハイリスクは避けて、ボーナスを頂くたびに定期貯金に加算したりしていた。
やがてある証券会社より、投資信託の勧誘のパンフレットが郵送され、
何かしら四半期毎に8%~12%の利回りがあった、と直近の四半期実績推移表が添付していた。
そして天下のXX証券が、世界中の資金を運用するプロの集団だから、と信頼して、
取りあえず100万円だけ、我が家は投資した。
一年過ぎた頃、結果として元本の100万円の消えて、精算は85万円にお詫び状が付いていた。
そして我が家は少なくとも15万円も損失したので、これ以来とのような証券会社より勧誘が来ても、
無視をしたりしてきた。
我が家は国債を二千万円足らずを購入しているが、絶対的に大丈夫、と問われれば、
『国債が駄目になった時は日本が滅びる時である・・その時は私たちの生命財産はもとより保障されないので・・』
と私は今でも公言をしている。
このように我が家は預貯金に関しては、元本保証プラスわずかな金利主義となっている。
確か年金生活を始めた翌年の2005年(平成17年)頃に、
外資のシティバンクの新聞に《・・金融資産1億円の方に・・》と掲載していた。
私はこっそりと読んだりしたが、金融資産と住宅の敷地の固定資産評価額を加算したら1億円は超えるが、
とても金融資産1億円は・・と項垂(うなだ)れたりした。
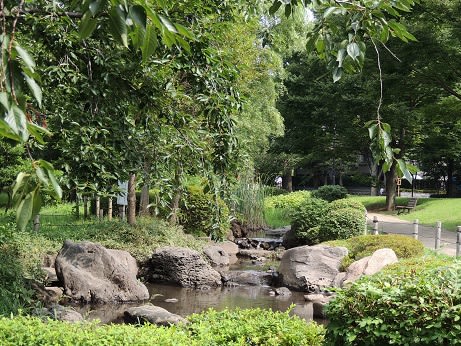
昨年の2013年(平成15年)、ビジネス総合情報誌として名高い『プレジデント』が、
『ゆとりある老後 必要な資金は』の記事をネットで提供された記事を私は精読していた・・。
ジャーナリストの山本信幸さんの寄稿文を無断ながら、長く引用させて頂く。
《・・(略)・・定年後の生活にいくら必要か? という質問にひと言で答えるなら「1億円」である。
大卒社員の生涯賃金の3分の1に相当するお金を、老後のために確保することなんてできるのだろうか?
まずは老後の生活には毎月いくらかかるかという話から始めよう。
2010年度の総務省・家計調査報告によると、
夫65歳以上、妻60歳以上の高齢無職世帯の夫婦の1カ月の平均支出が26万4948円。
対する収入は22万3757円。毎月4万1191円の赤字である。
ここで注目すべきは「年金面では恵まれているリタイヤメント世代でも、
公的年金だけでは生活ができない」ところにあるとFP(ファイナンシャルプランナー)の大竹のり子氏は指摘する。
しかも「収支が赤字になる状況は、現役世代がリタイヤする頃になっても解消されないどころか、
もっと厳しい状態になる」(大竹のり子氏)ことはほぼ確実だ。
この生活で夫婦ともに90歳まで生きると仮定して、60歳以降、年金以外に必要なお金は約3000万円だ。
ところがこの平均的な支出では、旅行やレジャー、趣味を楽しむゆとりのある生活はできないと多くの人は考えている。

2010年度「生活保障に関する調査」(生命保険文化センター)によれば、
夫婦で老後にゆとりある生活を送るには36万6000円の収入が欲しいという。
その場合、30年間で必要な額は約6700万円にも膨れ上がる。
とはいえリタイヤ直後の65歳と、20年後の85歳では生活の仕方も変わるはずだから、
生涯にわたって毎月36万6000円使うというわけではない。
老後のお金に詳しい経営コンサルタントの岩崎日出俊氏は、こう試算している。
60歳まで生きた男性の平均寿命は82.84歳、女性は88.37歳まで生きるという統計(2010年簡易生命表)がある。
余裕を持たせて夫87歳、妻92歳まで生きると仮定し、
最低限の生活のためには月24万円、ややゆとりある生活のためには月30万円かかるとすると、
最低限生活では1億776万円、ゆとり生活では1億1856万円確保しなければならない。
しかし年金が7274万円支給されるので「不足分は最低限生活で3502万円、
ゆとり生活で4582万円になります」。・・(略)・・》
ここまで私は読んだら、年金生活のスタート時点に4500万円あれば、ゆとり生活ができる、
と苦笑したりした。
そして私の現役時代の先輩、同僚、或いは友人の中で、
不幸にも定年退職時の前に、リストラ烈風で退社を余儀なくされて、不遇な方もいる。
或いは父親の商店を受け継いで、何とか生活しているよ、と私は中学校時代のの有志会で、聞いたりしてきた。

こうした中で、私は総務省が「家計調査」実態の公表を読んだりした。
昨年の2013年(平成25年)6月末現在の平均支出額として、
60歳から69歳の世帯で月額25万9695円、70歳以降が19万6500円。
或いは金融広報委員会の調査に於いては、老後の生活費として現役世代が見込んでいる金額は平均で26万円。
こうした実態であるならば、年金だけでは老後の生活費をまかなうことはできない、と私は思われた。
そして肝要の年金受給額の実態は、日本年金機構の公表に於いては、
一昨年の2012年(平成24年)2月現在として、モデル世帯の年金月額は約23万円。
そして内訳は、夫の老齢厚生年金が約10万円、老齢基礎年金が約6万5000円、妻の老齢基礎年金が約6万5000円。
そしてモデル世帯は、夫が厚生年金に40年加入し、妻が第3号被保険者を含め、国民年金を40年納めた場合であり、
ここ15年前後、経済が衰退する中でリストラ烈風もあった中で、モデル世帯のような条件の良い世帯は現実には少数派、
と私は感じたりした。
そして実際の年金額の平均としては、日本年金機構の統計の昨年の2013年(平成25年)7月現在に寄れば、
厚生年金が10万8348円、基礎年金が5万3716円。
そして夫が会社員、妻が専業主婦というモデルに合わせた場合、平均の年金額は21万5780円。
そして60歳から69歳の支出額に、約4万4000円不足。
このような年金生活の実態を私は学んだりしてきた。

年金生活の我が家の基本は、厚生年金、わずかな企業年金を頂き、通常の生活費するのが原則としている。
しかし共通の趣味のひとつである国内旅行、或いは冠婚葬祭などの思いがけない出費などに関し、
程々の貯金を取り崩して生活している。
そして、毎年年始が過ぎた頃に、新年度の月別の概算表を作る際、
家内の要望などを織り込んで作成し、予算としている。
従って、年金生活の身であるから、今年も赤字が120万円前後かしら、とお互いに確認し合っている。
こうして私たち夫婦は経済的に贅沢な生活は出来ないが、
働らなくても何とか生活ができるので助かるわ、
と家内がときおり、 呟(つぶや)くように私に言ったりするので、私は苦笑したりしているのが、
我が家の実態である。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪
 にほんブログ村
にほんブログ村

最後の5年半はリストラ烈風の中、出向となったりし、敗残者のようなサラリーマン時代を過ごした。
その上、私の半生は、何かと卑屈と劣等感にさいなまれ、悪戦苦闘の多かった歩みだったので、
せめて残された人生は、多少なりとも自在に過ごしたと思い、年金生活を始めた・・。
この間、私たち夫婦は自分たちの老後の生活の改めて話し合ったのは、
1999年(平成11年)の新春の当時で、私が54歳あった。
私が勤めてきた中小業の多い音楽業界の各レコード会社は、1998年(平成10年)に売上の主軸となるCDがピークとなり、
この少し前の年から各社はリストラ烈風となり、業務の大幅な見直し、会社間の統廃合もあり、人員削減も行われはじめた。
私の勤めた会社も同様に、早期退職優遇制度の下で、上司、同僚、後輩の一部が業界から去ったりし、
人事異動も盛んに行われたりし、 私も50代のなかば1999年(平成11年)の新春、
取引先の物流会社に出向を命じられた。
こうした時に、私が定年退職を出来た後、どのような生活をしたいか、そして生活資金などを話し合った。
具体的には、私たち夫婦の第二の人生は、どのように過ごしたいのか、主題であった。

やがて結論としては、定年退職後の60歳以降は、
私は働くことを卒業し、お互いのささやかな趣味を互いに干渉することなく、
共通の趣味のひとつの国内旅行を四季折々できればよいなぁ、と漠然に念願したりした。
こうしたことを実現するためには、この当時も各出版社から数多くの本が発売されていたので、私なりに買い求めた。
そして『定年後』~「もうひとつの人生」への案内~(岩波書店)、『間違いだらけの定年設計』(青春出版社)、
『「定年後」設計 腹づもり ~50代から考えておきたい~』(三笠書房)などを購読した。
或いは雑誌としては、 『ほんとうの時代 ~50代から読む「大人の生き方誌」~』(PHP研究所)であり、
こうした本を読んだりしながら、現在の我が家の貯金の確認、定年退職までの年収、退職金など、そして年金の推定額も算出し、
収支概算表を年別に作表し、この当時の夫婦平均寿命までの年を総括表にしたりした。
そして、毎年の月別は、家計簿の応用で収入の項目、支出の保険、税金等を含め、予定表も作成したりした。
この時の私は、幸いに住宅ローンを終えていたが、私は1944年(昭和19年)9月生まれであるので、
年金の満額の支給は62歳であり、それまでの2年間は満額のほぼ半分となるので、このことも配慮した。
そして年金が満額となった62歳からの生活の収支は、
私たち夫婦の共通趣味である国内旅行費、そして冠婚葬祭など諸経費は例外として、
原則として生活費は年金を頂く範囲として、収支の概要を作成したりした。
こうした結果、私の年齢、家内の年齢を主軸に、1998年(平成10年)から私が80歳を迎えるまで、
年次別の収支と残額を作成し、パソコンに入れて、計画、実績、差額を毎月入れたりしていた。

こうした中、不慣れな遠い勤務先の出向会社に私が奮戦している時、
出向先の物流会社も大幅なリストラが実施されたり、
私が30年近く勤めてきた出向元のレコード会社会社でも、リストラ烈風となる中、
私の同僚、後輩の一部が定年前の退社の連絡、或いは葉書で挨拶状を頂いたりし、
私は出向先で2004年〈平成16年〉の秋に定年退職を迎えたのである。
そして、私は出向身分であったので、何とか烈風から免れたのも事実であり、
定年前の退社された同僚、後輩に少し後ろめたく、退職後の年金生活に入った理由のひとつとなった。
こうした中で、経済にも疎(うと)い私が、信愛している経済ジャーナリストの荻原博子さんなどの数多く著名人の寄稿文を読み、
デフレ経済の蔓延している中、公的年金を受け取りながら堅実に年金生活をし、
預貯金が3000万円あれば、少しづつ取り崩して生活すれば、少しはゆとりのある年金生活ができるかしら、
と学んだりした。
しかしながら私はつたないサラリーマン時代の軌跡であったので、もとより一流大学を卒業され、大企業、中央官庁などに
38年前後を邁進し栄達されたエリートの年収、そして退職金などは、遥かに及ぶことなく、遠い存在である。

2004年(平成16年)の秋に定年退職し、年金生活を始めた直後、私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、
銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした時、ある銀行の窓口で私の退職金を引き出した時、支店長から応接間に招待され、
支店長から『一時払い終身保険』を私たち夫婦に説明して頂ながら、勧誘させられたりした。
しかし10年間の運用利回りが良いと言われても、長期に及び資金が固定されてしまうので、
魅力は感じることなく、対象外とした。
この直後、支店長から3分の2はある投資信託で高い金利、残りの3分の1を安全利回りで運用されれば確実に増えます、
と勧誘するように助言されたりした。
そして支店長が自分もしていますよ、と自身の投資額と金利の推移表のカードを
私たち夫婦に見せて、先月は5万少し・・と提示して、微笑みながら勧誘した。
しかし私たち夫婦は、もとより金利の変動は良いことあれば悪いこともあり、
悪化しマイナスになった場合は、残された人生に狂いが生じるので、安全な国債などした。
私は小心者のせいか株、投資信託などのハイリターン、ハイリスクで、
残された大切な人生に一喜一憂するのは、何よりも心身によくないと思ったりした。
そして、貯金関係は殆ど国債の元本保証プラスわずかな金利、そして定期貯金を選定したのである。

こうした私たち夫婦の根底には、バブル期の終了まじかに、投資信託に失敗したことがあったことが主因であった。
バブル期、私は現役のサラリーマンであり、同僚たちが盛んに株の売買で、高揚していた。
私は基本的な私たちの生活資金として、この当時は預貯金は1000万に到達していない上、
小心者の為に株のハイリターン、ハイリスクは避けて、ボーナスを頂くたびに定期貯金に加算したりしていた。
やがてある証券会社より、投資信託の勧誘のパンフレットが郵送され、
何かしら四半期毎に8%~12%の利回りがあった、と直近の四半期実績推移表が添付していた。
そして天下のXX証券が、世界中の資金を運用するプロの集団だから、と信頼して、
取りあえず100万円だけ、我が家は投資した。
一年過ぎた頃、結果として元本の100万円の消えて、精算は85万円にお詫び状が付いていた。
そして我が家は少なくとも15万円も損失したので、これ以来とのような証券会社より勧誘が来ても、
無視をしたりしてきた。
我が家は国債を二千万円足らずを購入しているが、絶対的に大丈夫、と問われれば、
『国債が駄目になった時は日本が滅びる時である・・その時は私たちの生命財産はもとより保障されないので・・』
と私は今でも公言をしている。
このように我が家は預貯金に関しては、元本保証プラスわずかな金利主義となっている。
確か年金生活を始めた翌年の2005年(平成17年)頃に、
外資のシティバンクの新聞に《・・金融資産1億円の方に・・》と掲載していた。
私はこっそりと読んだりしたが、金融資産と住宅の敷地の固定資産評価額を加算したら1億円は超えるが、
とても金融資産1億円は・・と項垂(うなだ)れたりした。
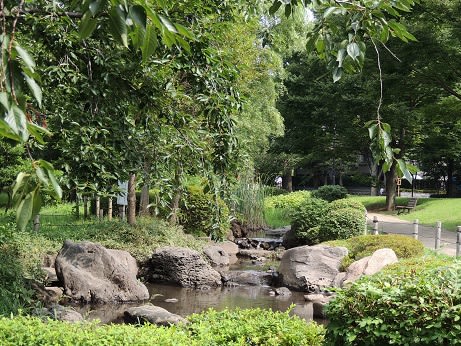
昨年の2013年(平成15年)、ビジネス総合情報誌として名高い『プレジデント』が、
『ゆとりある老後 必要な資金は』の記事をネットで提供された記事を私は精読していた・・。
ジャーナリストの山本信幸さんの寄稿文を無断ながら、長く引用させて頂く。
《・・(略)・・定年後の生活にいくら必要か? という質問にひと言で答えるなら「1億円」である。
大卒社員の生涯賃金の3分の1に相当するお金を、老後のために確保することなんてできるのだろうか?
まずは老後の生活には毎月いくらかかるかという話から始めよう。
2010年度の総務省・家計調査報告によると、
夫65歳以上、妻60歳以上の高齢無職世帯の夫婦の1カ月の平均支出が26万4948円。
対する収入は22万3757円。毎月4万1191円の赤字である。
ここで注目すべきは「年金面では恵まれているリタイヤメント世代でも、
公的年金だけでは生活ができない」ところにあるとFP(ファイナンシャルプランナー)の大竹のり子氏は指摘する。
しかも「収支が赤字になる状況は、現役世代がリタイヤする頃になっても解消されないどころか、
もっと厳しい状態になる」(大竹のり子氏)ことはほぼ確実だ。
この生活で夫婦ともに90歳まで生きると仮定して、60歳以降、年金以外に必要なお金は約3000万円だ。
ところがこの平均的な支出では、旅行やレジャー、趣味を楽しむゆとりのある生活はできないと多くの人は考えている。

2010年度「生活保障に関する調査」(生命保険文化センター)によれば、
夫婦で老後にゆとりある生活を送るには36万6000円の収入が欲しいという。
その場合、30年間で必要な額は約6700万円にも膨れ上がる。
とはいえリタイヤ直後の65歳と、20年後の85歳では生活の仕方も変わるはずだから、
生涯にわたって毎月36万6000円使うというわけではない。
老後のお金に詳しい経営コンサルタントの岩崎日出俊氏は、こう試算している。
60歳まで生きた男性の平均寿命は82.84歳、女性は88.37歳まで生きるという統計(2010年簡易生命表)がある。
余裕を持たせて夫87歳、妻92歳まで生きると仮定し、
最低限の生活のためには月24万円、ややゆとりある生活のためには月30万円かかるとすると、
最低限生活では1億776万円、ゆとり生活では1億1856万円確保しなければならない。
しかし年金が7274万円支給されるので「不足分は最低限生活で3502万円、
ゆとり生活で4582万円になります」。・・(略)・・》
ここまで私は読んだら、年金生活のスタート時点に4500万円あれば、ゆとり生活ができる、
と苦笑したりした。
そして私の現役時代の先輩、同僚、或いは友人の中で、
不幸にも定年退職時の前に、リストラ烈風で退社を余儀なくされて、不遇な方もいる。
或いは父親の商店を受け継いで、何とか生活しているよ、と私は中学校時代のの有志会で、聞いたりしてきた。

こうした中で、私は総務省が「家計調査」実態の公表を読んだりした。
昨年の2013年(平成25年)6月末現在の平均支出額として、
60歳から69歳の世帯で月額25万9695円、70歳以降が19万6500円。
或いは金融広報委員会の調査に於いては、老後の生活費として現役世代が見込んでいる金額は平均で26万円。
こうした実態であるならば、年金だけでは老後の生活費をまかなうことはできない、と私は思われた。
そして肝要の年金受給額の実態は、日本年金機構の公表に於いては、
一昨年の2012年(平成24年)2月現在として、モデル世帯の年金月額は約23万円。
そして内訳は、夫の老齢厚生年金が約10万円、老齢基礎年金が約6万5000円、妻の老齢基礎年金が約6万5000円。
そしてモデル世帯は、夫が厚生年金に40年加入し、妻が第3号被保険者を含め、国民年金を40年納めた場合であり、
ここ15年前後、経済が衰退する中でリストラ烈風もあった中で、モデル世帯のような条件の良い世帯は現実には少数派、
と私は感じたりした。
そして実際の年金額の平均としては、日本年金機構の統計の昨年の2013年(平成25年)7月現在に寄れば、
厚生年金が10万8348円、基礎年金が5万3716円。
そして夫が会社員、妻が専業主婦というモデルに合わせた場合、平均の年金額は21万5780円。
そして60歳から69歳の支出額に、約4万4000円不足。
このような年金生活の実態を私は学んだりしてきた。

年金生活の我が家の基本は、厚生年金、わずかな企業年金を頂き、通常の生活費するのが原則としている。
しかし共通の趣味のひとつである国内旅行、或いは冠婚葬祭などの思いがけない出費などに関し、
程々の貯金を取り崩して生活している。
そして、毎年年始が過ぎた頃に、新年度の月別の概算表を作る際、
家内の要望などを織り込んで作成し、予算としている。
従って、年金生活の身であるから、今年も赤字が120万円前後かしら、とお互いに確認し合っている。
こうして私たち夫婦は経済的に贅沢な生活は出来ないが、
働らなくても何とか生活ができるので助かるわ、
と家内がときおり、 呟(つぶや)くように私に言ったりするので、私は苦笑したりしているのが、
我が家の実態である。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪


















