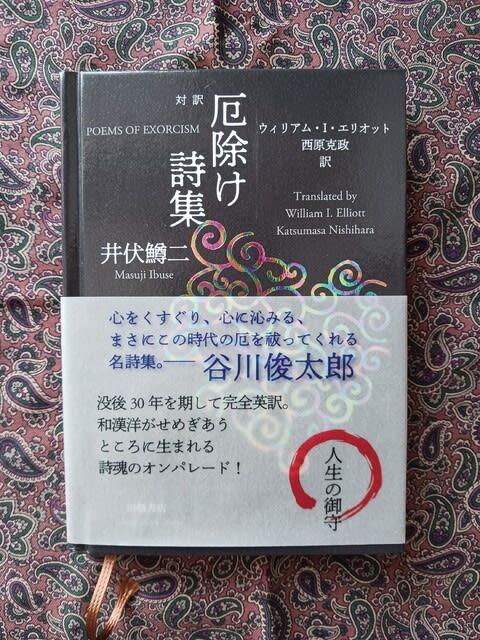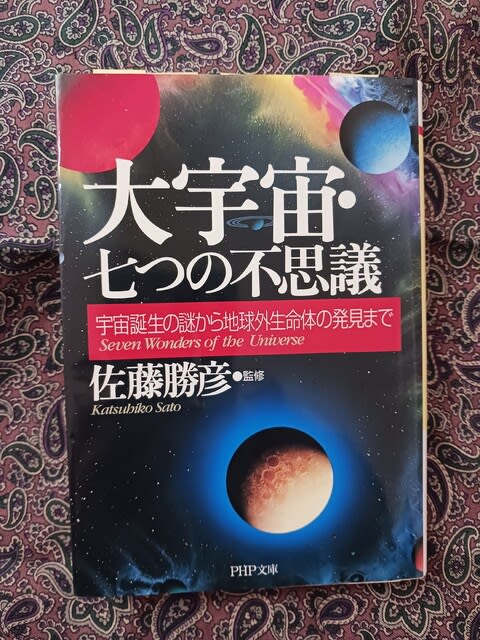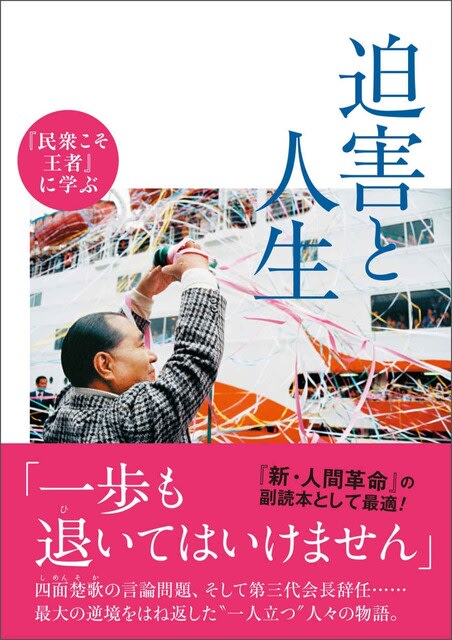著者 田中 俊孝
出版 神奈川新聞社
定価 1500円+税
頁数 170頁

2023年10月から3カ月間、神奈川新聞に62回に渡り連載された中小企業の社長の自叙伝である。
自身が経営者として歩んできた人生とは何だったのだろうか。果たして、功成り名を遂げたと言えるのだろうか。人生のターニング・ポイントで去来した思いが、そのまま書名の『縁と恩に有難う』になった。そんな素晴らしく素直な感謝と奮闘の一代記である。
著者とはほぼ同世代。ここで登場する昭和の世相やトレンドやゴシップ、熱気などは殆ど共有できる。ちなみに、私のIDの一つは〈vintage.shonan-boy.1946〉であることを告白しておこう。”右型上がり”やら”護送船団方式”と名付けられ、国際的にも類を見ない”分厚い中間層”が我が国を支えた時代である。自分を信じ仲間との紐帯に意気を感じ、為せば成ると確信に満ちた時代。一実業家の生きざまは、即同時代を生き抜いてきた我々一人ひとりの物語でもある。悪戦苦闘、愛別離苦、慙愧の念、欣喜雀躍みな収まっている。
とりわけ印象深いのは著者の父君への思いであろうか。行間に散見できる。艱難を乗り越えたのは遺訓によるところが少なくない。
そのいくつかを抜粋する。
・同年代と遊んでも得るものは少ない。どうせなら、年上と付き合え。
・お前ひとりが出来ることは高がが知れている。だから、できる人間を使える人間になれ。
・まかぬ種は生えない。
・感謝を忘れるな、礼節を欠くな。
・自分のしたことは必ず自分に返って来る。一流の店に行け、そこには地元の一流の人がいる。
・借金をしたら最後の一円まで返さないと次の成功はない。
・信義を通せ、逃げるな。
・身近な所から商売を始めるな。
・10年頑張れば固定客がつかめる。それまで自分の力を尽くせ。
・相談できる人を持て、人生の宝物になる。そして感謝の気持ちと礼節を忘れるな。
・読書で得た知識が何らかの縁によってよみがえり示唆を与えてくれる。
特別な言説ではない。当たり前のことどもである。しかしこれを素直に実践して苦境を切り拓いてきたところにこ御仁の父君へのリスペクとDNAを感じる。
23年8月に子息に代表権を譲ったとある。ひとまず、衷心より慶祝の辞を贈らせて戴こう。
時は誰人にも平等に流れる。だが、どのような時を刻むかはそれそれの心で決まる。行動で決まる。