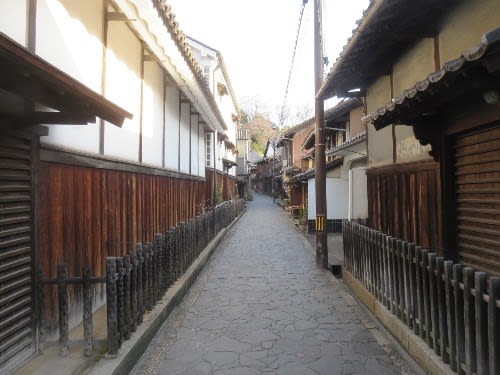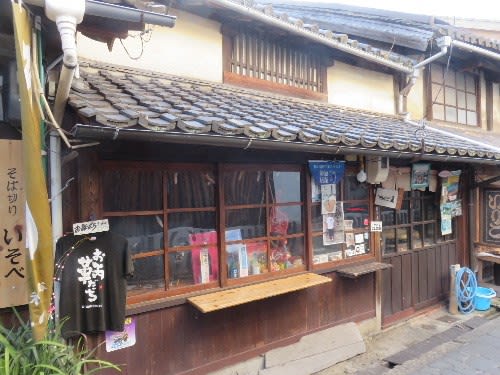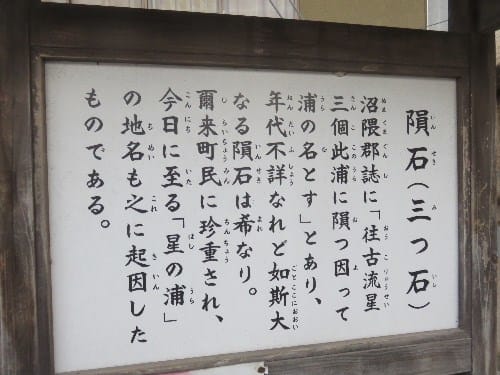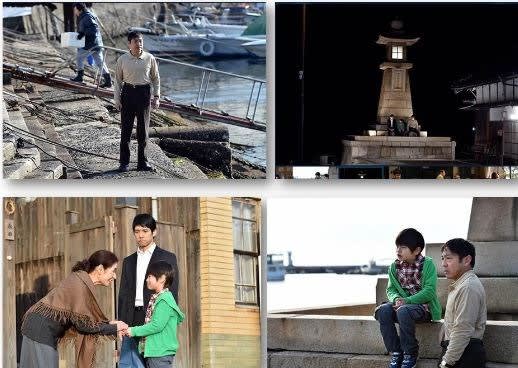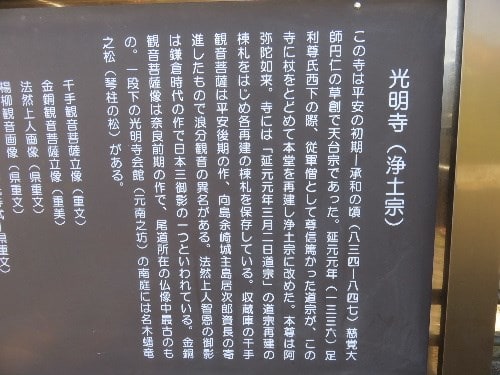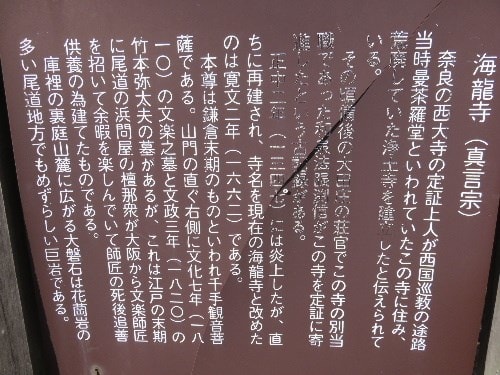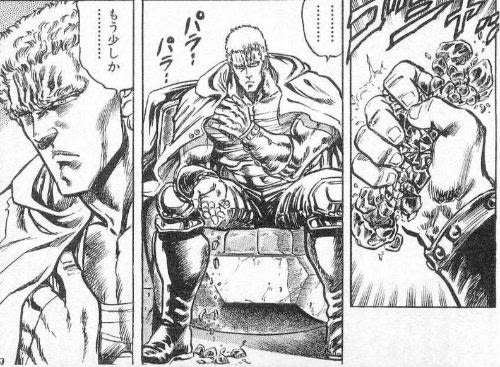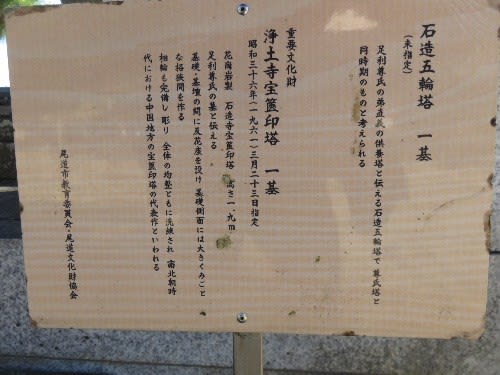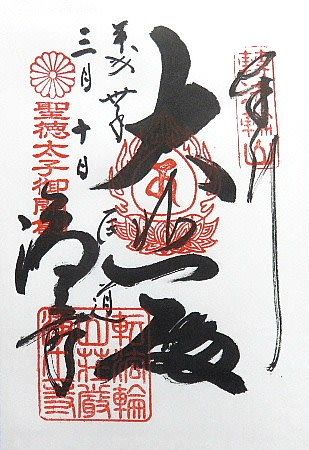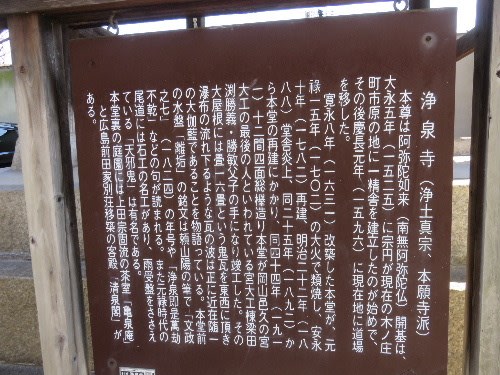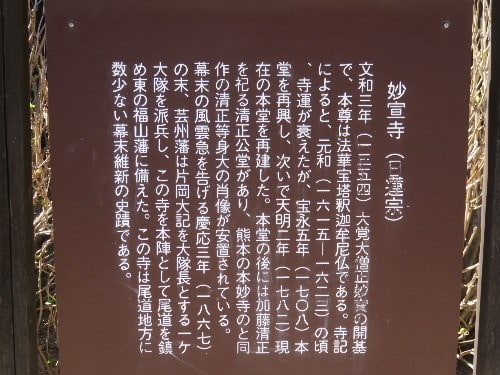続いて本日最大のメインである浄土寺。
ここへ行く道は相当狭いということが、
ネットで書いてあったので商店街の有料駐車場に停め、
徒歩で浄土寺へ向かった。
【西郷四郎像】

もうすぐ浄土寺に到着という所で、
このような像を発見。
彼は講道館四天王の一人で、
姿三四郎のモデルとなった柔道家なのは有名ですね。
そういや近くに西郷寺というのがあったな。
徒歩であの坂を登るのが嫌だったので行かなかったけど。
【西郷四郎逝去の地碑】

大正9年(1920)妻の郷里である尾道に訪れ、
浄土寺の末寺吉祥坊(廃寺)で神経痛の療養をしていたが、
大正11年(1922)12月23日57歳で死去した地。
【裏門】

左手に見えるのが重要文化財の裏門です。
すぐ近くに平行して山門があるのに、
裏門とはこれいかに。
無料駐車場はここを通り、
先に進むと境内に停めれます。
ネットでは細い道と書いてあったが、
これぐらいなら余裕ですね。
車で境内まで行ったら良かったと後悔した。(^^;
所在地:広島県尾道市東久保町20-28
宗派:真言宗泉涌寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
創建:推古天皇24年(616)
開基:(伝)聖徳太子
札所:中国三十三観音霊場、尾道七佛めぐり、備後西国三十三観音霊場、尾道社寺めぐり
【縁起】
転法輪山大乗律院荘厳浄土寺は遠く飛鳥の昔、推古天皇24年(616)、
聖徳太子の開基と伝えています。
鎌倉時代の終わりに西大寺の定証上人が西国教化の途すがら、
浄土寺末の曼荼羅堂(現海龍寺)に安居していた頃の浄土寺は、
堂塔を守る人さえもいない有様でした。
そこで上人は里人の懇請を容れて浄土寺の再興を発願し、
尾道浦の大檀那光阿弥陀仏らの援助によって嘉元元年(1303)から、
同四年(1306)にかけて堂塔を造営し華やかな落慶供養を営みました。
ところが竣工後わずか二十年の正中2年(1325)に至って、
諸堂宇悉く炎上という悲運に見 舞われましたが、
嘉暦元年(1326)には早くも尾道の邑老道蓮・道性夫妻が、
堂宇再興の大願を発して金堂・山門・多宝塔 ・阿弥陀堂等を再建
その後は一度も災禍にも遭わず、
六百余年の風雪を凌いで今日までその威容を保っております。
【山門】

南北朝時代に再建された重要文化財。
【境内】

浄土寺といえばこの写真をよく見ます。
左が重文の阿弥陀堂で右が国宝の多宝塔です。
素晴らしい。(^^
尾道に来た甲斐がありますよ。

このお寺にはハトが非常に多い。
ハトは糞害もあって嫌われるのですが、
このお寺では大切にされているようですね。
【本堂】


嘉暦2年(1327年)或いは元徳元年(1329)に再建された国宝。
参拝した時は重文かと思ってましたが、
国宝だったのね。(^^
まずは外陣に入ってお参り。
係りのおっちゃんに拝観料600円を支払い、
本堂と阿弥陀堂内陣、方丈、庫裏、客殿、庭園を拝観。
まずは本堂の内陣に入れていただき、
荘厳な観音堂のような雰囲気を堪能。
御本尊を除く諸仏や足利尊氏公の肖像画も見れました。
係りのおっちゃんが細かく説明していただき、
いろいろ話しがはずむ。
ここだけで600円の元を取った。(^^
堂内は撮影不可でした。
続いて阿弥陀堂の内陣へ。
入ってすぐに蓮如上人筆の六字名号の掛け軸。
浄土真宗の蓮如上人のモノが何故あるのか、
よく分からないそうです。
中央には阿弥陀三尊像が祀られていました。
特筆すべきは天井近くの四方の壁に、
卍崩し組み子細工がされていたこと。
普通に見ると卍に見えるのに、
離れたり光加減により形が変わったり、
赤が緑に見えたりする。
目の錯覚を利用した視覚トリックなんだろうけど、
これは本当に不思議でしたね。
これは是非とも撮影したかったけど、
残念ながら撮影不可。
続いて方丈と庭園へ。
【歓喜天】

方丈横に歓喜天が祀られているお堂があります。
こちらはお寺の方でも滅多に中に入れないそうです。

お堂の下を通って方丈へ。
【方丈】

元禄3年(1690)建立の重要文化財。
重厚な上段の間が見事でしたね。
方丈の中も残念ながら撮影不可。
係りの方の説明は方丈で終了。
庭園や客殿は自由に拝観することが出来ました。
【方丈庭園】


建仁寺で見れるような禅宗っぽい庭園です。
奥に見えるのが正徳2年(1712)に建立された唐門です。
庭園は撮影OKでした。
【名勝庭園】


方丈横にはもう一つの庭園があります。

こちらは先ほどの方丈庭園とは違った築山泉水庭園で、
多くの石を計算され尽くして配置した見事なものです。
庭を見ていると京都の大寺院に参拝しているような錯覚を覚える。
【露滴庵】

これはあの秀吉公が桃山城に建てた茶室燕庵を移築したもの。
重要文化財。
【客殿】

享保4年(1719)建立された重要文化財。
こちらも中を拝観出来ますが、
撮影不可でした。
【中庭】

【庫裏】


庫裏は撮影OKでした。

梁も見事なものです。
享保4年(1719)建立された重要文化財。

庫裏の玄関に出て拝観終了。
いや~実に見所たっぷりな拝観であった。
観光客は千光寺に皆さん行かれますが、
神社仏閣巡りが目的なら圧倒的に浄土寺の方が満足度は高い。
千光寺は確かに景色は最高に素晴らしいけどね。
【宝物館】

宝物館はプラス400円で拝観可能ですが、
今回は時間の都合上、拝観はしませんでした。
次回は必ず。
とりあえず長くなりましたので続きは明日。