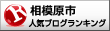世界遺産登録を目指す称名寺さんを後に、野島公園を目指します。ここに伊藤博文邸があるのです。
その道々、歴史ポイントを巡ります。
 薬王寺
薬王寺
薬王寺さんは称名寺の赤門と道を挟んであります。
今は上の画像の如く、どおってことないお寺ですが、ここは源頼朝の弟、源範頼の別邸だった場所です。範頼の位牌もここにある。
細い道を南下して、次のポイントは。
 金沢八幡神社です。
金沢八幡神社です。
金沢文庫の古文書に「称名寺の金堂屋根を葺くために檜皮を八幡宮の前で荷揚げした」と記されてます。神社の前には瀬戸の内海が広がり、八幡河岸と呼ばれる船着き場がありました。」
そうなのです。かつて称名寺から南は陸でなく内海だったのです。だから、金沢文庫駅から称名寺への道は上り坂だったのですね。

金沢八幡神社は、付近の総鎮守として祀られてます。
その次の目的地は伝心寺さんだったのですが、迷った!挙げ句に曲がり角を見つけられず南下を続けてしまい、次の次の目的地に着いてしまった!!
あれ~~??
 次の次の目的地だった安立寺さんです。
次の次の目的地だった安立寺さんです。
安立寺さんは日蓮宗の寺でして、下総から鎌倉に向かう日蓮と富木胤継が船中で法論をしたが決着が着かず金沢に着岸して悟明庵に移ってもさらに問答を続けたといいます。この時日蓮の教えに感銘を受けた悟明は、弟子となり安立院日悟と名前を改めて、安立寺を開基したと伝えられます。上の画像の碑は、”船中問答着岸の霊場”とあります。

現在ではこじんまりとしたお寺で、山門をくぐると右半分は全て墓地となってます。とりあえず参拝して山門に戻るとダンナが「あそこに古い建物がある」というので墓地に足を向けたのですが…。
「あれは、隣の龍華寺さんの建物じゃんっ!!」ってことで引き返して道を南下。改めて龍華寺さんへ向かいます。

龍華寺さんは結構大きなお寺でした。

実は境内にはぼたんが沢山あります。春、4月末かな?その頃来るのが望ましい。
 室町時代(天文10年)の鐘。神奈川県の重要文化財。
室町時代(天文10年)の鐘。神奈川県の重要文化財。
龍華寺に隣接してもう一つ神社があります。
 洲崎神社です。
洲崎神社です。
この神社もこじんまり。元は現在野口英世記念館のあるあたりにあったのですが、応長元年(1311)に一帯が大波に流されて滅び、住民と共に移住して神社もここに移動しました。現在の社は天保9年の再建。ところが明治維新後の神仏混交で廃せられ、道路回収などで現在の場所に移転したそうです。由緒を書いた説明板があったのですが、これが小難しく抜粋編集してみた。
さて。途切れることなく続く歴史ポイント。楽しみにしてた明治憲法草創の碑に到着です。
私、明治憲法を作ったのって、小田原の伊藤邸だと思ってたのですが、それをちらっと称名寺さんのボランティアガイドさんに言ったら、全力否定されてしまった。
や。こっちが本家らしいね。その所、明日の記事で解説します。
その道々、歴史ポイントを巡ります。
 薬王寺
薬王寺薬王寺さんは称名寺の赤門と道を挟んであります。
今は上の画像の如く、どおってことないお寺ですが、ここは源頼朝の弟、源範頼の別邸だった場所です。範頼の位牌もここにある。
細い道を南下して、次のポイントは。
 金沢八幡神社です。
金沢八幡神社です。金沢文庫の古文書に「称名寺の金堂屋根を葺くために檜皮を八幡宮の前で荷揚げした」と記されてます。神社の前には瀬戸の内海が広がり、八幡河岸と呼ばれる船着き場がありました。」
そうなのです。かつて称名寺から南は陸でなく内海だったのです。だから、金沢文庫駅から称名寺への道は上り坂だったのですね。

金沢八幡神社は、付近の総鎮守として祀られてます。
その次の目的地は伝心寺さんだったのですが、迷った!挙げ句に曲がり角を見つけられず南下を続けてしまい、次の次の目的地に着いてしまった!!
あれ~~??
 次の次の目的地だった安立寺さんです。
次の次の目的地だった安立寺さんです。安立寺さんは日蓮宗の寺でして、下総から鎌倉に向かう日蓮と富木胤継が船中で法論をしたが決着が着かず金沢に着岸して悟明庵に移ってもさらに問答を続けたといいます。この時日蓮の教えに感銘を受けた悟明は、弟子となり安立院日悟と名前を改めて、安立寺を開基したと伝えられます。上の画像の碑は、”船中問答着岸の霊場”とあります。

現在ではこじんまりとしたお寺で、山門をくぐると右半分は全て墓地となってます。とりあえず参拝して山門に戻るとダンナが「あそこに古い建物がある」というので墓地に足を向けたのですが…。
「あれは、隣の龍華寺さんの建物じゃんっ!!」ってことで引き返して道を南下。改めて龍華寺さんへ向かいます。

龍華寺さんは結構大きなお寺でした。

実は境内にはぼたんが沢山あります。春、4月末かな?その頃来るのが望ましい。
 室町時代(天文10年)の鐘。神奈川県の重要文化財。
室町時代(天文10年)の鐘。神奈川県の重要文化財。龍華寺に隣接してもう一つ神社があります。
 洲崎神社です。
洲崎神社です。この神社もこじんまり。元は現在野口英世記念館のあるあたりにあったのですが、応長元年(1311)に一帯が大波に流されて滅び、住民と共に移住して神社もここに移動しました。現在の社は天保9年の再建。ところが明治維新後の神仏混交で廃せられ、道路回収などで現在の場所に移転したそうです。由緒を書いた説明板があったのですが、これが小難しく抜粋編集してみた。
さて。途切れることなく続く歴史ポイント。楽しみにしてた明治憲法草創の碑に到着です。
私、明治憲法を作ったのって、小田原の伊藤邸だと思ってたのですが、それをちらっと称名寺さんのボランティアガイドさんに言ったら、全力否定されてしまった。
や。こっちが本家らしいね。その所、明日の記事で解説します。