場所は横浜市金沢区。野島公園内。
旧伊藤博文金沢別荘は、明治31年(1898)に建てられた茅葺き寄せ棟屋根の田舎風海浜別荘建築です。
明治期、富岡・金沢は東京近郊の海浜別荘地として人気となりました。その後、大磯・葉山など湘南地方が人気となります。
平成18年(2006)11月、横浜市の有形文化財に指定。
建物の老朽化が著しかったことから、平成19年(2007)解体工事・調査を行い、現存しない部分を含め創建当時の姿に復元することになりました。平成20年(2008)6月より工事に着手。平成21年(2009)10月に庭園とあわせて竣工しました。
!!ってことはこれ、復元建築なのですね。へえ~へえ~へえ~~。
実はどこまでブログで画像を紹介していいものだかわからないんですけど、取りあえず展示物は除きますので、興味のある方は現地へ足を運んで下さい。
私が興味を引かれたのは便所です。3カ所もあった!し~か~も~。便所にはランクがあった。客用の便所は、便器が本漆仕上げでしたよ。便器の周りは畳張り!!すごいよね。

ちなみに上の画像は本漆の便器ではありません。
伊藤邸を訪れた数日後に、世田谷区の旧小坂家住宅を訪問しました。そこの便所は大便器・小便器共に有田焼で出来た美しい陶磁器製だったのよ。便器にも時代の変遷があるのね。
や~日本に来た外国人にとってしゃがんで使用する和風便器は使用法が分からない謎の便器に見えるそうですよ。そんな事で不思議の国ニッポン!と驚かれても困っちゃうんですけど、確かにしゃがんで使う便器はアラブを旅した時以外見かけたことないんだよ。そいうや、映画の『テルマエ・ロマエ』ではお尻を洗えるタイプの便器を使ったローマ人が魂消てましたが…。明治期の便所もなかなか興味深かったです。
あ。そうだ。興味深いと言えば…。

お風呂です。サワラ材(まな板なんかに利用されてますね)の木製箱風呂です。お風呂というより、湯殿ですね。なんと、脱衣場・湯殿・釜場に別れてます。ただし、大正期にはサワラ材から台湾ヒノキの板風呂に交換されてます。更にそれから10年後にはコンクリートを流しタイルを貼る工事が行われました。やっぱ水回りは寿命が短かったのね。
あと驚愕したのが、和紙1枚の断熱の優秀さです。

上の画像を見てください。手前はガラスが入ってるのですが、奥の部屋は障子が見えるでしょう?行ってみたら、障子を開いたら直接外でしたっ!!そう障子だけが奥内と屋外を隔ててるんですよっ!!
障子は日光をそこそと通すので、室内の視界は確保出来ます。や。何を感動してるんだって聞かれると困るんですけど、障子の外側には廊下があって、廊下と外は窓ガラスで隔ててるのが私の実家であり嫁入り先の家です。障子が直接外界と奥内を隔ててるのを見てびっくりしちゃったのよ。

内庭の周りも障子が!!

これって、障子ってゆーか、和紙って丈夫だったのかな?雨とか直接受けるような気もするが…。
ちなみに、客間の周りだけ窓ガラスがあります。

明治期の窓ガラスは高価だったのでしょうね。下世話な話、窓ガラスって当時いくら位だったのでしょうか?つーか、国内生産始まってたのかな~?
あんまり知識がないのが残念な見学でした。
ちなみに、伊藤邸の庭には牡丹園があります。ボタンの咲く頃が一番の訪問時期ですね。
ちなみに、見学は無料。
休館日は毎月第一・第三月曜日。年末年始(12月29日-1月3日)。
開館時間は9:30-16:30となってます。
本日の予定ではとっくに鎌倉へ移動してるハズでしたが、称名寺さんで時間をかけ過ぎたのが敗因か、既に時刻は12時半です。これはマズい。ご飯にせねば。
「ここで提案です。海を見ながらお昼にするか?海は見えないけどベンチがあるここで食べるか?」とダンナに尋ねましたれば、12月に入っての海辺は寒いということで、伊藤邸の外にあったベンチでもそもそとあんパンと熱いお茶をいただきました。
さて、移動です。金沢八景駅へ向かいます。ところが…。

晴れてたハズの空が一転、嵐のように風は強くなり暗くなり…。どないなっとんねんっ!!
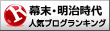 幕末・明治(日本史) ブログランキングへ
幕末・明治(日本史) ブログランキングへ
旧伊藤博文金沢別荘は、明治31年(1898)に建てられた茅葺き寄せ棟屋根の田舎風海浜別荘建築です。
明治期、富岡・金沢は東京近郊の海浜別荘地として人気となりました。その後、大磯・葉山など湘南地方が人気となります。
平成18年(2006)11月、横浜市の有形文化財に指定。
建物の老朽化が著しかったことから、平成19年(2007)解体工事・調査を行い、現存しない部分を含め創建当時の姿に復元することになりました。平成20年(2008)6月より工事に着手。平成21年(2009)10月に庭園とあわせて竣工しました。
!!ってことはこれ、復元建築なのですね。へえ~へえ~へえ~~。
実はどこまでブログで画像を紹介していいものだかわからないんですけど、取りあえず展示物は除きますので、興味のある方は現地へ足を運んで下さい。
私が興味を引かれたのは便所です。3カ所もあった!し~か~も~。便所にはランクがあった。客用の便所は、便器が本漆仕上げでしたよ。便器の周りは畳張り!!すごいよね。

ちなみに上の画像は本漆の便器ではありません。
伊藤邸を訪れた数日後に、世田谷区の旧小坂家住宅を訪問しました。そこの便所は大便器・小便器共に有田焼で出来た美しい陶磁器製だったのよ。便器にも時代の変遷があるのね。
や~日本に来た外国人にとってしゃがんで使用する和風便器は使用法が分からない謎の便器に見えるそうですよ。そんな事で不思議の国ニッポン!と驚かれても困っちゃうんですけど、確かにしゃがんで使う便器はアラブを旅した時以外見かけたことないんだよ。そいうや、映画の『テルマエ・ロマエ』ではお尻を洗えるタイプの便器を使ったローマ人が魂消てましたが…。明治期の便所もなかなか興味深かったです。
あ。そうだ。興味深いと言えば…。

お風呂です。サワラ材(まな板なんかに利用されてますね)の木製箱風呂です。お風呂というより、湯殿ですね。なんと、脱衣場・湯殿・釜場に別れてます。ただし、大正期にはサワラ材から台湾ヒノキの板風呂に交換されてます。更にそれから10年後にはコンクリートを流しタイルを貼る工事が行われました。やっぱ水回りは寿命が短かったのね。
あと驚愕したのが、和紙1枚の断熱の優秀さです。

上の画像を見てください。手前はガラスが入ってるのですが、奥の部屋は障子が見えるでしょう?行ってみたら、障子を開いたら直接外でしたっ!!そう障子だけが奥内と屋外を隔ててるんですよっ!!
障子は日光をそこそと通すので、室内の視界は確保出来ます。や。何を感動してるんだって聞かれると困るんですけど、障子の外側には廊下があって、廊下と外は窓ガラスで隔ててるのが私の実家であり嫁入り先の家です。障子が直接外界と奥内を隔ててるのを見てびっくりしちゃったのよ。

内庭の周りも障子が!!

これって、障子ってゆーか、和紙って丈夫だったのかな?雨とか直接受けるような気もするが…。
ちなみに、客間の周りだけ窓ガラスがあります。

明治期の窓ガラスは高価だったのでしょうね。下世話な話、窓ガラスって当時いくら位だったのでしょうか?つーか、国内生産始まってたのかな~?
あんまり知識がないのが残念な見学でした。
ちなみに、伊藤邸の庭には牡丹園があります。ボタンの咲く頃が一番の訪問時期ですね。
ちなみに、見学は無料。
休館日は毎月第一・第三月曜日。年末年始(12月29日-1月3日)。
開館時間は9:30-16:30となってます。
本日の予定ではとっくに鎌倉へ移動してるハズでしたが、称名寺さんで時間をかけ過ぎたのが敗因か、既に時刻は12時半です。これはマズい。ご飯にせねば。
「ここで提案です。海を見ながらお昼にするか?海は見えないけどベンチがあるここで食べるか?」とダンナに尋ねましたれば、12月に入っての海辺は寒いということで、伊藤邸の外にあったベンチでもそもそとあんパンと熱いお茶をいただきました。
さて、移動です。金沢八景駅へ向かいます。ところが…。

晴れてたハズの空が一転、嵐のように風は強くなり暗くなり…。どないなっとんねんっ!!



















