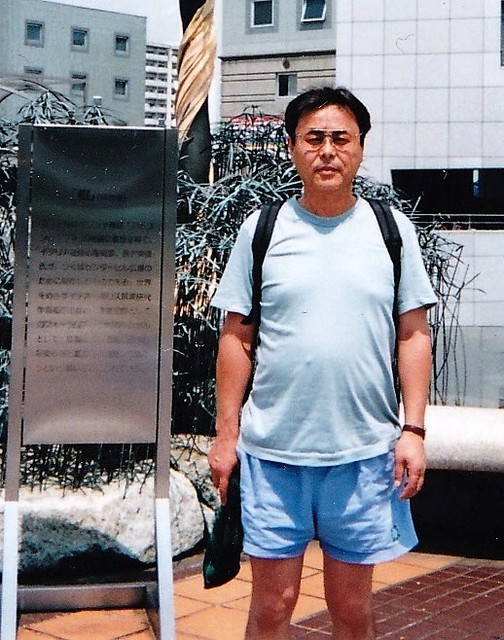昨日の続きです。
“東大寺大仏殿”のような大屋根に驚き、興奮しながら大屋根を見据えて歩いていると、手前の処で鳥居を見つけました。
素通りすることはできません。兎に角、覗いて見る事にしました。諏訪神社とあります。

それなりに、なかなかの神社です。奥に、目指す大屋根のお寺が見えます。

この諏訪神社は、享保年間(1716年~1736年)の創建だそうです。
“富士塚”がありました。

富士塚は江戸時代に盛んに造られたようですが、ここの富士塚は大正9年に造られたと有ります。かなり新しいものです。

小御嶽神社が祀られています。

富士塚の必需品である“富士山の溶岩”です。これってホントに富士山から運んできたのでしょうか?
いゃ。神様を疑ってはいけません、罰が当たります。

もしかして、昔は“富士塚”を専門に扱う、造営業者があったかも知れません。
本殿は残念ながら、鉄筋コンクリート製です。

キンキラキンに、極彩色の塗装も日本です。

この際、狛犬も極彩色で派手に決めて見たらと思うのですが、狛犬は本殿と異なり、かなり年代が経っているようです。

本殿の内部をガラス越しに覗いたのですが、神社と云うよりも、お寺の本堂に見えます。神社は質素で自然な白木造りが似合います。

どうですか?この写真、なかなかでしョ! どう見ても、千葉の匂いが漂う総武線平井駅の近所とは思えません。

奈良の香りがしてきます。
諏訪神社には失礼ですが、早く、隣に行きたくなりました。
それでは、また明日。
“東大寺大仏殿”のような大屋根に驚き、興奮しながら大屋根を見据えて歩いていると、手前の処で鳥居を見つけました。
素通りすることはできません。兎に角、覗いて見る事にしました。諏訪神社とあります。

それなりに、なかなかの神社です。奥に、目指す大屋根のお寺が見えます。

この諏訪神社は、享保年間(1716年~1736年)の創建だそうです。
“富士塚”がありました。

富士塚は江戸時代に盛んに造られたようですが、ここの富士塚は大正9年に造られたと有ります。かなり新しいものです。

小御嶽神社が祀られています。

富士塚の必需品である“富士山の溶岩”です。これってホントに富士山から運んできたのでしょうか?
いゃ。神様を疑ってはいけません、罰が当たります。

もしかして、昔は“富士塚”を専門に扱う、造営業者があったかも知れません。
本殿は残念ながら、鉄筋コンクリート製です。

キンキラキンに、極彩色の塗装も日本です。

この際、狛犬も極彩色で派手に決めて見たらと思うのですが、狛犬は本殿と異なり、かなり年代が経っているようです。

本殿の内部をガラス越しに覗いたのですが、神社と云うよりも、お寺の本堂に見えます。神社は質素で自然な白木造りが似合います。

どうですか?この写真、なかなかでしョ! どう見ても、千葉の匂いが漂う総武線平井駅の近所とは思えません。

奈良の香りがしてきます。
諏訪神社には失礼ですが、早く、隣に行きたくなりました。
それでは、また明日。