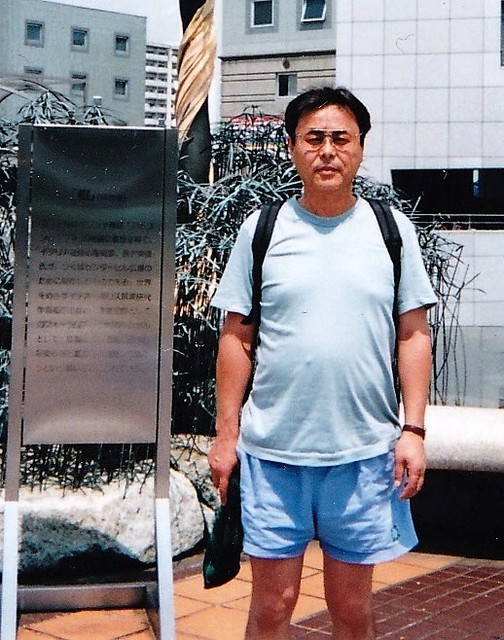昨日の続きです。
前回、最後にちょっとだけ触れた“北朝鮮への帰還事業”ですが、“キューポラのある街”の作品評価で必ずこの事が問題にされます。
帰還事業は朝鮮戦争が1953年12月に“停戦的休戦状態”に入ってから、6年後の1959年12月より始まりました。終了したのが1984年、四半世紀も続いていたのです。帰還者は93,340人で、そのうち7千人弱が日本国籍を持つ子供や日本人妻だったそうです。
それで、映画のなかで帰還事業を、それなりに肯定的に取り上げ、北朝鮮を、社会主義を、賛美し、帰還事業を推進する一定の役割を果たしたと、一部では未だに批判や非難が囁かれています。
でも、しかし、帰還事業は、じつは右も左も仲良く推進していたのです。
右からは「人道的配慮を云いつつ厄介払い」として、左からは「社会主義体制の優位性」を宣伝するための手段として、お互いに同床異夢で推進していたのです。
“ジュン”の“子分”も、朝鮮人の父と、日本人の母の間に生まれました。

そして、北朝鮮へ帰還するのですが、

母は一人、日本に残ります。

子分の姉はジュンの友達、

悲しい別れなのです。

未来への明るい希望を抱いて祖国へ帰って行く、そんな雰囲気ではなく、かなり悲壮感漂う情景描写だと思います。
ジュンの子分は途中で汽車を降ります。北朝鮮よりも母親を選びました。でも、しかし、戻って来ると母は何処かに消えていました。何となく、新しい男との、新しい生活を選択したようでした。
それでも、強く明るくたくましく、一人でも生きていけそうな少年です。北朝鮮へ帰らなくて、ホントにヨカッタです。
作品では帰還事業がかなりのウェイトを占めますが、北朝鮮は「地上の楽園」だとか、「衣食住の心配がない」とか、左翼的宣伝は語られてはいません。
いまだから言えることで、あの頃、帰還事業を、それなりに“肯定的”に取り上げたとしても、あの頃、あの帰還事業は、普通の人には、単なる“風景”だったと思います。
映画公開から6年後経った頃、私は社会人になったのですが、会社は浜松町駅から徒歩10分ぐらいのところで、隣は「日本赤十字社」の本社で、交差点の斜め向かいが「愛宕警察署」でした。
会社の前を通って、毎日、毎日、十数人から、時にはその倍程度の在日の人達が、帰還事業に関しての、要求なのか、抗議なのか、幟を立てて日本赤十字の本社に向かうのを、日常的に眼にしていました。
兎に角、日赤の門前のチマチョゴリは普通の日常的な風景で、彼らが毎日、毎日、何のためにあの場に居たのか、まったく覚えていません。
あまり関心がなかったのです、世の中は、政治よりも、経済の時代でした。「キューポラのある街」を観て、北朝鮮は素晴らしい国だと思った人は、それほど居なかったと思います。
この映画は、街のかたすみで、貧しくともけなげに、いろいろな困難に立ち向かい、力強く生き、少女から女に成長していく過程を、アイドル女優の吉永小百合が初々しく演じた“アイドル映画”なのです。
キューポラのある街川口市も、貧乏も、北朝鮮帰還事業も、すべて吉永小百合がトップアイドルとして世にデビューさせるための、単なる背景でしかないのです。
背景は、暗ければ、暗いほど、“小百合ちゃん”は輝くのです。
こんなこと云ったら、監督の浦山桐郎さん、脚本の今村昌平さんに怒られる?
次回は、世評的には、まったくギャクの、この作品の、右翼的と云うか、反動的と云うか、資本主義的と云うか、反組合的と云うか、そんな側面を大胆に批判したいと思います。
それでは、また明日。
前回、最後にちょっとだけ触れた“北朝鮮への帰還事業”ですが、“キューポラのある街”の作品評価で必ずこの事が問題にされます。
帰還事業は朝鮮戦争が1953年12月に“停戦的休戦状態”に入ってから、6年後の1959年12月より始まりました。終了したのが1984年、四半世紀も続いていたのです。帰還者は93,340人で、そのうち7千人弱が日本国籍を持つ子供や日本人妻だったそうです。
それで、映画のなかで帰還事業を、それなりに肯定的に取り上げ、北朝鮮を、社会主義を、賛美し、帰還事業を推進する一定の役割を果たしたと、一部では未だに批判や非難が囁かれています。
でも、しかし、帰還事業は、じつは右も左も仲良く推進していたのです。
右からは「人道的配慮を云いつつ厄介払い」として、左からは「社会主義体制の優位性」を宣伝するための手段として、お互いに同床異夢で推進していたのです。
“ジュン”の“子分”も、朝鮮人の父と、日本人の母の間に生まれました。

そして、北朝鮮へ帰還するのですが、

母は一人、日本に残ります。

子分の姉はジュンの友達、

悲しい別れなのです。

未来への明るい希望を抱いて祖国へ帰って行く、そんな雰囲気ではなく、かなり悲壮感漂う情景描写だと思います。
ジュンの子分は途中で汽車を降ります。北朝鮮よりも母親を選びました。でも、しかし、戻って来ると母は何処かに消えていました。何となく、新しい男との、新しい生活を選択したようでした。
それでも、強く明るくたくましく、一人でも生きていけそうな少年です。北朝鮮へ帰らなくて、ホントにヨカッタです。
作品では帰還事業がかなりのウェイトを占めますが、北朝鮮は「地上の楽園」だとか、「衣食住の心配がない」とか、左翼的宣伝は語られてはいません。
いまだから言えることで、あの頃、帰還事業を、それなりに“肯定的”に取り上げたとしても、あの頃、あの帰還事業は、普通の人には、単なる“風景”だったと思います。
映画公開から6年後経った頃、私は社会人になったのですが、会社は浜松町駅から徒歩10分ぐらいのところで、隣は「日本赤十字社」の本社で、交差点の斜め向かいが「愛宕警察署」でした。
会社の前を通って、毎日、毎日、十数人から、時にはその倍程度の在日の人達が、帰還事業に関しての、要求なのか、抗議なのか、幟を立てて日本赤十字の本社に向かうのを、日常的に眼にしていました。
兎に角、日赤の門前のチマチョゴリは普通の日常的な風景で、彼らが毎日、毎日、何のためにあの場に居たのか、まったく覚えていません。
あまり関心がなかったのです、世の中は、政治よりも、経済の時代でした。「キューポラのある街」を観て、北朝鮮は素晴らしい国だと思った人は、それほど居なかったと思います。
この映画は、街のかたすみで、貧しくともけなげに、いろいろな困難に立ち向かい、力強く生き、少女から女に成長していく過程を、アイドル女優の吉永小百合が初々しく演じた“アイドル映画”なのです。
キューポラのある街川口市も、貧乏も、北朝鮮帰還事業も、すべて吉永小百合がトップアイドルとして世にデビューさせるための、単なる背景でしかないのです。
背景は、暗ければ、暗いほど、“小百合ちゃん”は輝くのです。
こんなこと云ったら、監督の浦山桐郎さん、脚本の今村昌平さんに怒られる?
次回は、世評的には、まったくギャクの、この作品の、右翼的と云うか、反動的と云うか、資本主義的と云うか、反組合的と云うか、そんな側面を大胆に批判したいと思います。
それでは、また明日。