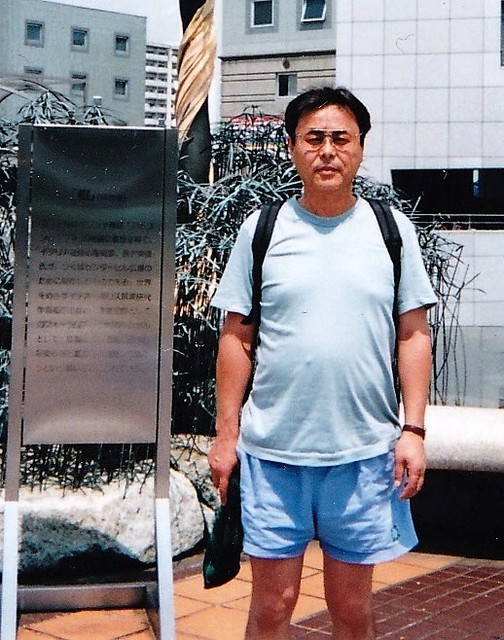昨日の続きです。
観音堂から見る大銀杏、大変立派で堂々としています。この風格に対して“目隠銀杏”は失礼だと思います。そんな役割は担っておりません。
見上げながら周囲を一周します。どう見ても、これは樹齢600年はありそううです。やっぱり、これは、どう見ても御神木の佇まい。

でも、ここは天台宗の東漸寺。しかし、やっぱり、幹の傍に蓮華を手にした観音様が居られました。神木ではなく“御佛木?”でした。

市指定文化財の“仁王門” 教育委員会の説明によれば、元禄3年(1690年)に吉田村の清左衛門さん寄進で、様式は“単層八脚門”とあります。“柱が八本の平屋建て”です。

チョッコシ知識をひけらかして、チョッコシ詳しく表現すると“単層八脚三間一戸切妻茅葺仁王門”となります。
でも、この柱の“八脚”ですが、八脚門と云っても、見た目には“十二脚”なのです、中心部にある4本の柱は補助柱で数に入っていないのです。どう見ても、12本で屋根を支えていると思うのです。
12本は同等に、しっかり屋根を支えているのに、“八脚門”と分類され、4本は数のうちに入っていないのです。中心の4本が聴いたら絶対に納得しないと思います。
わたし的には、十二本の柱のすべてが平等との認識に基づき、“単層十二脚三間一戸切妻茅葺仁王門”と命名します。これで背面の4本は納得し、末永く屋根を支え続けると思います。

茅葺きで、これだけの門、立派な門です。この柱が数に入っていないのです・

仁王門と参道の石畳・・・、ズレてます。

たぶん、創建当時の柱や板なのでしょう。三百有余年、風雨に晒され、日に照らされ、イイ肌合いになっています。

礎石に柱は直置きはしないようです。柱の腐食防止なのか? それとも柱の高さ調整のスペーサーなのか?

いいお天気です。参拝日和です。のんびりです。

それでは、天台宗 興山 東漸寺を後にします。

それでは、また明日。
観音堂から見る大銀杏、大変立派で堂々としています。この風格に対して“目隠銀杏”は失礼だと思います。そんな役割は担っておりません。
見上げながら周囲を一周します。どう見ても、これは樹齢600年はありそううです。やっぱり、これは、どう見ても御神木の佇まい。

でも、ここは天台宗の東漸寺。しかし、やっぱり、幹の傍に蓮華を手にした観音様が居られました。神木ではなく“御佛木?”でした。

市指定文化財の“仁王門” 教育委員会の説明によれば、元禄3年(1690年)に吉田村の清左衛門さん寄進で、様式は“単層八脚門”とあります。“柱が八本の平屋建て”です。

チョッコシ知識をひけらかして、チョッコシ詳しく表現すると“単層八脚三間一戸切妻茅葺仁王門”となります。
でも、この柱の“八脚”ですが、八脚門と云っても、見た目には“十二脚”なのです、中心部にある4本の柱は補助柱で数に入っていないのです。どう見ても、12本で屋根を支えていると思うのです。
12本は同等に、しっかり屋根を支えているのに、“八脚門”と分類され、4本は数のうちに入っていないのです。中心の4本が聴いたら絶対に納得しないと思います。
わたし的には、十二本の柱のすべてが平等との認識に基づき、“単層十二脚三間一戸切妻茅葺仁王門”と命名します。これで背面の4本は納得し、末永く屋根を支え続けると思います。

茅葺きで、これだけの門、立派な門です。この柱が数に入っていないのです・

仁王門と参道の石畳・・・、ズレてます。

たぶん、創建当時の柱や板なのでしょう。三百有余年、風雨に晒され、日に照らされ、イイ肌合いになっています。

礎石に柱は直置きはしないようです。柱の腐食防止なのか? それとも柱の高さ調整のスペーサーなのか?

いいお天気です。参拝日和です。のんびりです。

それでは、天台宗 興山 東漸寺を後にします。

それでは、また明日。