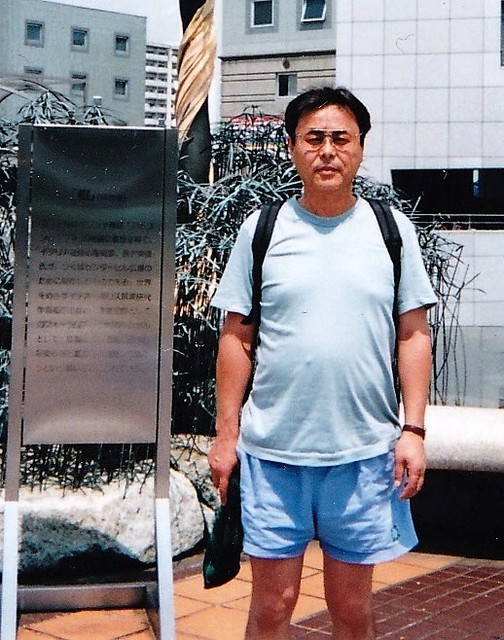先週の続きです。
先週は、参道、仁王門、大銀杏、観音堂、の何故か?何故か?問題が解決しましたので、これより、じっくり、落ち着いて、境内の観察です。
先ずは、大銀杏舐めで観音堂の景色を味わいます。やっぱり「目隠し銀杏」は目隠しの効果はなさそうです。
観音堂の脇にも大木、前には石灯籠が二対、手前の方が古いようです。

景色を味わった後はお参りです。頭を下げた後は、頭を持ち上げ「室町時代末期から江戸時代初期の雰囲気を止めている」向拝の“木鼻”を観察します。

それとなく、どことなく、室町末期から江戸初期の雰囲気が漂っているような、いないような。

横組みの先端が、何となく、そのままでは、寂しいような、味気ないような、そんな処から始まったのでしょう。木の端が、木の鼻で、飾り端。
それにしても、横組みの端に、わざわざ別の木を継ぎ足して彫刻を施しています。始めは横組みの木に彫刻していたのが、段々と凝り始めて表現が複雑になり、別の木を足してまで装飾を施す、判りますその気持ち。
こちらの大木の枝振りもなかなかのものです。何か、手を広げ、足を広げ大向こうに見得を切っているような・・・。

幹には空洞があり、

仏様が居ります。何か、こういう自然の空間が祠の始まりの様な気がします。ふつう祠に祀られるのは神様ですが、仏様が居られても、まったく問題ありません。
小さくて可愛い仏様、とても自然に、手を合わせたくなります。

こちらは古い方の石灯籠です。

“明和六年”とあり、下に“陰陽五行説”表記で“巳丑の歳”とあります。明和六年は1769年で241年前です。“巳丑の歳”も1769年であっていました。間違える分けないか。

制作者は、“石工 江戸八丁堀 和泉屋”とあります。

こういうものは、江戸で造って石屋が運んで来るのか? 地元の運送屋さんが江戸に取りに行くのか? それとも、石屋が出張して来て彫るのでしょうか?
こちらにも、小さなお堂が。

東漸寺、まだ、まだ、いろいろありそうです。
それでは、また明日。
先週は、参道、仁王門、大銀杏、観音堂、の何故か?何故か?問題が解決しましたので、これより、じっくり、落ち着いて、境内の観察です。
先ずは、大銀杏舐めで観音堂の景色を味わいます。やっぱり「目隠し銀杏」は目隠しの効果はなさそうです。
観音堂の脇にも大木、前には石灯籠が二対、手前の方が古いようです。

景色を味わった後はお参りです。頭を下げた後は、頭を持ち上げ「室町時代末期から江戸時代初期の雰囲気を止めている」向拝の“木鼻”を観察します。

それとなく、どことなく、室町末期から江戸初期の雰囲気が漂っているような、いないような。

横組みの先端が、何となく、そのままでは、寂しいような、味気ないような、そんな処から始まったのでしょう。木の端が、木の鼻で、飾り端。
それにしても、横組みの端に、わざわざ別の木を継ぎ足して彫刻を施しています。始めは横組みの木に彫刻していたのが、段々と凝り始めて表現が複雑になり、別の木を足してまで装飾を施す、判りますその気持ち。
こちらの大木の枝振りもなかなかのものです。何か、手を広げ、足を広げ大向こうに見得を切っているような・・・。

幹には空洞があり、

仏様が居ります。何か、こういう自然の空間が祠の始まりの様な気がします。ふつう祠に祀られるのは神様ですが、仏様が居られても、まったく問題ありません。
小さくて可愛い仏様、とても自然に、手を合わせたくなります。

こちらは古い方の石灯籠です。

“明和六年”とあり、下に“陰陽五行説”表記で“巳丑の歳”とあります。明和六年は1769年で241年前です。“巳丑の歳”も1769年であっていました。間違える分けないか。

制作者は、“石工 江戸八丁堀 和泉屋”とあります。

こういうものは、江戸で造って石屋が運んで来るのか? 地元の運送屋さんが江戸に取りに行くのか? それとも、石屋が出張して来て彫るのでしょうか?
こちらにも、小さなお堂が。

東漸寺、まだ、まだ、いろいろありそうです。
それでは、また明日。