The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
Integrity?
JRCA公開講演会で規格協会技術顧問の古山富也氏が、“審査員が心掛ける倫理的言動―組織とその顧客のために”のテーマで講演されたのですが、そこで 難しい要求事項を避けずに それを巡って被審査側と 対話をすべきだ、とおっしゃっていました。同氏は経営コンサルタントを意識されていましたが、審査とコンサルテーションどこで線引きするのが正しいのでしょうね。
その講演で難しい要求事項として真っ先に挙げられたのが次の54.2b)項でした。
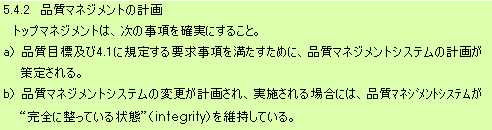
経営者の仕事だから、経営者みずから考えるべきで 我々の仕事ではない、とお思いの方も居るかも知れませんが それを言い出すとISO9001マネジメントは成立しません。
経営者は何をなすべきか。その内の計画の部分ですから重要です。
そして ここのa)項は “品質マネジメント(経営)の仕組を計画せよ”ということで 言っていることは分かりやすいです。ここで “計画”とは “経営意図を実現する仕組を企画し、手順とそのタイムテーブルを定め、確実にする、つまり実行する(品質マネジメントシステムを構築する)。”ということと解釈できます。
加藤重信氏によると a)項は“ISOシステム構築する時の人々”のための“精神的な指針”または“規範”とのことですが、この解釈では狭いような気がします。むしろ 経営者は日常的に システムに問題ないか点検し、活動を計画すると考える方が良く、システムが変更される場合にはb)項を遵守すると いうのは いかがでしょうか。
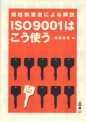
さて問題は次のb)項です。少々分かりづらいのですが、どうやら“経営の仕組や手順を変更する場合”のことを指摘しているものと考えられます。
例えば、組織を変更した時 どうするのか。変更後の組織が機能不全にならないよう、会社全体が 組織替えする以前となんら変わりなく機能している状態を維持せよ、と言っているものと解釈できます。
余計なことですが当然、狙い通り 変更によって業務がパワーアップし効率化していることが 望まれますが、ここでは そこまでの要求ではないと考えられます。
キィワードは“完全に整っている状態”(integrity)ですね。確かに“「完全に整っている状態」(integrity)を維持している”というのは難しいという印象ですね加藤重信氏によると日本語に翻訳する時 参考のために中国人はどう訳すのか聞いてみたそうです。すると“完整性”という言葉を示したそうです。同氏は これが良いということで、日本語でもこれで行こうとしたところ“辞書に無い言葉を使うのは止めた方が良い”との意見が通って 今の規格の表現になったらしいのです。後で 良く調べたら広辞苑には 記載されている言葉だったとのことで、委員らが使った辞書は安物だった?とか。
私は“integrity”の訳語に“元のままの状態”と言うのがありますので こちらではないか、と思うのですがいかがでしょうか。つまり “「元々有った機能は果たす」ように変更しなさい。”でよいのではないかと思うのです。 (integrityには“誠実”という訳が 真っ先に来るようですが、これは 何があっても“元のままの状態である”、つまり “ブレない”→“信じられる”→“誠実”ということから来ていると思うのです。)
言葉の解釈は以上のようですが、さて それでは“完整性(元々有った機能は果たす状態)”を保って 組織替えや 仕組・手順の変更をどのように行うのか。下手すれば 最近の大企業でも起こしそうな トラブル原因となっている場合があるのでは ないでしょうか。
ここで、プロセス・アプローチの概念が重要性を帯びて来ます。つまりプロセス・アプローチを可視化したフローチャートを用いると 非常に分かり易いと思うのです。プロセスの流れをフローチャートに可視化していれば、どの業務をグルーピングするのが合理的か、プロセスの塊をパケットにして整理する見通しもつくのではないか。そうすれば 業務合理化にもつながります。
ですから 重要な仕組や手順は 必ず フローチャートにして表現しておくべきですね。そうすれば変更時の問題点も分かり易いと思うのです。
ここで 最重要のポイントは 変更後のインターフェース、プロセスの接続部分の問題です。情報や仕事の受け渡しをどのように変更したのか、変更後の状態を 関係者全員が具体的にイメージできるようになっているかが ポイントであると思います。
このあたり重要ポイントですので 何らかの変更点管理の手順として文書化しておくべきでしょう。これは規定要求事項ではありませんが考慮するべきです。また このような部分の手順については、特に、組織人事関係者は 心するべきです。
その講演で難しい要求事項として真っ先に挙げられたのが次の54.2b)項でした。
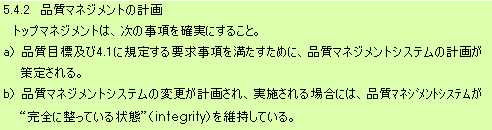
経営者の仕事だから、経営者みずから考えるべきで 我々の仕事ではない、とお思いの方も居るかも知れませんが それを言い出すとISO9001マネジメントは成立しません。
経営者は何をなすべきか。その内の計画の部分ですから重要です。
そして ここのa)項は “品質マネジメント(経営)の仕組を計画せよ”ということで 言っていることは分かりやすいです。ここで “計画”とは “経営意図を実現する仕組を企画し、手順とそのタイムテーブルを定め、確実にする、つまり実行する(品質マネジメントシステムを構築する)。”ということと解釈できます。
加藤重信氏によると a)項は“ISOシステム構築する時の人々”のための“精神的な指針”または“規範”とのことですが、この解釈では狭いような気がします。むしろ 経営者は日常的に システムに問題ないか点検し、活動を計画すると考える方が良く、システムが変更される場合にはb)項を遵守すると いうのは いかがでしょうか。
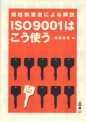
さて問題は次のb)項です。少々分かりづらいのですが、どうやら“経営の仕組や手順を変更する場合”のことを指摘しているものと考えられます。
例えば、組織を変更した時 どうするのか。変更後の組織が機能不全にならないよう、会社全体が 組織替えする以前となんら変わりなく機能している状態を維持せよ、と言っているものと解釈できます。
余計なことですが当然、狙い通り 変更によって業務がパワーアップし効率化していることが 望まれますが、ここでは そこまでの要求ではないと考えられます。
キィワードは“完全に整っている状態”(integrity)ですね。確かに“「完全に整っている状態」(integrity)を維持している”というのは難しいという印象ですね加藤重信氏によると日本語に翻訳する時 参考のために中国人はどう訳すのか聞いてみたそうです。すると“完整性”という言葉を示したそうです。同氏は これが良いということで、日本語でもこれで行こうとしたところ“辞書に無い言葉を使うのは止めた方が良い”との意見が通って 今の規格の表現になったらしいのです。後で 良く調べたら広辞苑には 記載されている言葉だったとのことで、委員らが使った辞書は安物だった?とか。
私は“integrity”の訳語に“元のままの状態”と言うのがありますので こちらではないか、と思うのですがいかがでしょうか。つまり “「元々有った機能は果たす」ように変更しなさい。”でよいのではないかと思うのです。 (integrityには“誠実”という訳が 真っ先に来るようですが、これは 何があっても“元のままの状態である”、つまり “ブレない”→“信じられる”→“誠実”ということから来ていると思うのです。)
言葉の解釈は以上のようですが、さて それでは“完整性(元々有った機能は果たす状態)”を保って 組織替えや 仕組・手順の変更をどのように行うのか。下手すれば 最近の大企業でも起こしそうな トラブル原因となっている場合があるのでは ないでしょうか。
ここで、プロセス・アプローチの概念が重要性を帯びて来ます。つまりプロセス・アプローチを可視化したフローチャートを用いると 非常に分かり易いと思うのです。プロセスの流れをフローチャートに可視化していれば、どの業務をグルーピングするのが合理的か、プロセスの塊をパケットにして整理する見通しもつくのではないか。そうすれば 業務合理化にもつながります。
ですから 重要な仕組や手順は 必ず フローチャートにして表現しておくべきですね。そうすれば変更時の問題点も分かり易いと思うのです。
ここで 最重要のポイントは 変更後のインターフェース、プロセスの接続部分の問題です。情報や仕事の受け渡しをどのように変更したのか、変更後の状態を 関係者全員が具体的にイメージできるようになっているかが ポイントであると思います。
このあたり重要ポイントですので 何らかの変更点管理の手順として文書化しておくべきでしょう。これは規定要求事項ではありませんが考慮するべきです。また このような部分の手順については、特に、組織人事関係者は 心するべきです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « “グローバルス... | 仕事、何スン... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




